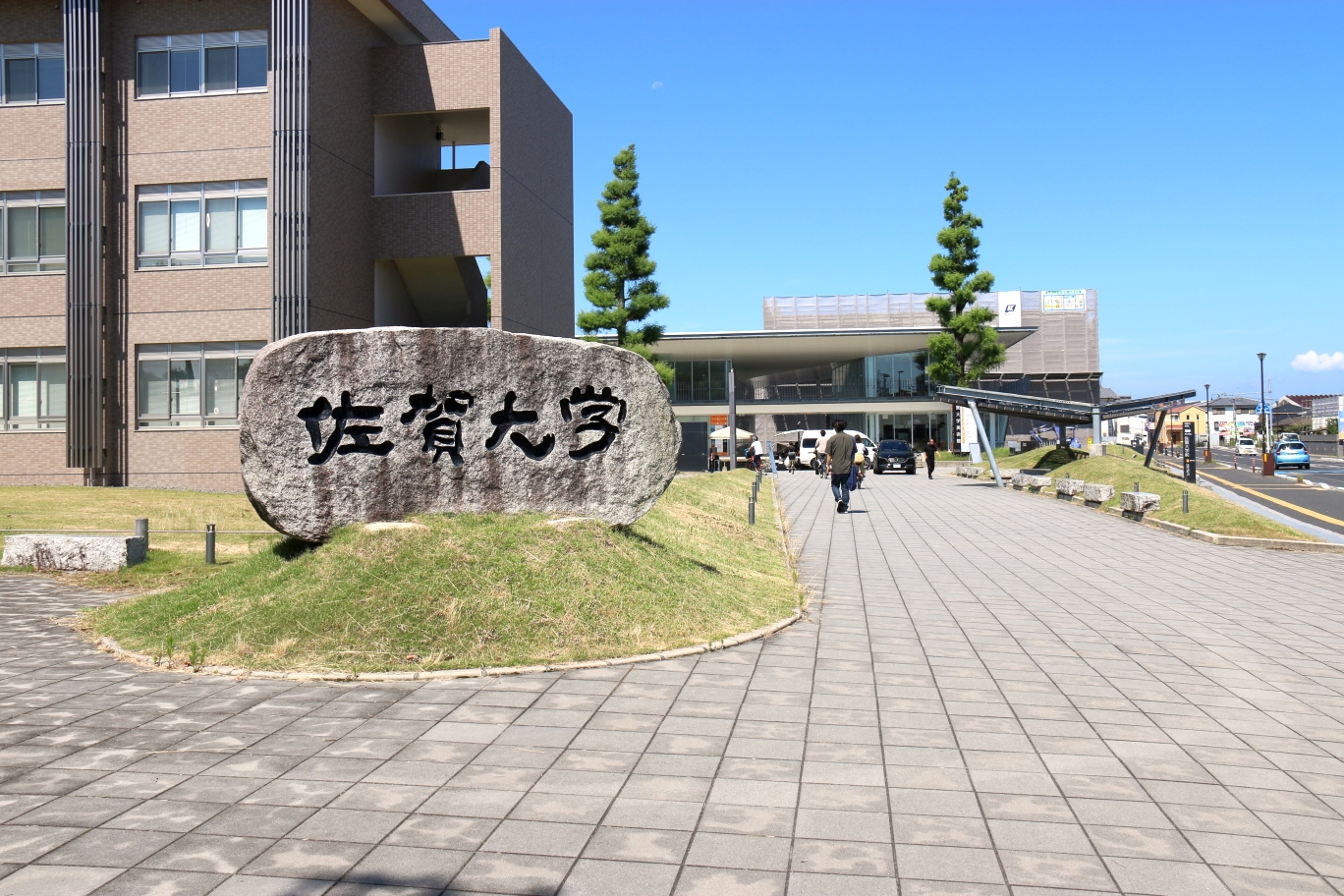学生とシニアの対話
in佐賀大学2023概要報告書
日本原子力学会シニアネットワーク連絡会(SNW)世話役 山崎智英
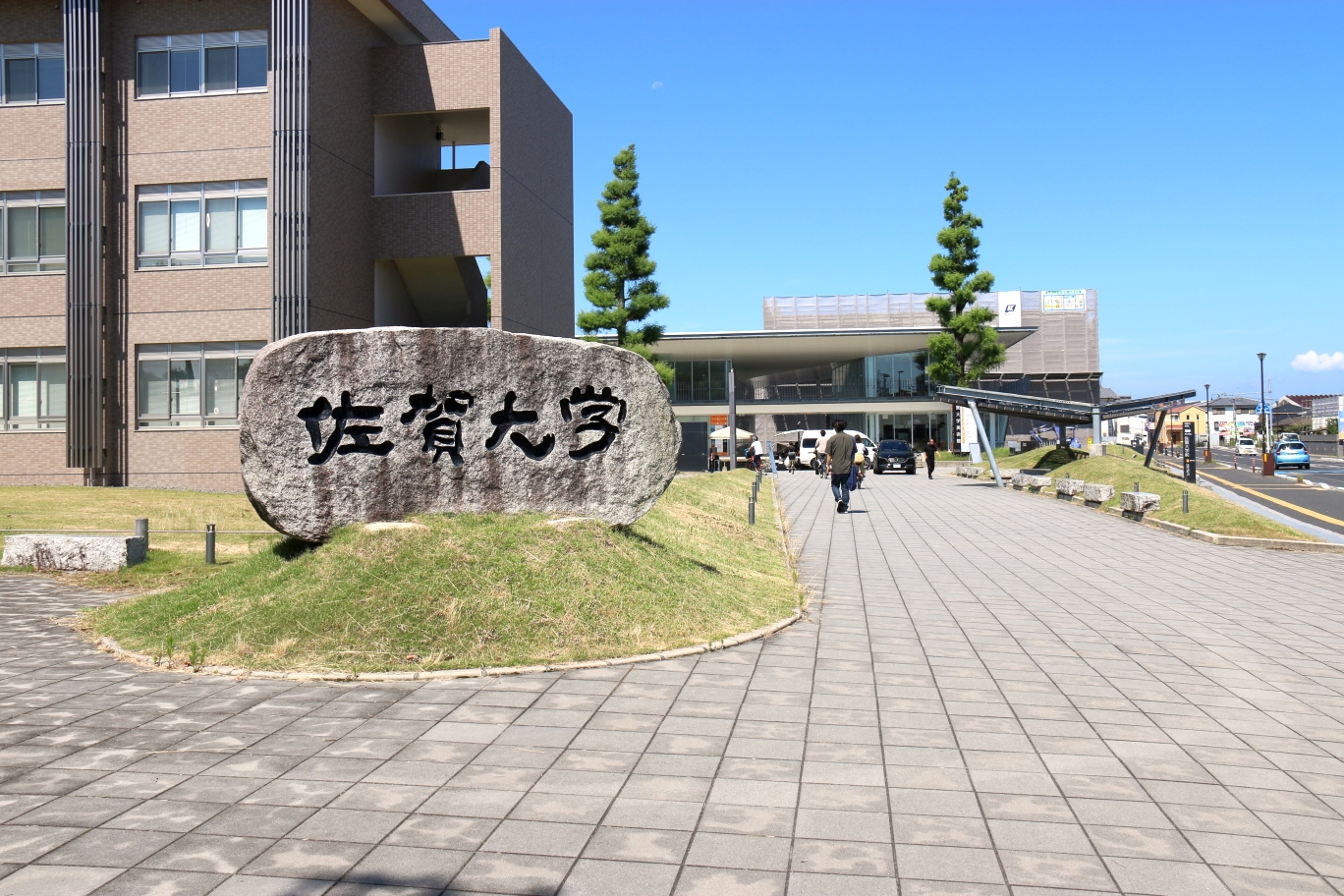 佐賀大学 本庄キャンパス
資源エネルギー概論の授業の一環として学生とシニアの対話を実施
機械エネルギー工学コース3,4年生対象選択科目「資源エネルギー概論」の授業(基調講演1コマ、対話会2コマ)で実施した。対話の導入として、「エネルギー安定供給と脱炭素への道筋」について基調講演を行った。
基調講演、対話会とも対面で行ったが、2023年11月15日に佐賀県でインフルエンザの流行発生「警報」が発表されたことから、マスク着用の対話会となった。(一部の学生はリモートにて参加)
佐賀大学 本庄キャンパス
資源エネルギー概論の授業の一環として学生とシニアの対話を実施
機械エネルギー工学コース3,4年生対象選択科目「資源エネルギー概論」の授業(基調講演1コマ、対話会2コマ)で実施した。対話の導入として、「エネルギー安定供給と脱炭素への道筋」について基調講演を行った。
基調講演、対話会とも対面で行ったが、2023年11月15日に佐賀県でインフルエンザの流行発生「警報」が発表されたことから、マスク着用の対話会となった。(一部の学生はリモートにて参加)
1.講演と対話会の概要
(1)日時
- ・基調講演:2023年11月18日(金)13:00~14:30
- ・対話会:2023年12月1日(金)13:00~16:20
(2)場所
- 佐賀大学本庄キャンパス
(3)参加者
- 大学側世話役の先生:佐賀大学海洋エネルギー研究所 光武雄一教授
- 参加学生
機械エネルギー工学コース「資源エネルギー概論」受講 基調講演:16名、対話会:13名
- 参加シニア:3グループ
針山日出夫、田中邦治、早野睦彦、小西政彦、古藤健司、山崎智英
(4)基調講演
- テーマ
- 「エネルギー安定供給と脱炭素への道筋」~エネルギー環境政策の転換期で日本の針路は?~
- 講師
- 針山日出夫
- 講演概要
- 世界主要国のエネルギー・環境政策を俯瞰しつつ、エネルギー危機への対処と脱炭素社会に向けての原子力の役割に焦点を当てエネルギー安定供給の実現と脱炭素への同時の取り組の道筋について概説。世界がエネルギー危機・脱炭素の渦中であり、このような状況下での日本の針路選択の在り方について世界主要国のエネルギー政策の最新動向について概説。
2.対話会の詳細
(1)開会あいさつ
- 世話役の山崎から、11月17日の針山さんの基調講演を受けて、本日12月1日の対話会を迎えました。基調講演の不明点、事前回答の不明点や意見などをベースに対話しましょう。シニアはみんなしゃべりたがりですので、皆さんは負けないように発言してください。
(2)グループ対話の概要
- 1)グループA
テーマ
- 日本がカーボンニュートラル実現に必要な再生エネルギー導入のあるべき姿
- 参加者
- 学生:4名(3年生3名、4年生1名)
- シニア:古藤健司、田中邦治
- 対話内容
- 人気の高いコースに入っている学生達であるためか理解力は高く優秀との印象あり。対話会での態度は誠実・真剣で、他の人の意見に頷くなど議論に集中していた。意見交換の進捗も概ね順調で全員が発言した。シニアの説明に対する反応も明瞭で、内容を理解していたと見える。対話終了後の学生達だけによる実績まとめには全員で取り組んでいた。
具体的な質疑応答・対話の内容は再エネが中心であったが、理系の学生であるためか、太陽光や風力に課題があること、安定再エネにも限界があることを理解し、原子力も活用するバランスが重要との結論に至ることができた。今回の対話を通して、エネルギーセキュリティを確保することの難しさに関する認識が深まったことは確実である。
- 以下、質疑応答の要約
-
①バイオディーゼル燃料が普及しない原因
-
- バイオ資源の確保耕作地化による森林破壊、農産植物価格への影響、燃料製品の品質安定化、コストなどの課題を確認。
-
②2050CNの実現可能性
-
- 変動型再エネによる送配電系統への影響、大容量蓄電システムの必要性、そのコスト、安定型再エネの限界、CCUS立地の見通し、大量水素供給のコスト、大気中CO2除去の量的実現性、Sharing economyの効果など様々な課題があることを確認。
-
③太陽光が増えた場合の電気料金の見通しと問題点
-
- 安くなる見通しの乏しいこととその理由、系統制御などの課題を説明。
-
④再エネで日本が優位な技術、取り組んでいる企業
-
- 中国にシェアを奪われている現状、ペロブスカイト太陽電池の研究開発、潮力発電などを説明。海洋エネ利用に関心のある学生は参考となる図書が見つからず困っているとのこと。
-
⑤再エネ導入比率の最適解とそれを阻む問題の有無
-
- 基本政策分科会での議論、日本の不利な自然条件、調和電源ミックスなどを解説。
-
⑥原発再稼働と再エネ新規建設のコスト比較
-
- 既設炉の再稼働と運転期間延長が有利となり得ること、その原因は再エネの利用率の低さにあることを説明。
-
⑦再エネを利用した地産地消の実例
-
- 弘前、藤沢、久留米に実在する例を紹介。
-
⑧遠距離送電の可能性
-
- 遠隔電源から需要地への送電は技術的には可能だがコストに問題あり、逆に分散電源による配電線の問題もあることを解説。
-
⑨再エネのコスト高の理由とその削減に必要な技術開発項目 -
- 出力密度の低さ、利用率の低さ、送配電系統の強化と制御、安価な蓄電技術の開発ニーズを説明。
-
⑩メタンハイドレードの可能性 -
- コスト、CO2排出を説明。
-
⑪大気から炭化水素を合成するドリーム燃料の可能性 -
- エネルギー収支、産業規模利用の実現性に疑問があることを回答。
-
⑫地熱発電の見通し -
- 開発コスト、温泉地の理解獲得、利用率漸減などの課題から限界があることを説明。
- 2)グループB
テーマ
- 高騰するエネルギー価格への対策と我々が取るべき姿
- 参加者
- 学生:5名(3年生4名、4年生1名)
- シニア:山崎智英、早野睦彦
- 対話内容
- シニア、学生それぞれの自己紹介の後、事前質問に対する回答について更なる疑問やコメントを下に意見交換した。ファシリテータは山崎氏が務めた。
- 学生の質問やコメントは多岐に亘ったが、纏めると以下の項目に関するものになるかと思う。
-
①原子力に関する理解活動について
-
- 新規制基準で原子力の安全性が高まったと言うが、果たしてどこまで国民理解が進んでいるのか?メディアからはネガティブな報道が多い。年代別、地域別、性別等に区分けした理解活動をやっているのか。⇒メディアは「売らんかな」の立場から一般的にネガティブ報道に傾きがち。電力は見学会や出前授業など地道な活動をしているが、信頼を得るのは地道な努力が必要なのに対して信頼を失うのは一瞬なのが現実である。
-
②再エネに関する新技術の可能性
-
- ペロブスカイトなど新技術開発はどんどん進んでいるし、出力変動への対応(例えば、送電網の充実、蓄電能力の拡充等)も推進されているが、いかにも効率が低すぎて限界がある。再エネ(太陽光、風力発電)についても我が国は恵まれない環境にある。
-
③核融合等原子力技術に関する可能性
-
- 我国の科学技術に対する投資が低く、これでは技術後進国になるのではないかと心配である。⇒技術の研究開発と社会実装の間には深いダーヴィンの海がある。核融合はまだまだ先の技術である。また、我国は欧米に比べてすべての分野に投資するだけの資力を持ってはいないので選択と集中が必要である。
-
④電気料金の決め方と大衆運動の効果について
-
- 電力は国の基盤を担う公益事業である。大衆運動によってその料金が左右されるものでもないし、また左右されるべきものでもない。電力自由化以前は総括原価方式で国会の承認を以て決められていた。現在も送配電については同様であるが、正に国の在り方を問う問題である。
- 最後に、エネルギーの本質について話をし、始まったCOP28などエネルギーを考えることは世界を考えることとして視野を広げるよう話をした。
- 3)グループC
テーマ
- 原子力エネルギーの利用拡大と安全性担保
- 参加者
- 学生:4名(3年生2名、4年生2名)
- シニア:小西政彦、針山日出夫
- 対話内容
- 自己紹介の後、事前の質問に対するシニアからの回答、シニアからの逆質問、対話席上でのシニア/学生双方からの意見交換で出た問題点/指摘について対話を重ねた。
- 以下、意見交換での主な話題(順不同)
-
①福島原発処理水放出に係わる安全性
-
- -中国の反発とそれへの対処の在り方(科学技術論vs外交政策)
-
②原子力発電所の新安全規制基準と安全性
-
- -自然災害に対する規制強化全般と立地条件
- -事故後の事態収拾に対する計画・配慮
- -「安全」を如何に定義するか、残余のリスクへの配慮と自主的安全性の追求
-
③資源国・オーストラリアのエネルギー事情
-
-
④ウランの埋蔵量と可採年数
-
- -ウラン資源の存在箇所と最近の需給バランスと地政学的リスクの俯瞰
-
⑤使用済み核燃料貯蔵容量
-
- -サイトでの貯蔵容量のひっ迫状況
- -各種対策(容量追加増加、乾式中間貯蔵など)
-
⑥新規建設
-
- -サプライチェーンの状況、産業界の設計・製作能力、建設技術力
-
⑦福島発電所における地下水の流入対策
-
-
⑧福島廃炉について
-
- -廃炉技術の問題点(特にデブリ回収)
- -廃炉ではなく、石棺方式を選択しなかった理由など
-
⑨2050CNと水素戦略
-
- -クリーン水素の製造コスト
- -日本の水素基本戦略と想定導入量、貯蔵・輸送の問題点
-
⑩小型炉の将来性
-
- -経済性と固有の安全性
3.講評
- 光武教授
- 本日の対話会では、原子力、再エネ、エネルギーコスト高騰のテーマでの議論を通して、将来のエネルギー問題やリスクについてヒントが得られたのでないか。学生はCN達成目標時期に社会の中枢で働く世代であり、日本の将来を背負っていく必要がある。そのため、幅広い視点を持つことが重要。また、シニアに対して謝辞が述べられた。
- 早野睦彦
- 皆さん、今日の対話会ご苦労様でした。我が国の将来に影響するエネルギー問題についてこの対話会で少しは勉強していただけたかと思います。
いま、ロシアのウクライナ侵攻で世界中が混乱しています。日本はこれからもエネルギーをどうやって確保していくかが大きな問題になっています。また、イスラエル問題も中東のエネルギーに依存する我が国にとってエネルギー安全保障上の大きな問題を内在しています。東アジアに目を向ければ中国が強大な軍事力を背景にして東南海域に出てきています。北朝鮮はミサイルを次々に東シナ海、日本海に発射しています。エネルギーを考えることは世界を考えることとはまさしくこのことです。
このようにリスクは常に存在しています。これから10年、20年経てば皆さんは立派な社会人になって社会を動かしていく責任があります。その時には我々シニアはもういません。そこで皆さんに行っておきたいことがあります。
世の中にはいろいろなリスクがあって、リスクのない世界はありません。数多くのリスクを克服してきて今の文明社会があります。皆さんはこれからいろいろなリスクに出会うことになりますが、感情に流されることなく、科学的で合理的な判断をしてほしいと思います。そのためには多くの知識と見識が必要です。その意味で今日の対話会が少しでも役立てば、我々シニアがここに来たかいがあると思っています。
さらに質問したいことがありましたら、光武先生を通してメールを出してもらえれば、回答いたします。
4.学生アンケートの概要
(1)参加学生について
アンケート回答者は13名で、回収率は100%。
7名が進学、6名が進学を希望。
(2)対話会について
講演は、100%の満足度であった。事前に聞きたいと思っていたことは、「十分」、「ある程度」聞けたが併せて100%、今後聞きたいテーマは、核融合の開発状況などが挙げられた。
(3)意識調査について
放射線・放射能については、「一定のレベルまでは恐れる必要はない」、が92%、「レベルに関係なく怖い」が8%であった。
原子力については、「再稼働を進めるべき」が62%、「新増設、リプレースを進めるべき」が23%、「2030年度目標を達成すべき」が15%であった。
再エネについては、「利用拡大を進めるべき」が46%、「利用は抑制的にすべき」が54%であった。
アンケート結果の詳細は、別添資料を参照ください。
5.別添資料リスト