学生とシニアの対話
in佐賀大学2022概要報告書
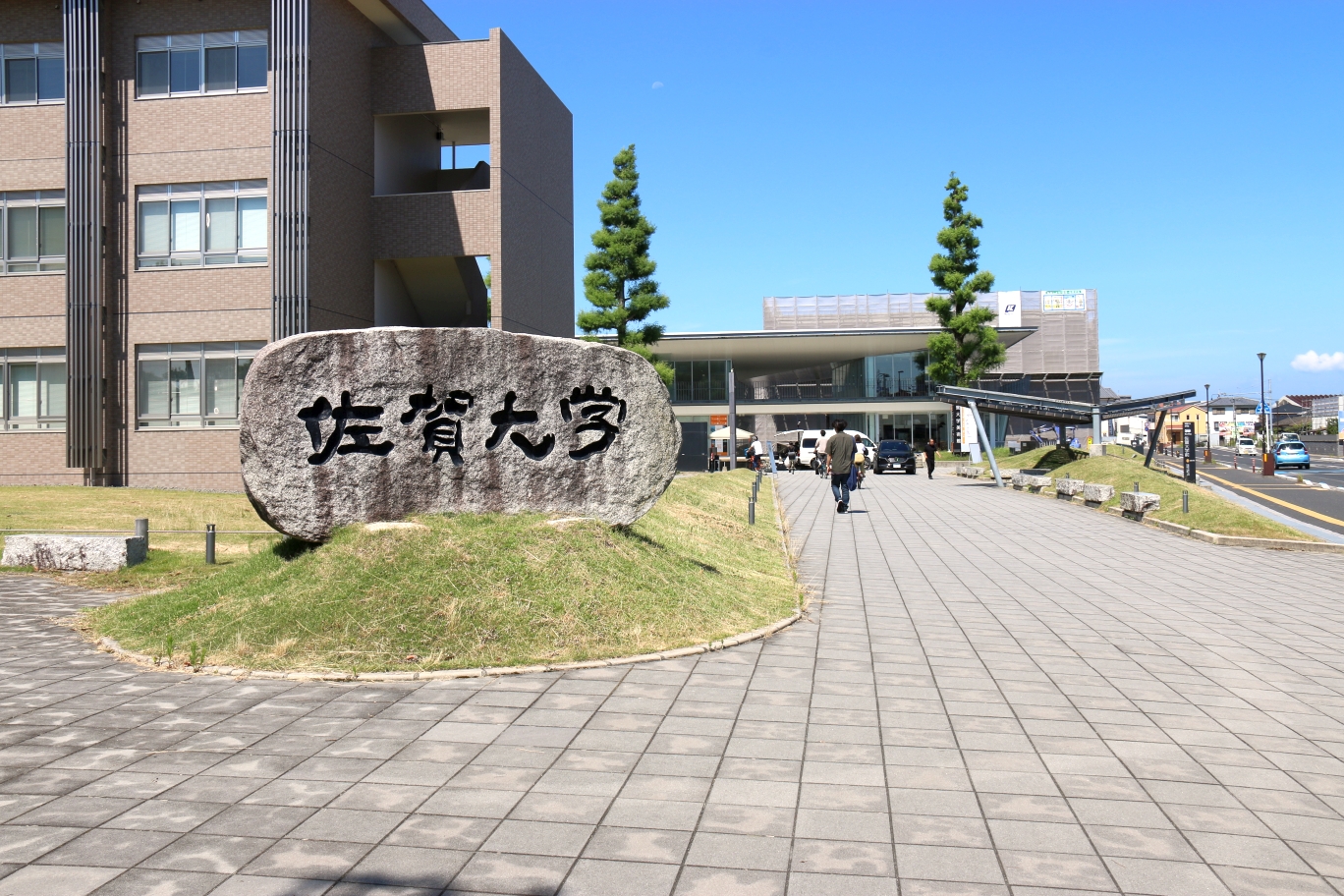
1.講演と対話会の概要
(1)日時
- 基調講演:2022年11月18日(金)13:00~14:30
- 対話会:2022年12月16日(金)13:00~16:30
(2)場所
- 基調講演:佐賀大学本庄キャンパス
- 対話会:リモートオンライン方式
(3)参加者
- 学生:理工学部理工学科機械エネルギー工学コース「資源エネルギー概論」受講 学部3年生13名、4年生4名(合計17名)
- 教員:佐賀大学海洋エネルギー研究所 光武雄一教授
- シニア:金氏顯、中村威、小西政彦、古藤健司、松永一郎、梶村順二、山田俊一、針山日出夫、山崎智英、米丸賢一(オブザーバ)
(4)基調講演
- テーマ:「世界主要国のエネルギー政策の最新動向」~脱炭素・欧州発エネルギー危機の中で日本の選択は?~
- 講演者:針山日出夫
- 講演概要:世界がエネルギー危機・脱炭素の渦中であり、このような状況下での日本の針路選択の在り方について世界主要国のエネルギー政策の最新動向について概説。
2.対話会
(1)グループA
- 1)参加者
- 学生:4名(3年生)
- シニア:金氏顕(ファシリテータ)、中村威、小西政彦
- 2)主な対話内容
- テーマ:原子力発電所再稼働と経年プラントの安全性の課題
- ①事前質問は4人で17問と多かった。
・分類すると、原子力関係が13問、再エネ関係が3問、学生時代の過ごし方が1問。
・原子力関係では、原子力の再稼働の為の安全審査、機器取替など経年劣化対策費用と経済効果、耐用年数、廃炉工事など運用に関する質問が最も多い。次いで、原子力発電の運営に必要な技術、立地条件、次世代革新炉の要件など。また、原子力に反対する意見は何か、という質問もあり、原子力に大変関心を持っていることが伺われた。
・変わったものでは「将来の日本の為に学生が出来ることはなにか?」という質問があった。 - ②これらについてシニア側で回答を分担作成、まとめた上で学生側に送信。当日(12月16日リモート対話会)、それについて説明を加えるとともに、シニア側から、ではそれについて学生としてどう考えるかなどの逆質問をすることにより、対話を進めていった。 当初学生5人の参加予定であったが、当日は4名となった。対話はスムースにファシリテータのリードのもと、元メーカー、電力関係で長年仕事をしてきた経験などを通して我が国の原子力発電の現状など説明するとともに、原子力について勉強することは多い、とくに、外国語を身につけることは自分の道幅を広げることが出来るなど経験も話した。
- ③この数年のコロナ問題や原子力規制の強化などにより現物を見る機会が減っていることなどが、これからの学生達の学びの場を狭くしていることなども知ることが出来た。
- ④発表会では、対話を通して解決したことや、一方まだまだ原子力には課題もあることなど報告されたが、学生時代に、技術者としてこの国をどうしていきたいのか、何を今やるべきかなどの発言もあり、そのような意識を少しでも持ってくれたことなど対話会の成果ではなかろうか。今後の彼らに期待したいものである。
(2)グループB
- 1)参加者
- 学生:4名(3年生)
- シニア:古藤健司(ファシリテータ)、松永一郎、米丸賢一(オブザーバー)
- 2)主な対話内容
- テーマ:再生可能エネルギー利用拡大に伴う課題と日本のエネルギー関連産業の将来
- 学生から事前に提出された20の質問と、回答に沿って対話した。
- ①再エネ設備を大量に設置した場合の環境への影響
太陽光発電では環境アセスメントの義務付けが遅れていたために、各地で山林の乱開発が進んで、土砂崩れなどの原因になっている。また景観などへの悪影響もある。そのため、全国の自治体の1割に当たる180の自治体が独自に規制条例を作っている(2019)。風力発電ではバードストライクや景観への悪影響がある。日本の利用可能な国土面積当たり太陽光発電設置率は世界1であり、余地は少ない。 - ②再エネの発電コストと他の発電方式の比較
太陽光発電や風力発電はエネルギー密度が低く、また稼働率も低いので発電方式に比べて高い。ただ、太陽光発電については低価格の中国製パネルが出回り、火力発電コストに近づいている。
新規太陽電池素材としてペロブスカイトが期待されており、これが実用化されると多様な普及が期待できる。 - ③風力発電や太陽光発電などの不安定電源に頼ってよいのか
これらの電源は天気まかせ、風まかせなので必ずバックアップ電源が必要になる。したがって電源の全部を頼ることはできないが、エネルギー自給率や脱炭素の観点から一定量は必要である。それには、エネルギーベストミックスの考え方が必要である。SNWでは独自にこの値を検証している。それによると、水力などの安定再エネを含む再エネ、原子力、脱炭素つき(CCUSなど)化石エネルギーがそれぞれ1/3ずつとするのがよい。
なお、大容量蓄電池が安価に使えるようになれば離島などでローカルシステムとしての「スマートグリッド」などが考えられる。 - ④水素製造用としての再エネの利用、製造した水素の自動車燃料としての利用
製造用としては効率が悪い。水素自動車はまだまだ問題が多く、普及に時間がかかる。 - ⑤学生の今後の進路などについて話し合った。
2)グループC
- 1)参加者
- 学生:4名(3年生)
- シニア:梶村順二(ファシリテータ)、山田俊一
- 2)主な対話内容
- テーマ:化石燃料脱却に伴うエネルギー安定供給の課題とエネルギー自給率向上
- お互いに自己紹介してアイスブレイクを行ったのち、事前質問に対する回答内容を確認しながら、追加質問を受け、適宜、シニアからも質問を行う形で対話を進めた。
- 学生からの事前質問20問の一部とシニアからの説明ポイントは以下のとおり。
- ①再生可能エネルギー導入の具体的問題点。
再エネ比率が高まれば、バックアップ電源も多く必要で過剰投資となる。安い蓄電池はまだ開発途上のため、系統バランス費用が高くなる。 - ②原子力発電所再稼働に時間が掛かりすぎている理由は何か。 新しくできた規制基準をどのように解釈するか規制側、申請側双方が手探りの状況で審査に手戻りが多く発生した。また基準地震動の策定に時間がかかった。
- ③脱炭素社会に向けて世界各国が原子力と再エネによる発電に舵を切るなかで、化石燃料のニーズはどのようになっていくと考えるか。
世界的なCO2削減の動きで、化石燃料資源開発に投資されなくなり、化石燃料の価格高騰を招いている。また、国際取引で炭素税が付加されるか、商品取引されなくなることも懸念される。日本は国際情勢を見つつ賢く立ち回る必要がある。 - ④東日本大震災による原発事故で放出されて長期に地域を汚染した、人間に悪影響がある放射能などはもっと早く除去できなかったのか、方法が知りたい。
福島事故で環境の放射線量を長期にわたって上昇させたのは主にセシウム134(半減期約2年)とセシウム137(半減期約30年)。除去するには、物理的に取り除くしかない。 - 参加してくれた四人の学生に、対話の途中で原子力発電を使うことについての自身の考えを聞いたところ、四人とも原子力発電は活用すべきとの考えを持っているとのことであった。論理的に考えれば、日本では原子力発電を活用すべきであるが、なぜ再稼働が進まないのかという疑問と、自給率向上に貢献できる再エネの課題は何かということが対話の焦点であった。
3)グループD
- 1)参加者
- 学生:4名(3年生3名、4年生1名)
- シニア:針山日出夫(ファシリテータ)、山崎智英
- 2)主な対話内容
- テーマ:自動車の電動化とその効果と産業構造への影響・地球環境保全の課題全般
- 学生から事前に提出された質問と、シニアの回答に従って対話を行った。
- ①ガソリン車が排出するCO2の量は、電力会社の電源構成(CO2排出量がゼロの再エネ、原子力の割合が多い)によって上下する。
- ②車が走行時に排出するCO2だけではなく、発電・製造から廃車まで含めた評価(ライスサイクルアセスメント)を行うことによりCO2排出量を低減することが重要。
- ③日本は、EV車化に伴う自動車産業の隆盛により納税、外貨獲得、雇用に大きな影響を受けることとなる。
- ④日本のCO2排出量削減のためには、需要面と供給面の両面からのアプローチを行い、カーボンニュートラルを達成する必要がある。
- ⑤雇用不安や産業構造変更がおきたときには、新しい技術・新しい管理方法・新しいコミュニケーションが社会に実装されるため必要な雇用の変化も現れる。
3.講評:松永一郎
本日は長時間におよぶ対話会、ご苦労様でした。
この対話会は確か対面で行われる予定でしたが、コロナの影響で昨年同様にZOOM方式となりました。それでも発表内容から、皆さん良い対話ができたようです。
4つの対話テーマは、11月18日の針山さんの講演内容に必ずしも直結したものではなかったかもしれませんが、皆さんからの事前質問を読んだ限りでは、皆さん、自分なりにそれと関連付けて、それなかなか的をついた質問をされていました。シニアからの逆質問もたくさん出されており、それに対して自分なりに考えて、対話した後が伺われました。
光武先生の「資源エネルギー概論」でどのようなことを学ばれているか知りませんが、本日の対話は自分たちの資源エネルギーを多角的に見る目を養う訓練になったことと思います。
すべての基本は得られた知見から、自分の頭で考えることです。これは皆さんの将来にとって、必ず役に立ちます。
来年度の対話会に出られるかどうか分かりませんが、是非、対面で実施されることを期待いたします。
4.学生アンケート結果の概要
- 授業だけでは得られない現場のリアルな意見を聞き、知見を深めることができた。
- エネルギー問題、原子力や再エネについて見識を深め、日本や世界がどのようなエネルギーと向き合うべきかと自分なりに考えるきっかけとなった等、概ね好意的な意見が多かった。
- 対話の時間が短く、聞きたいこと全てを聞くことができなかったという意見もあったことから学生の質問をうまく引き出すなどの工夫が必要と思われる。