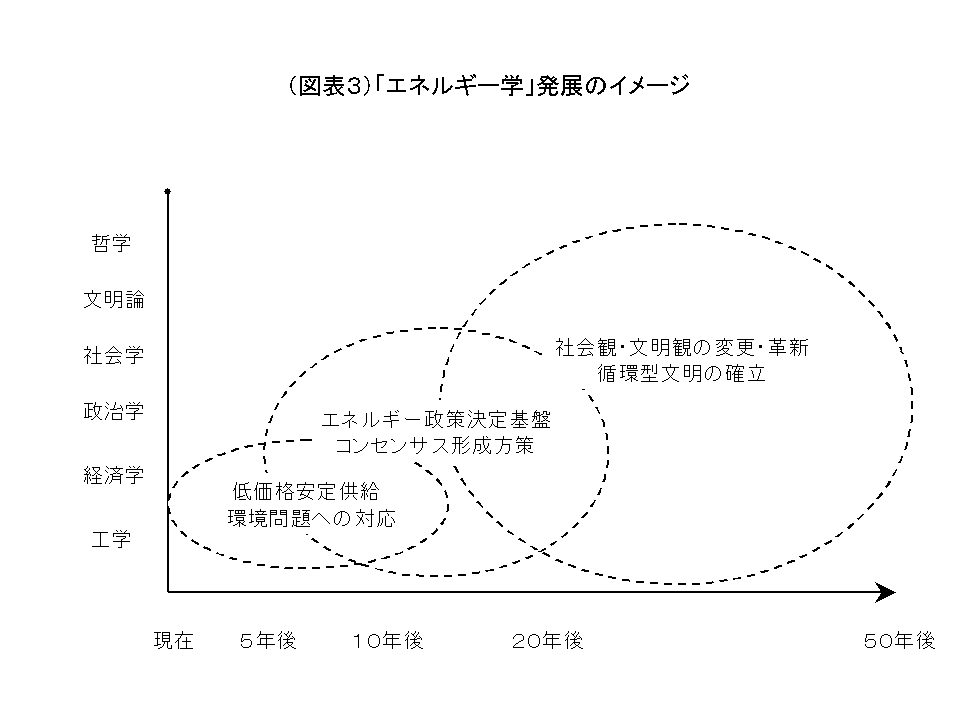パネル冒頭発言要旨
エネルギーレビュー 2000.3 「原子力学」と「エネルギー学」 を参照してください。
通商産業省 総合エネルギー広報企画官
通商産業省 原子力発電課 企画官
科学技術庁 原子力利用計画官
国吉 浩
2.「原子力学」
日本原子力学会は、昨年、原子力に関連した社会・環境分野の研究活動を支援し、その発展に貢献するため、「社会・環境部会」を設置した。昨年9月には、「社会・環境部会の使命と課題---新しい『原子力学』の確立を目指して」をテーマに、パネルディスカッションが開催された(座長:金子熊夫東海大学教授、概要は http://picaso.q.t.u-tokyo.ac.jp/sed/kasiwaPD.htm
を参照)。
私はパネリストとして、ディスカッションに参加する機会に恵まれ、「原子力学」について論じた。ここではその時の発表を基に、私の考える「原子力学」を紹介する。
(1)「原子力学」の目指すべきもの
◇社会的存在である原子力
核燃料の輸送や原子力発電所の些細なトラブルでさえも、大きく報道されるのを目にするたびに、原子力が「普通の」エネルギーであれば良いのに、と思う。しかし現実問題として、原子力は「社会的」存在である。原子力のエネルギー利用は、国の政策如何によって大きく影響を受け、原子力施設の建設は、その地域にとって「普通の」大規模施設の建設以上の意味合いを持つ。
昨年9月末のJCOの臨界事故は、原子力施設で事故が起こった場合の地域社会への影響の大きさを実証する形となった。JCO事故は施設周辺にまで安全性に関わる影響を与えた我が国最悪の事故であるが、安全が確保された原子力施設であっても、その存在は、政治的、経済的、社会的に地域社会へ影響を与える。
エネルギーシステムとして工学的に捉えれば、原子力発電所は、他の発電システムと相対化し得るが、現実社会において原子力施設は、特別な存在なのである。それが「社会的」事実である。原子力関係者は「工学的」事実こそが正しく、それが社会に理解されないと考えがちだが、「社会的」事実も、別の形態の事実として認めることが必要であろう。
◇原子力の軍事利用防止
一方、原子力に別な意味で社会的特殊性を与えているのは、軍事利用の可能性である。日本における原子力利用が平和の目的に限られることは当然だが、それは決意を表明すれば足りるものではない。保障措置や輸出管理などの核不拡散へのたゆまざる努力があってこそはじめて、平和利用を進めることが許されるものである。
軍事転用の防止は、平和利用の基盤であり、単なる義務以上の積極的意味合いを持っている。軍事転用の可能性が少しでもあるということになれば、一切の平和利用が許されないものとなる。すなわち軍事転用の防止なしには、平和利用は存在し得ないのである。
◇原子力システムの総合評価
原子力システムが持つ様々な特徴を、他のシステムと比較して、社会の中での位置付けを明確にしていくためには、環境負荷、燃料の安定供給性、経済性、リスク、廃棄物処理処分等の総合的な評価が必要である。
現状では、往々にして、原子力発電は発電中に二酸化炭素を排出しない、放射性廃棄物処理の問題が未解決である、等それぞれの観点からの主張がなされ、議論がかみ合わない。いろいろな観点からの評価に関し十分研究を進めるとともに、それらを総合した形でのシステムの評価を可能とすることが求められる。
◇「原子力工学」から「原子力学」へ
原子力工学はそもそも、原子力の平和利用という目的のために、多様な工学分野の知識を結集して創られた総合工学である。今、社会的存在である「原子力」を考えるときに、従来の工学的アプローチを核にしつつも、工学の枠を越えて、経済学、政治学、社会学等、様々な学問分野の知識の総合、融合を図ること(=新しい「原子力学」の確立)は、自然の発想であろう。そうしてこそ、はじめて「原子力」の在り方を探求することができるものと考える。
◇「原子力学」の目指すべきもの
このような「原子力学」の直接的効果は、原子力に関わる問題解決のための、学問的手法と知識の1セットの提供である。この意味では「原子力関連問題解決学」と言った方が適切かもしれない。これはまた原子力問題を考える際に知っておくべき知識のセットとも言えるので、そのまま「原子力教育カリキュラム」にもなり得る。さらに、これらの実用的な役割にも増して期待すべきは、原子力に関連する各学問領域の知識、方法論の融合により、新しい価値、学問が創造されることであろう。
(2)「原子力学」へのアプローチ
◇「モード2」的アプローチ
ここ数年、「モード2」という言葉を良く耳にするようになった。ディシプリンに基礎を置く従来型の研究活動の編成様式をモード1とし、これに対し、モード2と呼ばれる新しい知識生産様式が出現しているというものである(図表1)。モード2においては研究課題はアプリケーションのコンテクストで決まり、その課題解決のため、特定のディシプリンからだけではなく、広汎な領域からの参加(トランス・ディシプリナリ:インター・ディシプリナリ(=学際的)ではないことに注意)が求められる。
ここでは詳細は省くが、「原子力学」に期待されるのは、正にこのモード2的知識生産活動ではないだろうか。既存の個別学問分野の中で片づく課題であれば「原子力学」は必要なく、課題解決のために広汎なディシプリンからの知識と方法論の結集が必要な場合にこそ、「原子力学」が活きてくるものと考える。
◇「原子力学」の対象のイメージ
それでは「原子力学」とは何を研究する学問であろうか。研究対象のイメージを示したのが、(図表2)である。先に述べたように、原子力学の研究すべき領域は、『社会(public)との関わり』『軍事利用防止』『システム総合評価』である。図から分かるように、これらの領域は、様々な学問の知識、方法論を総合して対応することが望まれる分野である。
『社会との関わり』を例に若干説明をしておくと、例えば原子力に関する「政策決定過程」の研究には、工学的評価はもちろんのこと、政治学、社会学、社会心理学等、さまざまな学問分野からのアプローチを総合することが必要であろう。さらにこの「政策決定過程」は、「リスク評価・管理・コミュニケーション」「地域振興」「メディア、教育」等他の項目とも密接に関連しており、最終的には、『社会との関わり』全体として、総合的アプローチが必要となるのである。
『軍事利用防止』『システム総合評価』については、関係する学問分野の記載を省略してあるが、『社会との関わり』同様に、工学、経済、政治、社会等、様々な学問分野からの総合的アプローチが求められることは明らかであろう。なお広い意味では、これら3領域全てが、社会との関わりとも言えるので、図の『社会との関わり』には、publicと挿入して、意味を限定した。
◇広がりより融合を重視
「原子力学」というような学横断的、総合的アプローチを考えると、得てして大きな姿を描く誘惑に駆られる。例えば「原子力学」の場合だと、世界のエネルギー需要想定、長期的気候変動の評価、冷戦後の安全保障枠組み、といったもの全てを対象にする考えもあるだろう。
しかしそれでは、「原子力学」が無限に広がり、発散してしまいかねない。むしろ前述の3領域のように、原子力特有の側面を対象にしているものに限定すべきだろう。図で「平和利用のための」としているのも、核軍縮、核戦略といった純粋に軍事の領域を対象から除外するためである。そのように対象を絞り込んでこそ、相互触発、融合が期待でき「原子力学」というアプローチに価値がでるのである。
3.「エネルギー学」
昨年2月に、日本学術会議「社会・産業・エネルギー研究連絡委員会」は、「21世紀を展望したエネルギーに係る研究開発・教育について」と題する報告を出し、その中で、「エネルギー学」の創出、進展を提言している。
世の中で「エネルギー学」という言葉が使われるのは、これが初めてではない。93年には既に、科学研究費の中に「エネルギー学」という項目が採用されている。また、エネルギー・資源学会長の茅陽一慶応大学教授は96年に、同学会誌に「エネルギー学を考える」との巻頭言を載せており、山地憲治東京大学教授は97年に、ILLUMEに「いま、エネルギー科学からエネルギー学へ」と題する論文を書いている。日本エネルギー学会の学会誌でも、97年に谷口富裕東京大学客員教授が「エネルギー学」の確立が重要と指摘している。ただし、それぞれの主張の中味を見ると、考えていることは必ずしも一致していない。ここでは、私なりの「エネルギー学」の輪郭を描いてみたい。
なお、前述の学術会議の連絡委員会は、その後も「エネルギー学」について議論、検討を続けているので、この原稿が掲載される頃には、学術会議としての「エネルギー学」に関する考え方も報告書の形で示されているかもしれない。当然それは以下に述べる「エネルギー学」のイメージとは異なるものだろうが、様々な提案があることは「学」の概念形成上良いことと考え、敢えて本稿で私なりの概念提案をさせてもらう。
(1)「エネルギー学」の目指すべきもの
◇なぜ「エネルギー学」か
まず基本的な問いが、なぜ「エネルギー」にだけ、特別にそれ専用の学問が必要なのか、ということであろう。その必要性はエネルギー問題の特殊性から来る。
エネルギーは、我々の社会に不可欠な基盤となるものであり、それ故に人間の活動、社会、政策と密接に関連している。従ってエネルギー問題を取り扱うには、工学だけに留まらず、様々な学問からの総合的アプローチが求められるのである。これは、同様に人間の社会活動の基盤である情報について、「情報学」を確立する動きがあるのと良く似ている。
エネルギー問題にはさらに、長期性、グローバル性、エネルギー市場を通してのエネルギー源の相互関連性、エネルギー需給全体としてのシステム(構造)性等があり、問題を複雑にしている。特に近年、エネルギー問題は広がりを増してきており、既存の学問体系に納まらなくなってきた。これに対応するために、様々なアプローチの総合化が必要であり、それが正に新たな「エネルギー学」に求められているものなのであろう。
◇「エネルギー学」の目指すもの
以上のような考えに基づけば「エネルギー学」の目指すところは、「エネルギーという対象を人間(社会)が扱う際の諸問題」の解決ということになる。
エネルギー問題には、エネルギーの低価格安定供給、環境負荷低減、枯渇性エネルギーの保存、循環型社会の確立等、観点、時間軸に応じてたくさんのものがあり、またそれらが相互に密接に関連し合っている。従って、「エネルギー学」の対象とする問題とは、エネルギーという対象を人間(社会)がどう扱い、その利用をどう律していくかという観点からの(独立した要素に分解できない)問題の総体といえるだろう。
(2)「エネルギー学」へのアプローチ
◇モード2的アプローチ
「エネルギー学」が目指すものが、エネルギー問題の解決であれば、課題解決型、トランス・ディシプリナリという意味で、「原子力学」同様、モード2的学問となる。
これは必ずしも短期的問題解決を期待することを意味しない。地球環境問題、化石資源の枯渇等、エネルギー問題は長期に亘る傾向が強い。問題の存在自体は今から明らかであっても、問題が現実化するのは将来であり、その解決にもまた時間を要するものが多い。ただしターゲットは長期になるが、モード2的取り組みは直ちに行っていく必要がある。
◇「エネルギー学」の発展
エネルギー問題に対するモード2的トランスディシプリナリなアプローチが、学問領域間の相互触発、融合を促し、新たな学問的価値を生むことによって、「エネルギー学」が形成されていく。現在でも既に、エネルギー需給や環境負荷の評価などには、工学と経済学の手法が一体となって用いられている。これは「エネルギー学」の原型と言えるのではないか。
一方、前述したように、エネルギー問題の中には、その解決に時間をかけざるを得ないものも多い。その場合、関係学問領域の融合が起こるのに時間がかかることも想定される。例えば、社会観・文明観を変革し、エネルギーの多消費をしない世界を作るためには、工学や経済学のアプローチに加え、政治学、社会学、さらには文明論、哲学まで幅広い学問分野が融合化した対応が必要かもしれない。それには数十年のオーダーが必要であろう。
このように「エネルギー学」は対象とするエネルギー問題の時間スケールに併せて、段階的に発展すると考えたい。(図表3)にその発展のイメージを示しておく。もとより将来の学問の発展方向を今から判断することは不可能であり、あくまで例示である。また図の時間軸は、「エネルギー学」として、融合した新たなアプローチや価値が生まれるタイミングを示したものであり、それぞれの学問の観点からのモード2的アプローチの試みは直ぐにでも可能であり必要である。
4.おわりに
JCO臨界事故の事故調査委員会の報告書(昨年12月)は、工学的分析・評価を越えて、社会科学・人文科学的視点を多く取り入れたものであった。また、現在、新しい原子力長期計画について検討が進められているが、その議論の中でも工学的視点に加えて、社会科学的、人文科学的観点からの議論が多く行われている。「原子力学」という名前を付けるかどうかはともかくとして、原子力を対象とした、いろいろな学問分野の総合化は現実に始まっているのである。
エネルギーについても、総合的評価、検討の重要性が、新聞等メディアをはじめ各方面で言われている。大学でも社会科学系まで含めた「エネルギー科学」の研究科などが作られるようになってきた。「学」としての概念の確立は後追いになるかもしれないが、「エネルギー」を対象とした総合的研究を進めることは、疑いなく時代の要請である。
将来「原子力学」や「エネルギー学」が確立し、原子力やエネルギーの問題解決に役立つことを期待するが、その取組の過程でも、異なる専門分野の人達がお互いの問題意識を理解し合い、原子力やエネルギーに関する社会的議論が深まるという効果を期待できよう。
なお、留意すべきは、これらの学問は価値中立的であるべきだということである。原子力立地の推進を目的とするものでも、PAのためでもない。結果的に役立つこともあり得ようが、それを目的としたとたんに、学問として成り立たなくなるものと思う。
以上、「原子力学」と「エネルギー学」について、私なりの概念提案を行った。今後これらの「学」が育っていくためには、多様な提案がなされることが何より重要であろう。本稿が、今後の議論と両「学」の発展への何らかの貢献となれば幸いである。
|
ディシプリンのコンテクストで進められる知識生産 |
アプリケーションのコンテクストで進められる知識生産 |
|
| 問題設定 | ディシプリンの内的論理によって決まる 研究開発の実用的な目的は直接には存在せず実用化は予期せぬ副産物 |
アプリケーション(単に産業的な応用だけでなく、社会的な応用を含む)のコンテクストで決まる |
| 問題解決 | ディシプリン固有の規約、方法にしたがって進められる | 広汎なディシプリンからの参加 トランスディシプリナリな問題解決の枠組み 個別ディシプリンにはない独自の理論構造、研究方法、研究様式 |
| 研究成果の価値 | ディシプリンの知識体系の発展にいかに貢献しうるかによって判断---ピアレビュー | 問題解決への貢献、スピード |
| 研究成果の普及 | 学術雑誌、学会などの制度化されたメディアを通じて普及 | 制度化されたメディアを通じて普及するのではなく、参加者たちのあいだで学習的に知識が普及(参加型) |
| 参加者の資格 | 各ディシプリンの中で(大学の学科などで)養成された研究者 | 多様な母体からの参加(大学研究者のみならず、産業界、政府の専門家、さらには市民も) |
| 研究組織 | 永続的基盤を有する | 一時的 |
| 知識生産拠点 | 権威づけされた研究機関、エリート研究機関 | 相対化(知的活動における研究開発活動のウェイトは小さくなる) |
出典)小林信一、新しい知識生産と人材育成、ビジネスレビュー、45-4,pp19-30, 1998 (一部改変)