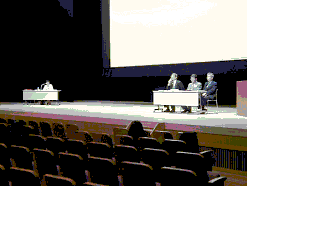
第10回チェインディスカッション
日本原子力学会 社会・環境部会
●チェインディスカッションのパンレットはこちら●
●当日実施したアンケートの集計結果はこちら●
討論テーマ:「原子力発電は地域にとって有益か」
日時:平成15年3月29日(土)13:00-15:30
場所:学会春の年会A会場(アルカスSASEBO)
座長:久留百合子さん(BISネット代表取締役)
1.プログラム
以下の講演者の方に、今回のテーマの趣旨に沿った演題にて講演をいただき、会場からの質疑と討論を実施した。参加者は約108名(うち一般参加者は25名)であった。
(1) 講演
①樋口 勝彦氏(九州電力 玄海原子力発電所長)「原子力発電と地元との共創について」
②福田 研二氏(九州大学 大学院教授)「社会的受容に向けて」
③中村 政雄氏(電力中央研究所 研究顧問)「地域にとって有益か」
(2) 質疑&全体討論
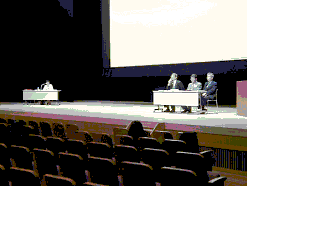
2.議事概要
宮沢部会長より、社会・環境部会の役割、チェインディスカッションの趣旨の説明と座長を務めていただく久留さんの紹介があった。久留さんは九州に生まれ、西日本銀行を退職後、BISネットを設立して現在に至る。福岡県在住で、エネルギーや環境問題を含めて幅広くご活躍している。
久留座長から、今回引き受けるに際し、「座長」や「チェインディスカッション」という言葉がとても新鮮だったとの感想が述べられ、「日本人はディスカッションが苦手であるが、今回のチェインディスカッションでは一方的に講演を聞くだけでなく、会場の人々も意見や感想を述べ、発言者と会場とがチェインでつながっていくという意味だと理解した」と締めくくった。
(1)
樋口 勝彦氏(九州電力 玄海発電所長)
「原子力発電と地元との共創について」
・ 今回のテーマ「原子力発電は地域にとって有益か」という問にはショックを受けたが、原子力で不祥事が続いている今、ここで初心に立ち戻って見つめ直すことも必要だと思って引き受けた。
・ 玄海に発電所ができて約20年。建設後、交付金や固定資産も低下していく中で、地域にとって有益になっているかをここで検証したい。地域にとって有益になるには、地域の信頼が不可欠である。玄海町の4ヶ所には原子力を歓迎する看板「心夢みるアトムの町」、「力あわせてすてきな未来」があり、この看板に地元の方からの付託を感じる。
・ これまでは発電所側から一方的に働きかけることが多かったが、現在は地域と原子力発電所のWIN-WINの関係(両者とも利益が得られる関係)が必要だと考えている。
・ 雇用、技術レベル、教育、観光、自然保護、文化、福祉、農業、漁業をキーワードとして、共に地域を創っていくことを考えている。辞書にはない言葉だが、「共創」である。平成9年の4号機の完成後に、色々な設備を作ってきた。これらの設備を中核に、地域の要求にあったあり方を模索し、共に創りあげていくための議論を積み重ねている。
・ 発電所で働く人は、通常運転時と定検時とを平均すると、約60%が地元の人間であり、地元にとっても魅力ある職場となっている。人口推移では、農業人口はどんどん減っているが、総人口は下げ止っている。農村部では難しい女性の雇用に対しても、エネルギーパークが雇用の場を提供している。佐賀県でも最も失業率の低い地域である。
・ 地元企業の技術レベルが高くなれば今まで外に委託していた作業が地元でできるようになるので、訓練センターなどの設備を使ってレベルの向上を図っている。玄海1/2号は中央制御室の取り替え、復水器をチタン管に取りかえるなど日本で始めてのトップレベルの工事もやっており、これに地元の企業が参加して、発電所外でも通用するような高い技術レベルを習得している。
・ 社員が体験談を地元の学校で話したり、温室を使ったフルートコンサート開催による情操教育、エネルギーパーク内での史跡の保護、地元物産の販売などを行っている。エネルギーパークの入場者は平均すると年間30万人で、そのうち70%は一般の方である。
・ 発電所では絶滅寸前の植物、たとえば「ゆうすげ」を保護したり、椿の原生林も保護している。昨年はWANOの関連でアジアの36の発電所長が集まる会議も開催した。郡部ではこのような国際交流の機会は非常に少なく、貴重な機会であった。
・ 原子力の場合は漁業補償が多いが、温室を貸し出すなどの農業支援も行っている。現在はガーベラを栽培しており、本日持ってきたので会場の皆さんに1束づつお配りする。農業後継者の育成にも協力している。また、取水口に詰まった貝殻や海草を使って肥料を作り、農家に配っている。カルシウムを多く含む肥料なので地元のミカン農家に喜ばれている。伝統文化の保護、ふれあいコンサートの実施、全国規模の絵葉書の展覧会等があり、文化面の活動を行っている。
・ 建設前も含めて30年近く疫学調査を続けているので、医療上の貢献も大きい。また、無菌室の設置、緊急時医療などでも協力している。
・ 今日の講演に、特にレジメは用意していないが、本日お渡しした玄海エネルギーパークの2枚の絵葉書がレジメである。我々がどういう気持ちで原子力発電所を作ったのか、即ち、地元に安心してもらい、ここに共に永遠の火をともす、という気持ちで初代所長が読んだ「祝 臨界」という漢詩である。特に「津々叡智図鵬挙(しんしんたる叡智、鵬挙を図る)」の部分である。くめども尽きぬ知恵を出し合って、国家のエネルギーを支えるという気持ちである。もう1枚は発電所の敷地内で新種の椿が発見された時に、地元の方が喜んでつくった詩である「図鑑には まだなき椿の新品種 玄海淡雪 わが町にさく」。また、地元の書家の筆によってこの絵葉書書となった。地域との共創の文化面の一例である。これを一つの例証として、「原子力発電は地域にとって有益か」という問に対する私の考えを述べさせてもらった。
(会場参加者A)
東海村に20年間住んでいる。道路も整備され、発展してきたが、原子力の事故・不祥事があり、村にあった歓迎の看板がはずされ、原子力に頼らない街作りを、と変わってきている。地域振興のみでなく、万が一事故が起きた時の対応についても、地域に伝えるべきだと思うがどのようにしているのか?
(樋口氏)
何かあった時の対応は、何かがあった時にそこへ行くのでは駄目なので、常に地元に出向いている。また、発電所にもいつでも来てもらう、そういう雰囲気を作り出すこと、双方向の働きかけによる信頼関係が必要である。議論を深めることが住民の疑念を晴らす。時間がかかるが、1人1人とやっていかねばならない。幸い7000人の町なので顔が見える関係であるが、今まさに町村合併の大号令がかかっている。そういう中でどのような方策に変えていくのか、選択を迫られている時期である。原子力発電所がなくなって止まった時にも地元で仕事が続けられるように、色々な施設を提供している。
(2)
福田 研二氏(九州大学 大学院教授)
「社会的受容に向けて」
・ 九州大学の環境センターも兼務している。個々の問題は地域に根ざしたフィードバックがベースであるが、本日はマクロ的に社会的受容をどう考えたら良いかについて話す。様々な価値が交錯する中で、社会的受容性をどう位置付けるかについて話したい。
・ キーワードは「外部性」である。これは市場経済の下で取引されない価値のこと、つまり対価を払わずに利益または損害を受けることである。もしここで損害賠償を起こすと外部性が内部化する。エネルギーセキュリティも外部性である。
・ 原子力は石油換算で1年分以上のエネルギーを備蓄していることになり、イラク戦争が長引いても電気に関しては安心できる。このように安心感を与える外部効果がある。また、資源の分散、中東に依存しないという効果もある。
・ 社会的受容性には大きく2つあり、重大事故や被曝による補填されない人的被害で、運転や建設時の人的/物的な被害、つまり僅かであるがそれぞれのプロセスで確率的な被害があり、これが補填されない場合には外部性である。これらはある程度数値的に求めることができるが、もう一方で漠然とした不安感もあり、これも社会的受容性の外部性の中に入れられる。
・ 外部性は支払われないが、値段を求めることはできる。シャドウプライスである。制約を実現するための価格のことであり、たとえば京都議定書に定められた目標値を制約とすると、そのためにかかる費用である。結果として二酸化炭素のカーボン1tあたり5000円という値が出ているが、これもシャドウプライスである。
・ エネルギーに対する様々な意見にもシャドウプライスはつけられる。極端な意見を実現しようとすると高くつく。どこに重点を置いたエネルギー観をもっているかもそれぞれ異なり、議論がかみ合わない場合が出てくるので、何らかの形でその重視度を定量化することを考えた。たとえば、「経済性と利便性のどちらを優先しますか?」、「経済性と環境」、「経済性と安全保障」など、全てにおいて比較質問をすると、その人が何に最も価値の重みをおいているかがわかる。そして、どういうベストミックスができるかを逆に求めてみる。即ち好みに合わせた電源構成を考える。
・ 今回、学生や主婦といった一般の人約400人にアンケートをした結果、最も重視されていたのは社会的受容性、その次が環境、エネルギーセキュリティについては、どちらでも良いという中立な結果となり、経済性と利便性は軽視されている。これを電源構成になおすと天然ガス、水力が主力となり、太陽エネルギーも根強い。LWRも2割の人が導入を希望している。
・ 社会的受容性を重視しているため、シャドウプライスとしては非常に高くなる。一方、これ以上、経済性・利便性を高めるためにさらにお金をかけて開発することの意義を感じていない、これが被験者達の価値評価結果である。
・ 被験者が各電源のどこを評価しているかだが、太陽光は社会的受容性を高く評価している。天然ガスはエネルギーセキュリティも環境もマイナスであるが社会的受容性は高い。LWRはエネルギーセキュリティはマイナスであるが、環境面はプラスである。社会的受容性は地域合意という点でマイナスである。FBRはエネルギーセキュリティも環境面もプラスである。
・ 社会的受容性が、エネルギーセキュリティや環境という側面を大きく凌駕してエネルギー観を歪めてしまっている。社会的受容性が電源のベストミックス選定に大きく寄与し、原子力などは定量化できない不安感により社会的受容性が低い結果となる
・ 社会的受容性の中の、非常に感覚的な部分(不安感)が大きいために、そのための費用が大きくなる。そのような不合理な部分とシステムリスクのような定量化可能な部分との乖離が大きい。乖離を小さくするためには確率論的リスク評価の研究を深めて社会的な理解を得ることが重要である。社会的受容性に対する欲求度は非常に高い。満たされないものを絶えず求めていくという経済的な構造の中に入っており、解決策はなかなかない。経済合理性を追求していく姿勢が大切。
・ 費用対効果、外部性、確率論的リスク評価などは体系化されつつあり、結果やツールについて技術者が分かりやすく説明し、一般の人の身近なものにしていくことが社会的受容性を高めることに繋がる。
・ エネルギーについては様々な問題が錯綜してトリレンマ状態ともいわれているが、エネルギー観の違いに気づかずに議論されて、誤解や不信が生まれていることが多い。不毛な対話を避け、きちんと対話をするために「ベストミックス」を取り入れる。「あなたのエネルギー観をベストミックスに換算すると、かかる費用はこのくらい。あなたはそれを払う意志がありますか?」という問はひとつ共通言語になると思う
(会場参加者B)
社会受容に対する評価額が高いのは、2つ理由があると思う。被験者は経済性・利便性・エネルギー安全保障・環境を含めて自分の社会受容性を評価しているので、社会受容を高く評価するのは当然である。もう1つは、自分で電源構成を決めたい、だから社会受容を高く評価する。この2点だと思うがコメントを頂きたい
(福田氏)
被験者は、値段を考えるわけではなく、値段は結果として出てくる。被験者は社会的受容性を非常に望んでいる。その気持ちを実現するためにはどういう電源構成でなければならない、その値段がこれだけかかる、となる。社会的受容性を希求しているので、それを実現するための電源は限られており高くつくのである。
(中村氏)
調査対象とした学生は第3者である。実際はコストというものは電源立地の人々の意思によって決まってくるのではないか?環境にやさしいと言われている水力発電も、実際に建設する時には他の電源よりもはるかに環境破壊が大きい。発電の種類によっても立地の人々の意見が違ってくるので、この辺りをどのようなウェイトで考えるかが難しい。非常に面白い研究であるが、実際に役にたたせるとなると少し違うのではないか?
(福田氏)
水力については、環境タームに生態系破壊を入れることを考えている。調査対象を地元の人、電力事業者、と変えるとまた違った答えになるだろう。今回の検討は政策決定や多数決に用いる性質のものではなく、ひとつの共通言語として「あなたはどんなエネルギー観をもっているか、その時に法外な値段がつくのかつかないか」を示す手段である。個別には対話が必要であり、このようなツールだけで解決できるものではない。
(会場参加者C)
調査対象となった今の学生達は豊かなエネルギーの中で生活してきた。彼らのエネルギーに対する思いは熱い思いなのかどうか知りたい。
(福田氏)
学生は大変熱心であり、バランスのいいエネルギー観をもってくれている。21世紀を自分たちで担うという気持ちも強い。
(3)
中村 政雄氏(電力中央研究所 研究顧問)
「地域にとって有益か」
・ 原子力発電は地域にとって有益だと思っている。六ヶ所村は今日本で一番若い人が多い地域である。平均所得も青森県内では青森市を抜いてトップである。
・ 原子力発電所或いは施設のあるところが、その地域を活性化したことは間違いないことを数字で示したい。電源立地促進対策交付金で、135万kWの発電所1基ができるとその地元の市長村と周辺とあわせて132億円の交付金がでる。それ以外にも税金がおちる。日本海沿岸でみると、原子力関連施設立地点では、軒並み人口が増えているし、男女の比率が1:1に近い。財政力指数は0.5以下が殆どであるが、立地地域は1.1を越えている。刈羽村は平成元年あたりから急激にあがり、昨年1年間はこの指数が2.1であり日本1であった。
・ 敦賀の市内の商店街がさびれている、といわれるが、これは自動車の普及によって郊外型の商店街が流行るようになったために、全国共通の現象として、市内の昔の商店街は流行らなくなりつつある、ということで原子力とは関係のない傾向である。敦賀市は東洋紡の敦賀工場があり、1950年に3800人の従業員がいたが今はその1/4に減っている。しかし関電、原電、JNCのおかげで従業員2500人、関連企業を含めると5000人くらいの雇用が生まれており、プラスマイナスゼロであった。福井県北部はあまり恩恵を受けていないという人がいる。これは間違いであり、原子力による収入増は県全体で税金として使っているから平等である、と県の資料には書いてある。立地県が県内で平等であるとは言いがたい所もある。静岡県にある立地町の浜岡町は明らかに周辺部よりも道路が整備され交通標識も立派に思える。立地市町村と、全く冷ややかに眺めている他の市町村とで同じではないとしても当然であろう。
・ 立地町では交付金で山ほどの施設ができた。大学をつくったところもある。しかし良いことばかりではなかった。刈羽村では1年間の財政が50億円であるが生涯学習センターラピカという84億円の施設ができた。新聞沙汰にもなったが、茶室をつくって1枚10万円の畳をいれていた。地元では建設会社の見積もりを評価できる人間が一人もいなかった。電源立地センターも何もしていなかった為、このような問題がおきた。
・ お金があって恵まれた環境になったということは、努力が活かしやすい環境でありながらかえって人間を怠けものにした。考える力、判断する力が失われたのではないのか?自分で生きていこうとする力が弱まったのではないか?自活能力のない人間が増えたのでは困る。刈羽村には財政調整資金と称する貯金が150億円あり、新潟県全体の54億円の3倍である。プルサーマル反対運動のリーダは、「我々は金は十分にあるので、これからは東京電力にお世話にならずに生きていく道を探りたい」といっている。では、どうやって生きていくのか、と聞くとその知恵はまだない。その知恵を東京電力に借りたいといっており、東京電力依存型であることに変わりはない。
・ 柏崎は1997年に7基の原子力発電所が完成し、この後から交付金の額がピークになり、2000年に地方税の交付団体、つまり赤字財政に転落した。柏崎の財政は年間370億円、そのうち37%が原子力発電所からのあがりである。かつては超優良財政だった市であるが、原子力発電所の償却固定資産税と建屋の固定資産税を合わせたものが2000年の86億円から2009年の37億円にまでずっと落ちていく。対策として、使用済みの核燃料税を設けることになった。鹿児島県の川内市も取ることになった。
・ 税金が取れなくなると発電所を増やすしかなくなる。福島県の富岡町は既に2基あるが、さらに2基つくるという。福島県知事は、「2基の発電所から交付金が十分にあってもダメだという財政のやりくりしかできないような場所に増設しても、いずれダメになる。まず、なぜ2基でダメだったのかをよく調べる事が先だ」といっている。
・ 発電所は30-50年使うと古くなり、その地域で原子力発電を継続しようと思えば、新しいものを造ることになる。大きなサイクルでみて、10年毎に1基、2基を造り直していくことをやらざるを得ないと感じている。そういうことを地域で大らかに率直に明るく議論ができるような雰囲気になっているかどうか、が一つの鍵である。
・ 原子力発電所ができることで地域に対立を生み出し、対立を激化させた例もある。その結果として首町が短命で終ったところもある。未だに対立が残っている場所もある。豊かになると人間は欲望を膨らませるので、対立の激化は避けられない。良いことがあればどうしても多少の陰ができてくることはやむをえない。原子力発電所の設置が地域にとってマイナスであったか?私はプラスであったと思っている。人形峠に動燃事業団の事業所ができて新しい就職口が出来た。当時の高卒は村役場に1人か2人採用してもらうしか職場がなかった。動燃に毎年10人くらい採用されるようになり、村長さんが胸をはっていた。私は原子力は地域の振興にとって大変プラスであったと感じている。
(4) 質疑&全体討論
(会場参加者D)
樋口所長への質問。会社としてイベント、施設等で地元に協力している例はわかったが、社員が一住民として地域活動をしているのか?一社員であると同時に一住民としての誠意がでているかどうかが大切であると思う。
(樋口氏)
生活視点でどれくらい地元の中で共にしているかという点が大切だと思っている。500人の社員のうち、特に管理職は2?3年の転勤族が殆どである。30年たち、若い人達の異動が少ないので、地元での結婚や地元で家を建てる人も多くなった。定収があるため、最近は社員が周辺市長村に30代で家を建てる例もでてきた。地元の会社の人には、九電の社員ではないが、1人1人に自分の会社が九電の玄海発電所だと思ってもらうようにしている。協力会社とは訓練・教育を同じ視点で一緒に実施している。皆さんにそのように認知してもらい、定着しつつあることを誇りにしている。会社で起こったことが直ぐに町に流れるし、町の噂がすぐに発電所にも届くようになった。
(会場参加者D)
幹部の方がそういう気持ちであることが大切であり、継続して頂きたい。東電の方にもこの言葉を聞いてもらいたい。
(樋口氏)
先ほど50人位いる特別管理職は転勤族が殆ど申し上げたが訂正する。私を含めて家を町に構えて既に22年玄海町に住んでいる者が何人かいる。後続もボチボチでてきている。
(会場参加者E)
敦賀市に住んで美浜町に通っている。関西電力では美浜の事故の後に地元に研究所をつくった。若狭湾研究センターもあり地元で広い意味の研究をするように進んできた。福井大学、茨城大学などで原子力関係の新しい専攻を作ろうという動きがある。研究や教育を地元で立ち上げていくことが良いのではないか?
(中村)
良いことだと思う。柏崎にも大学ができた。地元の大学が原子力の研究センターになり、人材を作り出していくことが一番重要なことだと思っている。ロケットでいえば種子島や内之浦に施設があるので東京大学の宇宙研は鹿児島大学に移るべきだ、と前から言っているが、なかなか合理的な大学の頭脳配分や施設の配置換えがやりにくい封建的な状態である。福井大学、茨城大学の新しい試みは非常に重要なことである。それが地元の方々の意志によってなったのであればなお素晴らしい。六ヶ所村は前の土田村長の時に中高校生や職員を外国に出して国際感覚をつけさせる、という次の世代の為の人材養成をしていた。その人材を地元でどう活かすかである。大学を作ってもその人材をどう活かすかであり、ただ大学を作れば良いということではない。
(久留座長)
市町村合併による地元への影響はどうか?
(中村氏)
町村合併は行政の合理化である。職員数を減らし、質の良い職員がより腕を広く振るえる環境になることがねらい。原子力発電所がある市町村はだいたいが田舎でまずしいところが多かった。せっかく交付金をもらって今まで良い思いをしたので、それを回りの人に分けたくない、自分の取り分を減らすことはしたくない、と黒字地域は一緒になることを嫌がっている。人間が大勢集まると揉め事が増えるが、知恵の総和も増えるので方向としてはそちらに行かざるをえない。ただし他と比べると時間がかかりそうだと思っている。
(久留座長)
将来を考えると原子力発電の寿命も無限ではないので、もう少し大きな目で市町村のあり方の中の原子力として考えても良いのでは?
(中村氏)
外野からみていると、お金があるうちに、そのお金を使って末永く暮らしていけるようにお金の使い方を考えたらどうかと思うがそうはいかない。文化センターなど、施設は県が造り、運用するのは地元である。年間に維持費が数億円かかり、その維持費はむしろ増えていくので、新しいことを考える方にお金を使うことはできない。目減りし、むしろ出て行く方が増えていくという構造の中で、なかなか難しい。予め維持費も考えて造ってくれれば良かった、と今ごろ反省している。これからは施設を造る財源がないのでもう1度発電所の数を増やして、新規まき直しでそれは上手くやろう、と思う。電力の需要は増えないし反対もあってなかなか発電所は造りにくいが、現実的には発電所を増やしていく以外の解決策は難しいようである。
(会場参加者F)
3先生のお話は、地元との関係においては日ごろの地道な努力が大事なこと、またプラスの面とマイナスの厳しい面の両方があるとのことだったが、リスクの共有に関してお伺いしたい。最近日本でも原子力の防災訓練が実施されるようになった。アメリカではTMI以降、もう20数年実施されていたものだが、今までの日本では、訓練をやると事故が起きるように受け取られる、訓練をすること自体が問題であるといわれて、なかなか実施できなく、やっと最近、方々のサイトで実施されるようになった。樋口所長にお伺いしたい。九州電力でもかなり先駆けて訓練を実施されており、当初は地元からも色々と意見があったかと思うが、訓練を重ねる中で地元との対話・関係に変化が出た点があれば教えて頂きたい。
(樋口氏)
初期には、事故の想定をした訓練は恐怖感を生じさせるといっていた。県の防災訓練で仮想事故の想定をするが、それに対して当初は町も「九州電力はちゃんとやっているので、そういう事故想定はいらない」といって曖昧な中で訓練を行っていた。JCO等の色々な事故があり、それではいけないという共通認識にたって事故を想定して、無理やりに放射性物質を漏らした。なぜこの想定をするのかという根底的なものを、役場の当局の方々と話し、ここまでいくにはこういうありえない仮定をおく必要がある、「ありえない」というところまで詰めたのち、リスクに対応するべき備えが必要だとの共通認識のもとで訓練を実施している。中でも具体的にもし発電所内で被曝がおこった場合にどこにどういう形で運ぶのか、除染も含めて訓練をしている。その為には広域運用という視点が必要で、玄海町だけでなく日本赤十字病院や放医研といった地点まで含めた訓練が必要である。訓練は年に1回であるが、それに先立つ色々な疫学的・放射線管理的な認識を深めていく必要があり、国の指導も受け、定期的に町や病院の関係者に集まって頂き、実際に除線や放射線防護の緊急処置の会合を開いて意見交換をしながら進めている。その中で「実際こういう事故が起こるのはどういう場合か?」との質問も受ける。そういう想定は本来の運用条件では起こりえないが、発電所のもつリスクを考えた場合に基本的なものとして共有しておく必要があるとの認識で仮定をしている、という説明をして、理解の下で進めている。市民レベルで認識があるかということとは別であるが、少なくとも立地市町村、周辺の担当者がきちんと認識したうえで、訓練を行うようになったというのが現状である。
(久留座長)
原子力では「安全性について」、「原子力は必要か否か」、というような議論はこれまでもある。今回、立地点でないところに住んで原子力発電所の電気を使う立場にある者としては、発電所がある地域のことを考えてみる、そして日本の中で、日本国として原子力発電をどうとらえるべきか、そんな問題を考えさせられる機会となった。
以上
(文責:社会・環境部会 チェインディスカッション幹事)