3.講演会
「原子力にかける夢」 東京電力 榎本常務
原子力開発の揺籃期に人類は原子力にどのような夢を抱いていただろうか。
アイゼンハウアー大統領により、国連で原子力の平和利用を提唱した"Atoms for Peace"演説がなされたのと同じ年の1953年に出されたPUTNAM報告は、「もはや電気代はただ同然になる」と、原子力の生み出す明るい未来について謳い上げている。米国では丁度、家庭電化時代の幕開けでもあり、原子力は明るい未来を開くゴールデンボーイであった。
夢は、原子力発電や原子力船だけに止まらず、原子力飛行機、原子力ロケット、原子力機関車など、多くの分野に及んでいる。夢に終わったものも多いが、例えば、原子力飛行機用エンジンの開発は全く無駄に終わったわけではなく、遮へい技術と高温材料開発という点で技術進歩をもたらしたと言われている。
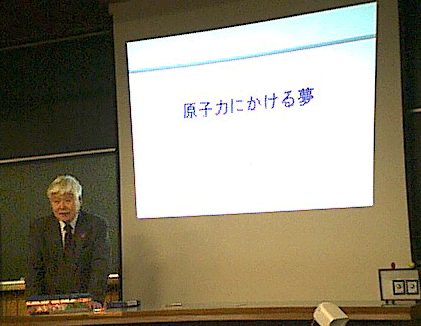
原子力の平和利用を提唱した"Atoms for Peace"演説がなされたのと同じ年の1953年に出されたPUTNAM報告は、「もはや電気代はただ同然になる」と、原子力の生み出す明るい未来について謳い上げている。米国では丁度、家庭電化時代の幕開けでもあり、原子力は明るい未来を開くゴールデンボーイであった。
夢は、原子力発電や原子力船だけに止まらず、原子力飛行機、原子力ロケット、原子力機関車など、多くの分野に及んでいる。夢に終わったものも多いが、例えば、原子力飛行機用エンジンの開発は全く無駄に終わったわけではなく、遮へい技術と高温材料開発という点で技術進歩をもたらしたと言われている。
日本でも昭和33年(1958年)、「すばらしい原子力」という本が、小中学生向けに発刊され、原子力利用による様々な可能性が描かれている。原子力利用で実現しようと考えられた夢は、どこまで現実となっているだろうか。
第一に、原子力によるエネルギ−利用の原点であった高速増殖炉は、未だ商業規模では実現していない。米国の核不拡散政策による研究開発の低迷や高速増殖炉組み込んだサイクル全体の技術が未だ発展途上にあること等が大きな要因と考えられる。
第二に、原子力発電の利用によって電気代はただ同然にはなっていない。原子力発電は、化石燃料に比べて長期的な価格安定性、環境適合性を持ち、化石燃料プラントに対して競争力を維持してきたが、化石燃料による発電技術に比して、技術革新に乏しく、このままでは競争力の維持が懸念される。
第三に、原子力の否定的な側面が、時には大変な誤解を伴って、社会の原子力に対する見方を形成し、原子力はゴールデンボーイとは言えなくなった。
第一と第二の点は、要すれば、安全性と経済性に関わる問題といえよう。
この状況を打開すべく、たゆまぬ努力が積み重ねられている。従来とは抜本的に異なる新型炉で、持続可能性、安全性、信頼性、経済性のいずれをも実現することを目標にした第四世代の原子炉開発の活動が行われるなど、先人達の描いた夢を引き継ぎ、その実現を目指す活動は現在数多く実施されている。事実、様々な努力の結果、米国では原子力発電プラント数のうち、3/4までが市場での平均発電原価よりも安い価格で発電をしている。今日、原子力産業界は、既設炉の寿命延長だけでなく新規電源としての原子力発電所新設に向けて意気盛んである。
受動的安全性の確保等、安全性に関する様々な工夫も進められている。
三番目の点は、一番解決が難しい問題と思われる。原子力は相対的に一般工業よりも遙かに高い安全性を持っていることは実績の上でも、リスク分析の結果においても、動かしがたい事実として示されているにも拘わらず、放射線という人間の五感で感知できないものに対する本能的な恐怖心に根ざした問題がある。
これらを踏まえて、私の夢を述べることにしたい。
第一の夢は、原子力利用の裾野拡大である。原子力発電は、国内で約35%のシェアを占めているが、一次エネルギー供給に占める割合は約13%に過ぎない。
これでは、原子力のエネルギ−セキュリティに対する貢献度は限定的で、満足できるものではない。原子力を用いて水素のような化学エネルギ−の生産も可能であるが、軽水炉では温度が低く効率的に達成できない。この温度の限界を突破することにより、例えば発電、化学エネルギ−生産、熱利用のカスケ−ド組み合わせも実現できると考える。
第二の夢は、資源制約からの解放への貢献である。資源制約から開放される手段として、高速増殖炉などによるウラン利用効率の向上、海水中ウランの利用、核融合等がある。
第三の夢は、社会が原子力の便益を享受できるようになるための必要条件であるので、他の夢と性質はやや異なるが、放射線の影響の科学的解明とこれに基づく認識の改善である。疫学研究のみならず、分子レベルで放射線の影響を解明を通じて、放射線に対する正しい認識が一般化すれば、社会の原子力に対する受容性も一段と高まることであろう。
以上