|
鈴木一弘(日本原燃) 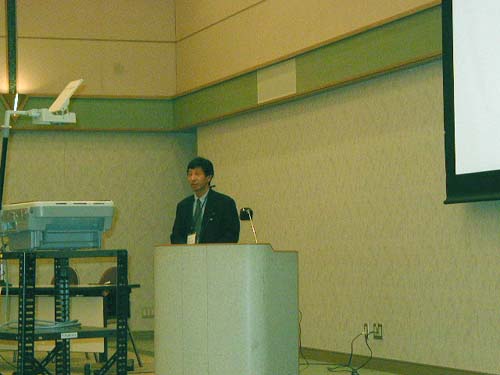 ・設備規模800トン。あまった分は中間貯蔵。国内外の最良技術を採用。主要工程はフランス技術。 ・使用済燃料受入・貯蔵施設は1999年12月に使用前検査合格。 ・平成14年8月までに、BWR359トン、PWR288トン受け入れ。 ・酸回収・蒸発管はTHORP技術。脱硝はJNC。 ・国内導入技術は、JNCと技術提携。スケールアップ試験等について技術協力。 ・海外導入技術は、JNFLが技術導入、国内メーカが分担して設計・製作・建設。COGEMA、BNFLの支援を受けて試験運転を実施。COGEMAから約60名の技術者が駐在。家族含め約200名が六ヶ所に。 ・昨年4月より通水作動試験を実施中。本年10月より、一部施設で化学試験開始。 ・7月末で工事進捗率89%。予定を2〜3ヶ月上回っている。 ・細かな不具合もWebで公開、またマスコミ説明も行い、信頼感醸成。 ・試験運転の概要を9月2日に保安院へ提出。 ・試験実施体制→全世界的体制。COGEMA、BNFL、JNC、メーカ、JNFL。 ・教育・訓練→メーカ施設でのモックアップ訓練、化学工場、原子力発電所での訓練、中核要員90名をラ・アーグに派遣。3ヶ月ずつ、7回。 ・化学試験で、化学薬品の密度を考慮した計測・搬送・運転特性等の確認。機器単体からはじめ、系統試験。その後、外乱を与えた試験。 ・ウラン試験→平成15年6月頃開始。溶解・抽出・脱硝等の物理化学的機能・性能の確認。 ・アクティブ試験→平成16年7月開始。使用済燃料300トンくらい処理。 (JNCアサクラ)Puを扱う施設で一番やっかいなのは、日米協定上の格上げ。アクティブ試験までには運転中の施設に格上げが必要と思うが、スケジュールは? (鈴木)政府間の協定の話。国とは、アクティブ試験前ということで進めている。 (倉崎)日米協定は文科省。この前にIAEAの保障措置があるが、両方ともアクティブ試験前ということで検討が進められていると聞いている。 (神田)子供たちや近所の人たちの見学会を入れると効果があると思うが。 (鈴木)建屋内部にはまだ残材があってきたないが、化学試験前にはきれいにするので、ぜひとも実施したい。その他にも全戸訪問も実施している。 (梶川)保障措置はたいへんだと思う。非核国が大規模再処理工場を持つのははじめて。計量管理等難しいと思うが、アクティブ試験はふつうの発電所とかなり違うのか。 (鈴木)IAEAの立ち会いで検量線を引くところからはじめる。 (山名)当初より、準リアルタイムの計量管理との考え方だったが、それは変わってないか。 (鈴木)間違ってるかもしれないが、変わっていないと思う。 (?)アクティブ試験はしだいに燃焼度を上げるのか。 (鈴木)やさしいものから順に。使用前検査は設計仕様の燃料で受ける。 (山名)COGEMA、JNCからの技術支援や、フランスでの実践訓練で技術を取り込む努力をしているようだが、その効果は。 (鈴木)JNCから30名の技術者が技術支援部に駐在。今メインの仕事は試験運転に向けた手順書の作成。フランスの手順書等は日本と細かさがちがうので、それを合わせるように。ラ・アーグ訓練では、制御の違いを身をもって体験しており、帰ってきて、要領書・手順書を作成している。不安だったところが払拭されたという意見を得ている。 (神田)六ヶ所の安全審査の主工程を担当した。内容を海外で講演した時に、英国では「なぜ英国技術をもっと使わない」、フランスは「なぜ全部フランス技術にしない」と言われた。このへんのことはまだ尾を引いているか。 (鈴木)人も変わっているので、ないと思う。 (?)安全運転、安全管理に世間の信頼がなくってきているが、再処理工場では社会に対してどのように説明していくのか。 (鈴木)保安院とも議論しているが、人に見られているといつも思うことが大原則。それを規則等具体的な形に落とし込むことが必要。社内でも検討チームを作って検討しているが、王道はないと思う。 |