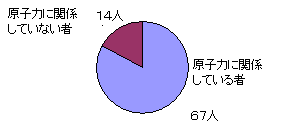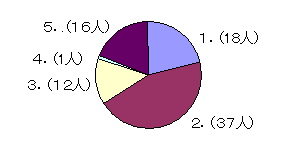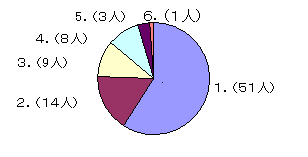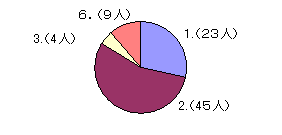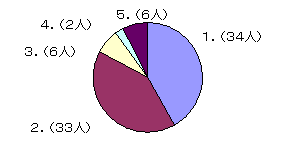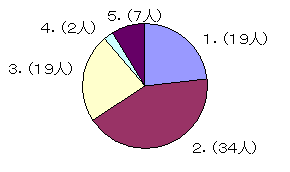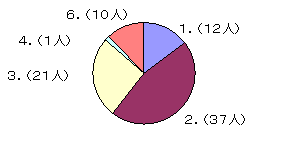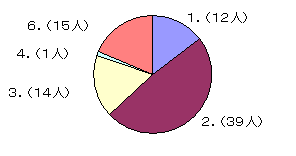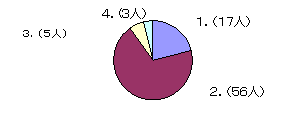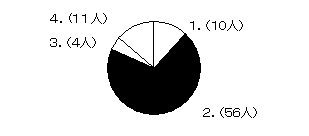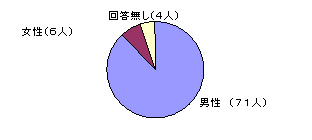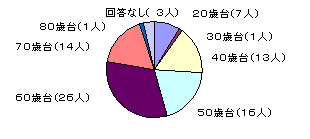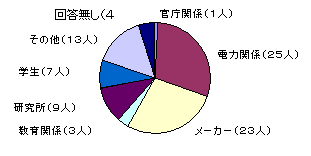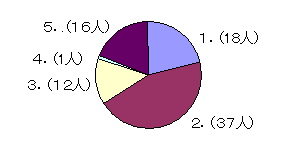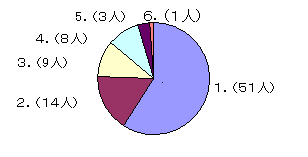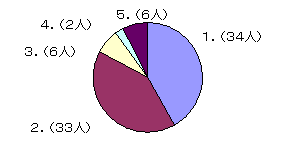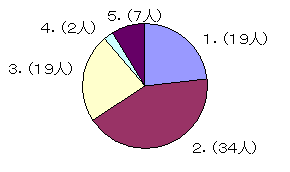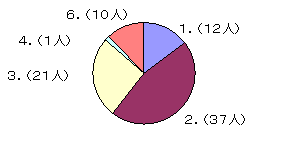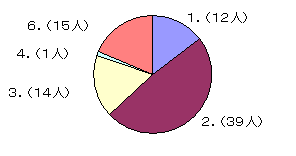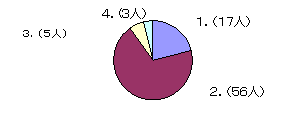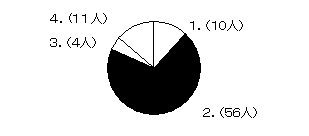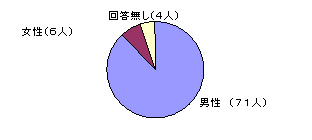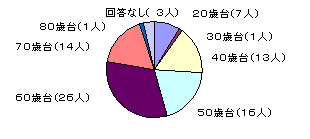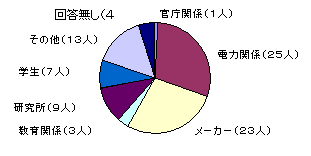| 日本原子力学会・シニアネットワーク第7回シンポジウム(20.3.4)アンケート集計 |
|
|
|
平成 20.3.11 |
|
|
シンポジューム事務局 |
|
|
|
出席者 179人、 内アンケート回答者 81 人 |
|
|
|
アンケート回収率(45.3%) |
|
|
(内訳) |
|
|
原子力に関係している(していた)者 67 人 |
|
|
原子力に関係していない者
14人 |
|
|
|
|
|
| 問1.シンポジュームをどのようにして知ったか。 |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.原子力学会からの案内 |
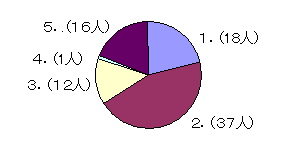
|
|
|
|
|
2.SNW,発言する会、EEE会議からの案内 |
|
|
|
|
3.会社、団体等の中での情報 |
|
|
|
|
|
4.新聞情報 |
|
|
|
|
5.知人等の紹介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(複数回答 3件) |
|
|
SNW,発言する会、EEE会議からの案内が44%,原子力学会からの案内が21%、合わせて |
|
|
65%を占めている。 |
|
|
知人等の紹介が19%あり、第5回の7%にくらべ増加している。 |
|
|
| 問2.どのような理由で参加したか。 |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.テーマ設定に関心を持った |
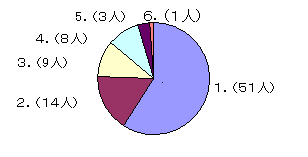
|
|
|
|
|
2.講師等に興味を持った |
|
|
|
|
|
3.研究や仕事で必要 |
|
|
|
|
|
4.自己啓発 |
|
|
|
|
|
5.その他 |
|
|
|
|
|
6.回答なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(複数回答 5件) |
|
|
「テーマ設定に関心を持った」からと答えた人が6割程度を占めている。 |
|
|
その他は「どのような企画か内容を知りたいと考えた」 等。 |
|
|
| 問3.シンポジュームに満足したか。 |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.大変満足 |
|
|
|
|
|
2.満足 |
|
|
|
|
|
3.どちらとも言えない |
|
|
|
|
|
4.不満 |
|
|
|
|
|
5.大いに不満 |
|
|
|
|
|
6.回答なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「大変満足」が28%、「満足」が56%、合わせて8割強の人が満足したと答えている。(第5回 |
|
|
と同様の傾向) |
|
|
「不満」「大いに不満」は無し。 |
|
|
|
「大変満足」、「満足」と言う人の主な理由、感想等 |
|
|
原子力広報、コミュニケーションが極めて大事。こうしたテーマで企画されたことを評価する。 |
|
|
論点がクリアに整理され、話しぶりにも経験の豊富さがうかがえた。 |
|
|
広報の取り組みについて登壇者の皆様の経験談を踏まえた提言は参考になった。 |
|
|
原子力関係者が自ら変わらなければならないとの思いが理解できた。 |
|
|
原子力関係者の「分からせる」姿勢から「分かってもらう」「共感・納得」へ姿勢が転換され始め |
|
|
たことを知った。 |
|
|
ダイアローグの必要性、広聴の意味が分かった。 |
|
|
バランスのとれた良いシンポジウムであった。 等 |
|
|
|
「どちらとも言えない」人の理由 |
|
|
自分の発表に一生懸命で聞き手への配慮が足りない講演者もいたから。 |
|
|
| 問4.講演「原子力の広報活動を振り返ってーその課題および社会との新たな信頼関係づくりへの |
|
|
提言」について |
|
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.大変よかった |
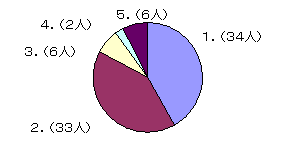
|
|
|
|
|
2.よかった |
|
|
|
|
3.普通 |
|
|
|
|
4.不満足だった |
|
|
|
|
5.回答なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 「大変よかった」が42%、「よかった」が41%、合わせて8割強の人がよかったと答えている。 |
|
|
|
「大変よかった」「よかった」と言う人の主な理由、感想等 |
|
|
TMI事故後の報道対応、チェルノブイリ後の変化等、体験、経験に基づく話は貴重であった。 |
|
|
長年の経験に基づいた広報のあり方をざっくばらんに話されたこと。 |
|
|
メッセージを「単語」で表すことの重要性を述べられた共感する主張であった。 |
|
|
”原点は「信頼」である”との話、すべてに通じる。 |
|
|
報道関係者との付き合い方等,受け手側を意識した発信についてすごく分かり易い意見であ |
|
|
った。 等 |
|
|
「不満足だった」と言う人の主な理由 |
|
|
問題点がよく分かっていながら何故改善できないかについての追求が無かった。 |
|
|
| 問5.講演「報道における原子力の扱い方ー”社会からの木鐸”と”社会への木鐸”という二つの使 |
|
|
命をどう果たしていくか」について |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.大変よかった |
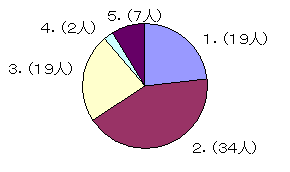
|
|
|
|
|
2.よかった |
|
|
|
|
3.普通 |
|
|
|
|
4.不満足だった |
|
|
|
|
5.回答無し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 「大変よかった」が23%、「よかった」が42%、合わせて7割弱の人がよかったと答えている。 |
|
|
|
「大変よかった」「よかった」と言う人の主な理由、感想等 |
|
|
新聞メディアは「社会からの木鐸」でも「社会への木鐸」と言う使命でも動いているのではない |
|
|
ということを明確に述べられたこと。今後の対応について考えさせられた。 |
|
|
記者の心根、心情が興味深かった。木鐸精神は1%と言うのも印象的。 |
|
|
マスコミ側の人間的な部分を本音で語ってくれて大変興味深かった。 |
|
|
メディアの本質を示され、メディア報道の特質を理解した上で双方向の情報発信の重要性を |
|
|
指摘された。 等 |
|
|
|
「普通」「不満足」の人の理由 |
|
|
木鐸の話の問題から逃げているのが残念だった、 |
|
|
フリーな立場なのにまだ身内(マスコミ)をかばっている。マスコミが成長しないと社会も変わら |
|
|
ない。 |
|
|
原発事故などを巡って原子力広報サイドの情報発信、メディア報道のあり方について、もっと |
|
|
突っ込んだ話が欲しかった。 等 |
|
|
| 問6.「広報・報道を巡る対談、質疑応答、討論」について十分な議論ができたと思うか。 |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.大変満足 |
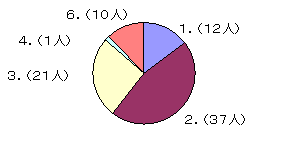
|
|
|
|
|
2.満足 |
|
|
|
|
3.どちらとも言えない |
|
|
|
|
4.不満 |
|
|
|
|
5.大いに不満 |
|
|
|
|
6.回答なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 「大変満足」が15%、「満足」が46%、合わせて6割程度の人がよかったと答えている。 |
|
|
|
「大変満足」「満足」という人の主な理由、感想等 |
|
|
各パネリストの多様な考え方が面白い。相手の視点を理解することがポイントである。 |
|
|
お互い旧知の間柄であるため、大変ハーモニックな質疑応答であった。 |
|
|
広報の難しさについてさらに一層その感を深めることができた。 |
|
|
ダイアローグにより、共感できるところを探すべしと言う点はもっともである。 |
|
|
|
「どちらとも言えない」「不満」と言う人の主な理由 |
|
|
問題点の解決の糸口が見えない討論ではなかったか。 |
|
|
この討論は難しい。結果が出にくい。 |
|
|
マスコミへまだまだ気を使っている。 |
|
|
| 問7.パネル討論について |
|
| (1)「原子力コミュニケーションのあり方を問う」について十分な議論が出来たと思うか。 |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.大変満足した |
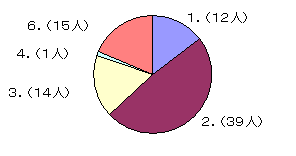
|
|
|
|
|
2.満足した |
|
|
|
|
3.どちらとも言えない |
|
|
|
|
4.不満 |
|
|
|
|
5.大いに不満 |
|
|
|
|
6.回答無し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 「大変よかった」が15%、「よかった」が48%、合わせて6割強の人がよかったと答えている。 |
|
|
|
「大変満足」「満足」と言う人の主な理由、感想等 |
|
|
多くのパネリストがそれぞれの立場で問題点を提示され考える材料を与えてくれた。 |
|
|
ダイアローグがコミュニケーションの基本であると言う”ダイアローグ”重要視の論点が多かっ |
|
|
たこと。 |
|
|
全体として現場の技術者の生の声が感じられなかった。本当に効いて欲しい方々(例えば規 |
|
|
制当局、研究、教育関係者)が会場にあまりいなかったのでは。誰を対象にパネリストの皆さ |
|
|
ん話されたのかナ・・・と感じた。 |
|
|
皆さん本音でかつ具体例も示しながら適切な発言であった。 |
|
|
5名のパネラーはそれぞれの経験や知識に基づく意見を述べられ非常に参考になった。 |
|
|
|
「どちらとも言えない」「不満」と言う人の理由 |
|
|
国民レベルでのコミュニケションと言う発言はあったが、国民がどの程度原子力に対する理解 |
|
|
度を持っているか把握するのが先だと思う。 |
|
|
パネリストが多すぎて議論が深まらない。 |
|
|
テーマは良いが時間が短い気がした。 |
|
|
| (2)最も印象に残った問題提起や議論はどの講師(パネリスト)のどういったものだったか。 |
|
|
|
竹 内 哲 夫 |
佐 々 木 宜 彦 |
|
|
・国益、国家観をもって原子力に対処せよ。 |
・事業者が正々堂々と意見を述べる段階に来 |
|
|
・原子力立国計画をPRせよ。 |
ている。 |
|
|
・米国とフランスの例。 等 |
・内向きの安全議論だけではなく、エネルギー |
|
|
|
セキュリティーを踏まえた議論が必要。 |
|
|
犬 伏 由 利 子 |
・説明責任の取り方、あり方。 等 |
|
|
・原子力は一度事故が起きたら対処ができな |
|
|
|
いから安心できない。 |
北 村 正 晴 |
|
|
・フィードフォアーをしっかりやれば、一般社会 |
・ダイアローグの大切さ。 |
|
|
は理解し受け入れる。 |
・市民との対話では自分は知っていると言う態 |
|
|
・報道は一般市民の本当に必要としている情 |
度では駄目。 |
|
|
報を伝えて欲しい。 等 |
・相手の立場に立って共感を得ようとすること |
|
|
|
が重要。 等 |
|
|
品 田 宏 夫 |
|
|
|
・技術者はもっと語れ。 |
桝 本 晃 章 |
|
|
・安全と安心の軸のズレ。市民の求めている安 |
・相手を知り己を知ることが必要。 |
|
|
心とは。 |
・ダイアローグの提示。 |
|
|
・責任者は情勢を的確に把握した上で決断を |
・異なった報道に対してはインターネット等を使 |
|
|
下す。 等 |
った反論を。 |
|
|
|
・一般の人は日常のエキスパートである。 等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最も印象に残った問題提起や議論では、北村正晴氏や桝本晃章氏のあげたダイアローグによ |
|
|
る相互理解という考え方、および品田宏夫氏の技術者は社会に向かってもっと発言すべきと |
|
|
言う主張と責任ある判断とは何かと言う意見をあげた人が多かった。 |
|
|
| (3)パネル討論の中で一番関心を持ったことはどんなことだったか。(27件) |
|
|
・品田宏夫氏の「責任ある判断」が出来るかどうかが重要と言う指摘。(8件) |
|
|
・品田氏の責任論に関連し、秋元勇巳氏がJCO事故を引き合いに出し当時の東海村長の行動 |
|
|
が妥当だったにもかかわらず、その後の10km退避について本当の意味の反省が出来てい |
|
|
ないこと。 |
|
|
・「責任」というものの考え方。戦後日本のあいまいさ、軽さが浮き彫りにされた。 |
|
|
・「コンプライアンスに逃げ込むな」に強く共感。 |
|
|
・技術系の人の前面に出た対話。 |
|
|
・ダイアローグと言う考え方。 |
|
|
・国と事業者間のダイアローグが必要な時。相互の役割の期待が食い違っている可能性があ |
|
|
る。 |
|
|
・安全は危険を知っている裏腹であるとの桝本氏の説明。 |
|
|
・安心、安全。説明責任。 |
|
|
・地域住民、消費者の考え方、利害に対する価値観が大きく変わってきたこと。 |
|
|
・真実と事実は異なる。 |
|
|
・今後の原子力事業の発展に対する規制等に関するシステム論議。 |
|
|
・役所の説明責任への対応不足。規制の独立性。 |
|
|
・IAEAの役割の問に対し、佐々木氏のIAEAへの期待や役割などの発言は残念だった。国民 |
|
|
に対してきちんと説明すべきは規制当局の責任ではないか。 |
|
|
・責任論一寸議論がかみ合わなかった。 |
|
|
・赤福や白い恋人と違ってなぜ原子力は沈んだままなのか。 |
|
|
等 |
|
|
| 問8.原子力関係のコミュニケーション活動、広報活動のあり方などについての意見、提言等。 |
|
|
|
|
マスコミを巡る問題 |
|
|
・テレビの影響が極めて大きく、テレビ関係とのコミュニケーション活動、広報活動をもっと考え |
|
|
る必要がある。 |
|
|
・NHKらマスコミとの徹底討論すべき。 |
|
|
・マスコミの改革が大切なのではないかと感じた。 |
|
|
・防災訓練等にメディアの参加(プレイヤーとして)を促す必要あり。災害報道のあり方につい |
|
|
てメディアと討論する必要がある。 |
|
|
・マスコミとのコミュニケーションのとり方。マスコミ教育。マスコミの原子力担当者をコロコロ変 |
|
|
更しない。 |
|
|
・教育の問題もあるが、現在は良識ある発言はマスコミにより知らされていない。 |
|
|
|
国の役割を巡る問題等 |
|
|
・やはり国がもう少し中心になって民間の総意をまとめ、考え方をまとめ、責任の取り方、教育 |
|
|
を含め方針を定め推進すべきである。 |
|
|
・中越沖地震による発電所の影響等について、地元でのNISA説明会が行われているが、規 |
|
|
制と原子力慎重派の対立の場になっている。質問者の中にはエネルギー問題や地球環境 |
|
|
問題に関心を持っている人もいる。是非、その場に国側の推進する立場からの説明が求め |
|
|
られるので出席して欲しい。 |
|
|
・民間の努力もさりながら、国、地方自治体役人の教育が必要と感じている。 |
|
|
・広報活動は立地地域にのみ行われているように感じる。もっと国レベルでアンケート等を実 |
|
|
施することも必要ではないか。 |
|
|
・「柏崎刈羽原子力の透明性を確保する地域の会」はフランスのCLIを参考につくられたもの。 |
|
|
|
事業者を巡る問題等 |
|
|
・コミュニケーションのプロが集まる部署を各団体が設けるべきでは。 |
|
|
・これまでの待ちのコミュニケーション活動、広報活動を改め、理解してもらえるための攻めの |
|
|
活動が必要になると思う。 |
|
|
・原子力発電所は休日、夜間の非常体制を確立すること。定期的合同訓練の実施。(消防、マ |
|
|
スコミ等) |
|
|
|
その他、一般市民を巡る問題等 |
|
|
・家族、知人等の参加を求めて一緒にエネルギー、原子力のことを考えるよう心がけたい。 |
|
|
・聴講者に若い世代、婦人を多く参加できるようにする。本日のようなシンポジウムをビデオで |
|
|
見られるようにする検討を。 |
|
|
・文系の人の参加が必要。 |
|
|
・大切なissueである。一般の人に広げる努力を。 |
|
|
・安心と信頼が表裏一体であるとの認識が重要。 |
|
|
・企業の中堅社員の意識が希薄になりつつあり、それらを対象とするコミュニケーション活動が |
|
|
必要 |
|
|
・熟議は正論。しかし共同体意識が衰弱している中で健全な熟議がどこまで現実性があるか |
|
|
心配。 |
|
|
・この問題を原子力特有のものとして解決しようとしているが、原子力と関係の無い分野での |
|
|
解決策を参考にすることも考えたら。 |
|
|
・原子力の世界は特殊な事情があると思っていたが、日本の社会全体について全くおなじで |
|
|
あることが分かってきた。(エネルギー、食料、戦力など) |
|
|
・それぞれの立場に固執したいわば保身のような活動が行われている。それぞれの利害をこ |
|
|
えた前向きな議論を引き出せるような本音の広報活動が必要。 |
|
|
等 |
|
|
| 問9.シンポジュームについて |
|
| (1)講演の時間は |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.長い |
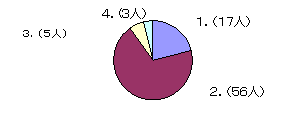
|
|
|
|
|
2.丁度良い |
|
|
|
|
3.短い |
|
|
|
|
4、回答無し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「長い」と答えた人が21%、「丁度良い」と答えた人が69%であった。 |
|
|
| (2)パネル討論の時間は |
|
|
項 目 |
合 計 |
|
|
1.長い |
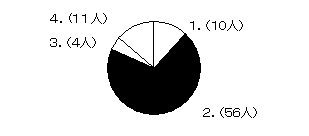
|
|
|
|
|
2.丁度良い |
|
|
|
|
3.短い |
|
|
|
|
4.回答無し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「長い」と答えた人が12%、「丁度良い」と答えてた人が69%であった。 |
|
|
| (3)案内や進行について |
|
|
|
・討論する時間を設け司会者(座長)のご苦労大変だったと思う。 |
|
|
・長すぎるコメントは司会者が中断すべきでは。 |
|
|
・司会(座長)の意見と質問をわかり易くすることが必要では。 |
|
|
・パネリストが一寸多すぎるのでは。 |
|
|
・フランスの事情は休憩の後に入れるべき、午後の前半が長すぎた。 |
|
|
・マイクの調子が悪い、事前のマイクテストが不充分。 |
|
|
・部屋の温度調節が良くない(暑すぎた)。 |
|
|
・質問票の回収のタイミングや進行上の呼びかけがあいまいであった。 |
|
|
・10時〜17時は少し長い。 |
|
|
・時間を守って貰いたい。(帰りの都合) |
|
|
等 |
|
|
| 問10.SNWの活動や次回のテーマ等についての意見、提言(15件) |
|
|
|
|
コミュニケーション問題について |
|
|
|
・今後もコミュニケーションについて引き続き取り組んで欲しい。次回は一歩進めて少し具体的 |
|
|
なテーマを取り上げて欲しい。「コミュニケーションの失敗」について等。 |
|
|
・原子力問題に関するコミュニケーションがいろいろのものがあり、過去の事例研究を含めて |
|
|
検証してもらう企画があれば素晴らしい。 |
|
|
・日本の情報発信が遅いとマスコミが言うが企業罪悪論でいじめの対象になり、言い直しを |
|
|
許さない社会通念をどうすれば直せるか。 |
|
|
・若人と老人のダイアローグの場としてのシンポジューム。 |
|
|
・マスメディアの現役とOBを巻き込んだ議論が必要。 |
|
|
・立場を考慮しない本音のトーク。 |
|
|
・コミュニケーションというか、対話形式。 |
|
|
・原子力関係者以外の人をどう引き込んでいくか。 |
|
|
・原子力110番。 |
|
|
・SNWメンバーの皆さんが今の電力会社を変えようとしている人々に口出ししたり、力を及ぼ |
|
|
さなければもっと原子力と社会とのコミュニケーションは良くなります。 |
|
|
|
教育問題について |
|
|
・新学習指導要領の最重点キーワード「持続可能な社会」をテーマに。 |
|
|
・原子力教育について。 |
|
|
・対話を深化させるためにはエネルギー教育が必要。 |
|
|
・エネルギー学の社会人講座。 |
|
|
|
その他 |
|
|
・企業中堅社員向けイベントあるいは中堅社員が参加できる企画を。「食と原子力とのドッキ |
|
|
ング」等一般市民にも身近になる構想の紹介。 |
|
|
(原子力とバイオの話等) |
|
|
| 性別 |
|
|
区 分 |
合 計 |
|
|
男 性 |
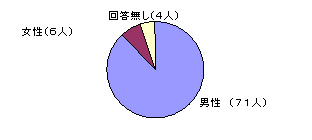
|
|
|
|
|
女 性 |
|
|
|
|
回答無し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年齢 |
|
|
区 分 |
合 計 |
|
|
2 0 歳 台 |
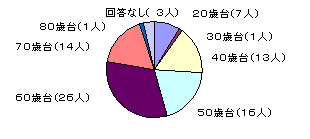
|
|
|
|
|
3 0 歳 台 |
|
|
|
|
4 0 歳 台 |
|
|
|
|
5 0 歳 台 |
|
|
|
|
6 0 歳 台 |
|
|
|
|
7 0 歳 台 |
|
|
|
|
8 0 歳 台 |
|
|
|
|
回答無し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職業 |
|
|
区 分 |
合 計 |
|
|

|
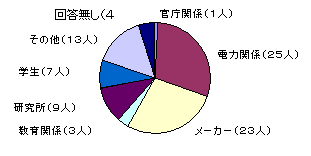 
|
|
|
|
|
電 力 関 係 |
|
|
|
|
メ ー カ ー |
|
|
|
|
教 育 関 係 |
|
|
|
|
研 究 所 |
|
|
|
|
主 婦 |
|
|
|
|
学 生 |
|
|
|
|
そ の 他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(複数回答 4件) |
|
|
その他はコンサルタント、団体事務局、自営等。 |
|
|
以 上 |
|
|
|
|
|
|
|
|