��w�ɂ�����w���ƃV�j�A�̑Θb���{�T�v
�|�Θb in ���|

�P�D���{��|
�@��N�x���瑱���Ă���u�w���ƃV�j�A�̑Θb�v�̈��ŁB����w�������Z�ƂȂ�A�}�g��w�y�ь����Ō������̌c����w�A�Ȃ�тɊw���A�����\�̓��C��w�̂S�Z�̊w�����Q�������B���{���q�͊w��̊w���A����y�уV�j�A�l�b�g���[�N�i�r�m�v�j���A�g���A���q�́^�G�l���M�[�n����̂Ƃ����w���ƃV�j�A�̌𗬂�}����̂ł���B�����SNW��Â̊����Ƃ��Ă�4��ځA�G�l���M�[���ɔ�����������p���A�ʎZ�ł�11��ڂƂȂ�B
�Q�D�Θb�̖ړI
�@���q�͌n���n�w�����ƃV�j�A�Ƃ̑Θb��ʂ��āA�w���ƃV�j�A�̑��ݗ�����}��Ƌ��ɁA����̌��q�́A�G�l���M�[�Y�Ƃɂ��ċ��ɍl���A���ꂩ��̑Θb�̂������G�l���M�[����̎��H������̎Q�l�ɂ���B�܂��A�ނ�w�����Љ�֏o��܂��ɁA���q�͂n�a�̌o����C�T�������ł��z���ł���@�����A����̎����ւ̎��M�Ɍq���Ă��炤�B
�R�D�Θb�̎��{
�i�P�j�����@�����P�X�N�Q���P0���i�y�j�@�P�R�F�O�O�`�P�V�F�O�O
�i�Q�j�ꏊ�@����w�H�w�������L�����p�X
�i�R�j�Q����
�@�@�w���@�@�R�O���i�w�����T���A��w�@���Q�T���j
�@�i����j�����F�Q�R���@�}�g��F�T���@�c����F�P���@���C��F�P���i�I�u�U�[�o�[�A�w���A�����\�j
�A�V�j�A�@�@
�@�@�E�r�m�v�����P�Q��
�|���N�v�A�r�䗘���A�␣�q�F�A���씎���A�����m���A�V���L�O�A�c���C�j�A�y�����Y�A�v�c�����A���c�}���j�A�Έ������A�ҏ��v�i�I�u�U�[�o�[�j
�B��w
�@�@����w�H�w�����w�����@�@�@�@�@�@�O�썎�A����
�@�@����w�H�w�����Y�������Z���^�[�@�ԓc��������
�i�S�j���{���e�@
�@�@�@�����u���@
�E�ꏏ�ɍl���悤�I���B�̃G�l���M�[�Ɗ��@�@�@�@�@�@�@�@���씎����
�A�Θb
�@�U�O���[�v�ɕ�����A�V�j�A�Q�`�R���ɑ��āA�w�����R�`�S�������đΘb�B
�Θb�̑�ނ͊e�O���[�v�őΘb��i�߂Ă����i�K�ŁA�w�����̋����ɏ����āA�e�O���[�v�����߂��B
�Θb�I����Ɋe�O���[�v����Θb���e�̂܂Ƃ߂Ɛ������Ȃ���A�V�j�A���\���ĉv�c������u�]���������B�@
�i�T�j����
�@�V�j�A���犴�z�����W�B�w���ɂ͎���A���P�[�g�����{�����B
�i�V�j�A���z�T�v�j
�w�N���̖Z���������ɂ��ւ�炸�A�����̗\�z���z����l���ƕ����Z�̎Q���āA����ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł����B���q�͂̌����J���̋��_�ł��邱�Ƃ���A�Ȃɂ����X�Ƃ������O�����������A�ɂ߂Ă܂��߂Ȑl��������ŁA���q�͂ɑ���F�������������B
���̈���A�c�_�ɐH������Ȃ����c�������A����̓O���[�v�̐l���i�w��4�`5���{�V�j�A2���j�Ƃ��́A���Ԃ�����Ȃ��̂�����ł͂Ȃ����Ǝv����B
�w���̎���ɂ�����x�V�j�A���̉�����Ɏ��Ԃ��Ƃ���͔̂������Ȃ��̂ŁA�V�j�A�̊�u�����ߑO���܂����H���Ԃ𗘗p����Ȃǂ���l�ł���B���O�ɂ������e�[�}��ݒ肵�Ă����I�����Ă��炤���@�Ȃǂɂ��O���[�v�Ґ������߂ɐݒ�ł���A���[���Ŏ��O�Ɏ��₵�Ă��炤�����Ȃǂ��l������B
�i�w���̃A���P�[�g���ʊT�v�j
�o�Ȏ�30���i�I�u�U�[�o�[2���܂ށj�̂���26�������������B
96���̊w�����Θb�̕K�v�����������̉��������B�ʏ�̎��ƂƂ͈Ⴄ���e�����h�������������̂Ǝv���B
�G�l���M�[��@�ɑ���F���ƌ��q�͂ɑ���C���[�W�̕ω������Ɖ����w���͖�65���ł������B���ΔR���̕s���≷�g���Ɋւ��ẮA������x�̒m�������w���������������Ƃf���Ă���̂ł��낤�B
����A���O�ɕ��������Ǝv�������Ƃ��������Ɖ����w���͔�����50���ŁA�����͕����Ȃ������Ƃ̉��������B���Ԃ̐���A�O���[�v�Ґ��̖������낤���A���̑Θb�Ŋ��S�Ȗ�����͓̂���B�N���ł��p�����čs���A���Ƃ��ĎЉ�ɂł�܂łɕ�����Θb�ɎQ�����邱�Ƃ��\�Ǝv���B
���̑��A�w�Z�����ی�҂ɑ��鋳��ւ̊S�ƁA���R�G�l���M�[�̗������i�悤�Ɏv����B�I�C���s�[�N�⎩�R�G�l���M�[�̃|�e���V�����Ȃǂ�̌n�I�ɗ�������@��͂��܂�Ȃ��Ǝv���̂ŁA��u���Ƃ��̌�̓��_�̈Ӌ`�͑傫���Ǝv���B
���̑Θb�W��͖�92���̊w���ɖ������Ă��炤���Ƃ��ł����B
�e�ݖ�͈̉ȉ��̒ʂ�ł���i�ڍׂ͓Y�t�����Q�Q�Ɓj
�i�P�j�u�w���ƃV�j�A�̑Θb�v�̕K�v���ɂ��Ăǂ̂悤�Ɋ����܂����H
�@ ���ɂ���@�@�@�@�@�@�F19
��₠��@�@�@�@�@�@�@�F
6
���܂�Ȃ��@�@�@�@�@�@�F 1
�S���Ȃ��@�@�@�@�@�@�@�F
0
���@�@�@�@�@�@�@�@�F 0
�i�Q�j�G�l���M�[��@�ɑ���F���ɕω��͂���܂������H
�傢�ɕω������@�@�@�@�F 4
�����ω������@�@�@�@�@�F13
���܂�ω����Ȃ������@�F 7
�܂������ω����Ȃ������F 2
�i�R�j���q�͂ɑ���C���[�W�ɕω��͂���܂������H
�傢�ɕω������@�@�@�@�F 5
�����ω������@�@�@�@�@�F12
���܂�ω����Ȃ������@�F 8
�܂������ω����Ȃ������F 1
�i�S�j���O�ɕ��������Ǝv���Ă������͕����܂������H
�\�����������ł����@�@�F13
���܂蕷���Ȃ������@�@�F11
�S�������Ȃ������@�@�@�F 1
���@�@�@�@�@�@�@�@�F 1
�i�T�j�Θb�̓��e�͖����̂������̂ł������H
�ƂĂ����������@�@�@�@�F 9
������x���������@�@�@�F15
���s�����@�@�@�@�@�@�F 2
�傢�ɕs�����@�@�@�@�@�F 0
���@�@�@�@�@�@�@�@�F 0
�S�D�܂Ƃ�
�@����͈���w�������Z�ƂȂ�A�}�g��w�y�ь��q�͌����J���@�\�Ō������̌c����w�̂ق��A�w���A�����\�̓��C��w�̊w��1�����I�u�U�[�o�[�Ƃ��ĎQ�������B������w���Q�������Θb�Ƃ��ẮA�u�Θbin���v�A�u�Θbin�����v�ɑ���3��ڂŁA�Q�������w������30���ƁA�����̊��҈ȏ�̂��̂��������B�����߂�����w�O�싳���A����N�̂��w�͂ɂ����̂Ɗ��ӂ���B
�@�V�j�A�����C�E�����n��ݏZ�E�o�g�̃V�j�A�T���̋��͂�12���i�����Q��5���j���Q�������B�Θb��5�O���[�v�A�e�O���[�v�w���T�`6���A�V�j�A�Q�`3���ł������B���炩���߃A���P�[�g�ɂ��ƂÂ��A��]�e�[�}�ɂ������O���[�v�������s�����̂ŁA������x���҂ɉ�����ꂽ�Ƃ͎v�����A�\�������������Ƃ������Ȃ������Ƃ̃A���P�[�g�҂�����A������o�Ȃ̃`�����X������ƃt�H���[�ł���̂ł͂Ȃ����v����B�N1����I�Ɏ��{����A���Ƃ܂ŕ�����Q������@�����A�X�ɖ����ł���悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�܂��A�����V�����̂��s�͂ň���w���w���ȂǁA����Ɋ֘A����w���̏����c���ł��A���q�͌����J���@�\�ɔh������Ă��錤�������܂߁A�Θb�̗ւ��X�ɍL���邱�Ƃ����҂����悤�ɂȂ������Ƃ͊�������Ƃł���B
�T�D����̗\��
�@�R���R�O���i���j�@���É���w�ɂ�����Θb�@
�@�@�@��������w�@�P�R�F�O�O�`�P�V�F�O�O
�U�D�Θb�ʐ^
�Y�t����
�Y�t�P�@�@�V�j�A���z
�Y�t�Q�@�@�w��������A���P�[�g����
�Θb�ʐ^

�J��Ɛ���

���씎�����̊�u��

�Θb���i
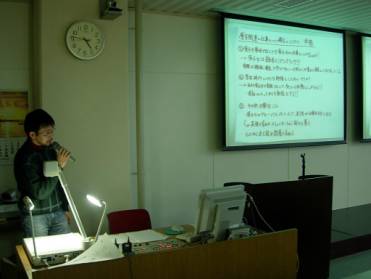
�w�����\

���e��
�Y�t�P�@�V�j�A���z
�␣�q�F
�T. �S��
����́A����w�A�}�g��w�y�ьc����w�A���C��w�̊w���w���A��w�@�w���A�����R�Q���A����w�̐搶�A�V�j�A�l�b�g���[�N�P�Q���̏o�Ȃ̂��ƂŁA�Θb�������ꂽ�B
����́A�Q���̊w���͂���������q�͂̐�U�łȂ����A�G�l���M�[�A���A���q�͂ɂ��đ傫�ȊS�������Ă��邱�Ƃ��A�Θb��i�߂钆�ʼnM���m�邱�Ƃ��ł��A���̂悤�ȑΘb�́A���q�͌n�����̓G�l���M�[�A���Ƃ͌��肹���ɁA�ϋɓI�Ȋw���̕��X�ւ͍L���Q�����Ăт���������A�V�j�A�l�b�g���[�N�̊����̎�|�ɍ��v����Ƃ̎v������������������ł��B
�U. �w���Ƃ̑Θb�@
�P�D�S��
�J��̈��A�̌�A����V�j�A����u�ꏏ�ɍl���悤�I�@�������̃G�l���M�[�Ɗ��v�肵�Ċ�u�����s���A���x���̍����������ێ��A�m�ۂ��Ă�����ł̃G�l���M�[�̑���A�܂�����I�Ȋm�ۈێ��̂��߂Ɉ�l��l�����̉ۑ�̑�Ȃ��ƁA���E�̃G�l���M�[�}�[�P�b�g�̍���̓W�J�ƌ��q�͂����̒��ł̑�Ȗ������ʂ������ƁA���҂���邱�ƂȂǕ�����Ղ����b���Ȃ��ꂽ�B
�Q�D�O���[�v���_�ɂ��āi�c�O���[�v�ɏo�ȁA�V�j�A�R���A�w���U���j
�O���[�v�̂܂ƂߒS���҂����߂���A�w��������e���̐�U�̊T�v�Љ�A�V�j�A������ߋ��̋Ɩ����e�A���тȂǂ��Љ�A�ӌ��������s�����B
�V�j�A����͎Ⴂ�l�̌��q�͕���ւ̐ϋɓI�ȗ����ƁA�\�Ȃ炱�̕���ł̊�������҂��A���̂��߂ɂ��̂悤�ȑΘb�̋@���ʂ��āA���C�Â��A���@�t�����o���邱�Ƃ����҂��Ă��邱�Ƃ��B
a.�w���̎�ɊS���������ɂ���
����̎Q���w���͌��q�͐�U�łȂ����A���q�͂�G�l���M�[�Ȃǂɂ��ĊS���������ɂ��āA���̂悤�ɔ������������B
�E �G�l���M�[�����o�����X�A���q�͂ƉΉA�����͐V�G�l���M�[�Ƃ̃x�X�g�~�b�N�X�͂ǂ�����ׂ����H
�E �䂪���́u���q�͐�����j�v�A�u�����̕��j�Q�O�O�U�v�ɂ��āA���e��m�肽���B
�E ���q�͎{�݂̗��n�̎���̂��߂ɗ��n�n��Z���̗����邽�߂ɓ����҂͂ǂ̂悤�ȑΉ������ׂ����H
�E �䂪���̃G�l���M�[�����ɉ����鎩���͂ǂ�����Ή\�ɂȂ邩�H
�E �G�l���M�[�����͍���^�C�g�ɂȂ�Ƃ̌��ʂ����������A���������͕ۂ���邩�A�܂��͂ǂ��Ȃ�̂��H
b.�O���[�v�S�̕�
�w���̑�����̊S�e�[�}�̔����܂��ẴO���[�v���_�ɂ��V�j�A����w���ւ̉̊T�v�͎��̂Ƃ���B
�E �G�l���M�[�����A��v���Y�����ł���Ζ���������̔��d�͉\�Ȍ��茴�q�͂𒆐S�ɂ܂����邱�Ƃ��A�����̑����I�ɖ]�܂������p�E���p�ł���B�]���ēd���\���͌��q�͂���ɁA�ΒY�A�Ζ��܂��\�Ȕ͈͂ŐV�G�l���M�[�Ƃ��鏊���x�X�g�~�b�N�X�𐄐i����B���q�͂��M�������d���ƈʒu�Â�����悤�A�W�҂͖��_������A���ꂼ��̗���ł�����y�����邢�͉������邱�Ƃɐs�͂��ׂ��ł���B�w���̕��X������Љ�ɂłĂ��̂悤�ȗ���ɓ������Ȃ�A������Ăق����B�V�j�A���M�����̌���ƈ�ʂ̐l�X�̗�������悤�A����܂ł�����Ă��܂����B
�E ���q�͗����̗��O�̂��ƁA���q�͂Ɍg���Z�p�҂͂��̗ϗ����т��ċƖ����s�����Ƃ����߂���B
�E ���q�͎��̂⎖�ۂɂ��Ă̂���܂ł̃��f�A�̎�舵���A�Ή��͕K�������ǂ��Ȃ������B�����̓��e����Ղ���ʂɗ������Ă��炦��悤�w�͂��邱�Ƃ�ނ�ɋ��߂邱�Ƃ��K�v�ł���B
�R�D�S�̔��\
�T�O���[�v�ɕ�����Ă̑Θb���_�̌��ʂɂ��āA�e�O���[�v�����Ȃ��ꂽ�B
�`�O���[�v
���������̈ێ����W�̂��߂Ɍ��q�͂̔��W�͕K�v�ł���B
���́E���ۂւ̔��ȂƑΉ��ɂ�茴�q�͋Z�p�̉��P�A�M�����̌���͏\�����ҏo����B
���q�͂�G�l���M�[�Ɋւ��鋳��͏\���łȂ��A�}�X�R�~�̑Ή����K�łȂ��B
�W�҂͑��̍��������K�v�ł���B
�a�O���[�v
�G�l���M�[�����̖R�����䂪���́A���q�͗����𐄐i���ׂ��ł���B
���q�͂����ւ̉e����^����Ȃ�K�v�Ȕ͈͂ŋK�������ׂ��ł���B
�b�O���[�v
�䂪���ł̂e�a�q�̓����ƔR���T�C�N���̊����̂��߂ɋ��߂���A���S���A
�o�ϐ��y�э����̗����̂��߂ɊW�҂͓w�͂��K�v�ł���B
�c�O���[�v
�G�l���M�[�����ɉ����錴�q�̖͂����͑傫���A�G�l���M�[�x�X�g�~�b�N�X�_�ŁA50%�ȏ��ڕW�Ƃ��ׂ��ł���B
���f�A�̌��q�͂ɂ��Ă̎��グ���s�\���A�s�K�ł��̖ʂł̉��P���K�v�ł���B
�d�O���[�v
�������q�͊W�̋Ɩ��Ɍg���ꍇ�̐S�\���Ƃ��Č��q�͂͑����H�w�̏W�听�ł���A�e���̐���ʂ����v�������҂ł���B
���Ќ�����r��ӂ�Ȃ��B
���ې���{�����ƁB
�S�D�S�̊��z
�Q�������w���̊F�l�͂���������q�́A�G�l���M�[�����͊��W�̐�U�łȂ��ɂ��ւ�炸�����S�A�ӎ��������Ă��邱�Ƃ��Θb�̂Ȃ��ŁA�V�j�A�ւ�������ۂÂ���ꂽ�B���̂悤�ȊS�̂��ƁA���q�͂̓G�l���M�[���̎�v�A���s���Ƃ̋��ʔF���������Ă��炤���Ƃ��o�����B����͂Ȃɂ��̐��ʂƌ�����B
���q�͂Ɍg���҂Ƃ��č����ϗ������߂���̂͐��Ԃ���̐M���邽�߂ɓ��R�Ƃ̔F�������ׂ����Ƃ��w���̕��X�͗������Ă��邱�Ƃ����������B
�V�j�A�l�Ƃ��āA�ӗ~�ɔR�����Ⴂ�l�����ƑO�����̑Θb�����Ă����ƁA��������̂悤�ȋ@���ʂ��āA���q�͂̑�Ȏ��̗�����[�߂邽�߂ɎQ���o����Ǝv����������������ł���܂��B
���씎��
���O�����̂���
�w���̎��Z�߂ɂ����������]����A���w�����������O��搶�ɂ́A����ł̑Θb��ւ̂��Q���ȗ��A���X�Ȃ�ʂ��������d�˂��A�܂������A���x�����������ԓc�搶�ɂ������b�ɂȂ�܂����B�r�m�v���ł������ɂ�����ꂽ���X���܂߂āA�����̊F�l�̂��s�͂Ɋ��ӂƌ���\���グ�����B
����I�ɂ͊w�O�𗬂��Ȃ��ł��낤����E�}�g��E�c����̊w�����N���A�ꓰ�ɉ�Č𗬂��A�V�j�A�Ƃ̑Θb����@����Ă����Ƃ́A����A�V���ȓ����Ă�����ŁA�M�d�ȑ̌��ł��������ƂƎv���܂��B
�V�j�A�̔��ȂƊw���ɖ]�ނ���
����̂��Ƃł����邪�A�����V�j�A���̔����������Ȃ邱�ƂȂ��Ă��܂��B
�w�����N�̗����Ȏ����ӌ��������o���A����ɋɗ͒��J�ɉ����悤�Ƃ���̂����A�Θb�̐��i���ނȂ��Ƃ���ł����낤���B
�w�����ł̎��O�A���P�[�g�ɍۂ��āA���[�����O���X�g�����p�������O�̈ӌ������̏ꂪ���Ă�A�X�ɏœ_���i���������ȑΘb�����Ă�̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����B�������̕��ׂ������Ė����ł��낤���H�@�w���A����ł̌�����҂������B
���q�̓V�j�A�̍ő�̔��Ȃ́A��������ɎЉ�����āu��������ė����v���Ƃ��B
���̂��Ƃ��A�G�l���M�[�Ɗ����A�Ȃ������q�͂ɑ���Љ�̗����Ǝ�e������ނ����Ă������ł�����B���ꂩ��̎Љ�l�́A�u������������Ɓv�ł͂Ȃ��A�u����������Ɓv�A�u���瓹�����Ɓv�łȂ��Ȃ�܂��B�Љ�̕�����ۑ�ɑ��āA�����͎��炪��g��ł���e�[�}�ɑ��āA�w�����N�͎���̎��_�ő��������ӎ��ƁA����ւ̈ӌ��𗦒��ɏq�ׂ�b�B��ς�ŗ~�����B��ɁA�r�W�l�X���O���[�o�������������́A�u����������Ɓv���������߂���̂ł͂Ȃ��낤���B
�����m��
�w���Ƃ̑Θb�ɏ��߂ĎQ�������B���씎������́u�ꏏ�ɍl���悤�I�@���B�̃G�l���M�[�Ɗ��v�Ƒ肷���u���̂��ƁA�O���[�v�ɕ���đΘb���s�����B�Θb�̒��ŁA���q�͂̏A�K�v���Ȃǂ̘b���o�邽�тɁA��u���̓��e��Ꭶ���邱�Ƃ��ł��A�w���B�ɂƂ��đ�ϗL���ȍu���ł������B
�@�A���P�[�g�������ʂɊ�Â��āA�ۑ薈�ɂT�̃O���[�v�ɕ����Θb���s�������A�b��ɏW��������_�ł���͗L���ł������B
���͐Έ䂳��ƂƂ��ɂd�O���[�v�ɎQ�������B���̃O���[�v�́A�@���q�͐�U�ł͂Ȃ����A���q�͎Y�ƊE�͎���邩�A�ǂ�Ȃ��Ƃ��w��ł����悢���A�A���q�͂̎Љ�ւ̎�e���A�ɂ��Ęb���������B
�w���B�́A���q�͂͊w��ł��Ȃ������q�͎Y�ƊE�͎���Ă���邩�Ƃ������Ƃɗ\�z�ȏ�ɋ����S�������Ă����B���B�̌o������A���q�͂͑����Z�p�ł����镪��̐l��K�v�Ƃ��Ă���̂ŁA���q�͐�U�łȂ��ł��S�����͂Ȃ��B�e�X�����Ƃ��镪����\���Ɋw�ї͂����Ă������ƁA����ɂ̓G�l���M�[�A���q�͂ɊS�������Ƃ���Ȃ��Ƃ�`���A�[�����Ă�������B
���q�͂̎Љ�̎�e���ɂ��āA���ꂼ��̈ӌ����o�����������A���q�͋Z�p�҂���O�ɐϋɓI�ɐ������Ă������ƁA�}�X�R�~��A���E���E���Z�ł̃G�l���M�[����x������ł��邪�A����ɂ͏����搶�ɂȂ�l�B�A�Ⴆ����w���̊w���ɑ�����̂悤�ȑΘb���L���ł͂Ȃ����Ǝw�E���ꂽ�B�Ȃ�قǂƊ������B
�Θb��̍��e��͂��������ȉ�b���ł��A���ʏ�X�ł������B
�Θb�Ƃ����ɂ́A�V�j�A�������b���߂������炢�͂��邪�A���̂悤�ȋ@����d�˂邱�Ƃɂ��Ⴂ�l�B�̔����������A������z�����{���̑Θb�������o����̂ł͂Ȃ����Ƃ������҂�����������ł������B
�V���L�O
�悸�A���̂悤�ȉ�̏��������ꂽ�W�҂̓w�͂̍b�オ�����āA�y�j���ɂ��S��炸�A�����͂��Ύs����̎Q�����܂ߊw��������30���W�܂�A�V�j�A��12���ƃo�����X�̂Ƃꂽ���̂ƂȂ������Ƃ͐����ł������Ǝv���܂��B�܂��A���쎁�ɂ��G�l���M�[�Ɗ��̖��_��ԗ��I�ɗv�̂悭�������ꂽ�̂́A�w���ɂƂ��đ�ϕ�����Ղ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B5�̃O���[�v�ɕ����ꂽ�̂ŁA���̃O���[�v�̂��Ƃ͂悭������܂��A�����́u�j�R���T�C�N���ƍ������B�F�v�����Ƃ���O���[�v�őΘb�����܂������A���Ԃ������Ă��邱�Ƃ�����A�قƂ�ǃV�j�A������̐����ƂȂ�A�����x�����ː��p����������A�ď����A�T�C�N���R�X�g�A�������B�F���p���̉ۑ蓙�X�ɂ��ĕK�������s������͂Ȃ��A���̈Ӗ��ł́A�����������ԓI�]�T�������Ă��˂����c�_�����҂������Ɗ����܂����B
�S�ʓI�ɂ́A�e�O���[�v�̔��\�ŁA���ׂ��炭�A��ʂ̐l�͂���w�G�l���M�[���A���q�͖��ɊS�������w�K�����ׂ��ł���A�}�X�R�~�͌��q�͂̃l�K�e�B�u�L�����y�[�����肹���܂��Ƃ��ȕ����ׂ��ł���Ƃ܂Ƃ߂Ă������Ƃ͍����]������A�ޓ�������𒇊Ԃ�Ƒ��A�אl�Ɋg���Ă���邱�Ƃ�]�݂����Ƃ���ł��B
�V�j�A�̑Θb���w���Փ��̋@��ɁA��ꕔ�͈�ʎs���A���n���܂߂��w���Ƃ��A��ŎQ���l�����i����˂������ڂȑΘb�Ƃ��邱�Ƃ���Ăł͂Ȃ��ɂ��Ǝv���܂��B
�|���N�v
��������Ɋ��z�߂������̂𑗂�܂������A�����ł͂Ȃ������̂ŁA��t�L���܂��B
�@����͂r�m�v�ɑ��Ċw���䗦�����������̂ŁA�w���O���̈ӌ����\�̋@����Ȃ������B�S���i�C�[�u�߂��āA�����ޓ��̈ӌ��q���w�ǂȂ������͕̂�����Ȃ��B
�A�Θb��̎��Ԃ��Z������̂ŁA�㔼�̓O���[�v���\�Ƃ����V���A�Z�����j�[�ɕ߂���ăW���j�A���݂̋c�_�Ɏ��Ԃ��Ȃ��A���\�̑̍ق���̋c�_�ɂȂ��Ă��܂����B
�B�N���Ɠ����ӌ������A�r�m�v�̘_���i���삳�S�j�͐H�����܂��͌ߑO�ɂ��āA�W���j�A�̗����Ə����ɂ����������Ԃ�^�����ق����ǂ��Ǝv���B
�C���Z�́A�^�ʖڂŁA�f���ł����_�͗ǂ����A�c�_�ɐ[�݂��Ȃ������B�i�����̐��E�^�Ƃ͈Ⴄ���A������_�ɂƂǂ܂������Ƃ́A������Ȃ������B�j
�D�������Ԃ��Z�������̂ɁA�\�z�ȏ�ɎQ���҂���A��^�c���������������Ƃɂ͐搶���͂��ߊW�ҁA�����̂��s�͂ɐ[�ӂ��܂��B
�c���C�j
���炭��҂̌��q�͗��ꂪ�������q�͂̏��������O���Ă���܂����B����͒n���J�ÂƂ������Ƃ��L��A�ŋ߂̎Ⴂ�l�B���ǂ̂悤�Ɍ��q�͂𑨂��Ă���̂��m�肽���A�܂����q�͂ɑ��ĕs�����S�z��������Ă���悤�Ȃ炻��������ق��������ɂȂ��Ǝv���A���߂ĎQ�������Ē����܂����B
���q�͐�U�̊w�Ȃ̂Ȃ���w����̎Q���҂Ƃ������ƂŁA�ǂ�Șb����яo�������������S�z���Ă���܂������A�w�N���̖Z���������ɎQ������ʂł����猴�q�͂ɊS�̗L��l�B�ł��邱�ƂɊԈႢ�Ȃ��A�܂��g�߂ɓ��C�����L��ƌ����y�n���̏��ׂ��A�ʒk�����w������݂͂Ȍ��q�͕͂K�v�ƔF�����Ă���f���Ȑl����ŁA��҂ɗL�菟���Ȃ����܂����l���̎�����͌������炸���S���܂����B
��̐i�s�͋ɂ߂ăX���[�X�ŁA�W���ꂽ�w������A�����̐搶���̂��w�͂̎����Ɛ悸�͊��ӂ������Ǝv���܂��B���삳��̊�u�����i�������A����̃G�l���M�[����ƌ��q�͂̈ʒu�t�����������A����ɑ���\���̗���������ꂽ���Ƃ͍��e��ł̊w������̔����ł����Ăł����B
�����O���[�v���_�̍ۂ̃e�[�}�I��ŁA�����悤�Ȗ��ɊS���������l�B�Ƃ������ƂŃO���[�v��������Ă���ɂ��ւ�炸���Ɏ��Ԃ��|���蓢�c�̎��Ԃ����Ȃ��������ƂƁA�w������B�����܂�ϋɓI�ɔ������Ă��ꂸ�M�S�ȓ��c�ƂȂ�Ȃ������̂��c�O�Ȃ��Ƃł����B
����̑Ή��Ƃ��āA�O���[�v���������l���ɂȂ�Ȃ������m��܂��A���O�A���P�[�g�̍ۂɃe�[�}�Ă���Ă����Ċe�e�[�}���Ɋ�]�҂��W�߂�Ƃ������Ƃ��l�����Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B�܂����̃e�[�}���ɒS���̃V�j�A���A�T�C�����Ă����V�j�A������Ȃ�ɏ������ėՂ߂邱�ƂɂȂ���葽�����c�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂�����̉�Ő܊p�m�荇�����V�j�A�Ɗw���̊W���P�����ŏI��点��̂͐ɂ����悤�Ɏv���܂��B���Ζʂł͂Ȃ��Ȃ��b���Â炢�Ƃ����ʂ��L��ł��傤�B���ȉ�I�Ȃ��̂łł��ʒk�̉��d�˂�����Ɩ{���̘b��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i������_�@�Ƃ��Ď���𗬂��o���Ȃ����̂��Ǝv���O���[�v�̊w������ɁA�b����Ȃ��������Ƃ��L��Ȃ�ł������Ăƃ��[���𑗂�܂����B���݂̏������͂P���j
���e��ŏo���邾���w������̘b���悤�ɂ��܂������A�w������̊S�͎Љ�l�ɂȂ�ɓ������Ă̐S�\���A�����ҁE�Z�p�҂Ƃ��ĐS�|����ׂ����ƂɗL��悤�ŁA�ɂ߂Đ^�ʖڂȐl�B����B�\�����q�͂̏���������ɑ���l�B���ƈ��S���܂����B���ꂩ��V�j�A�̐l�B����������傫�Ȏd���𐬂������ė����l�B�ł���A���q�͂ɕ��X�Ȃ�ʈ���������Ă���Ƃ������ƂɊ��������ƌ����Ă���܂����̂ŁA��X�̌��q�͂ɑ���M���v���͏\���ɓ`������悤�Ɋ����܂����B
�y�����Y
���߂ĎQ�������Ă����������y���ł��BOB�̊F�����q�͂𗝉����Ă��炤���߂ɓw�͂���Ă����ɗ������킹�Ă��������A���ӂ��Ă���܂��B�ǂ����Ă��V�j�A�̊F����̔����������āA�Θb�܂ł����Ȃ��Ƃ��낪����܂������A���{�l�̃V���C�ȏK�����āA�ϋɐ��E���C��{�����Ƃ��܂߂�����������Ă���l�q�Ɋ������܂����B����Ƃ���낵�����肢�������܂��B
�v�c����
�Θb�Q���ҁi�O���[�vC�j
�V�j�A�F�ē��L�O�A�ҁ@���v�A�v�c����
�w���F������GM2�AA.BucheeriD1�A�k�ݖ�M1�A����VM1�A��a����M1�A���c�a��M1
�Θb��ʂ��Ă̊��z
M2�̈���N�ɋc�������肢���A�o���̎��ȏЉ��A�A���P�[�g���ʂ���ɑΘb�ɓ������B�F�A�C�m�̊w���ŁA���q�͂���ɂ��Ă���w���͏��Ȃ��������A�����̃G�l���M�[�͌��q�͂��嗬�ł���Ƃ̔F���������A���q�͂ɂ��Ă̔F���͍��������B
�����F�ɊS�������O���[�v�Ƃ������ƂŁA�ē��L�O�搶���p�ӂ��ꂽ�����̃p���t���b�g����ɐ����ɓ������B
�w�������ǂ̂悤�ȓ_�ɋ����������Ă���̂������o���w�͂͂������A�ǂ����Ă��V�j�A�̐�������ɂȂ��Ă��܂��̂́A����̂��Ƃł͂��邪���Ȏ����ł���B
����̃O���[�vC�̂悤�ɉ����𒆐S�ɘb�������̂ƁA�L���w���̈ӎ������@�ƁA�傫��������2�̍s����������A���Ƃ��Ă͌�҂�I�т����C�����邪�A�꒷��Z�ł���B
�w��6�l�͑�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̔��Ȃ������悤�ł��邪�A2�F6�Ɖ]���̂͑����ґ�ȑg�ݍ��킹�ł���A�����ς���K�v�͂Ȃ��Ǝv���B����������Ԃ��Z���̂��ǂ����H������Ȃ��ތ����ł͂Ȃ��낤���B
�J��ݒ�̓���A�o���̕��S�Ƃ����_�͂��邪��x�A�ߑO���u���A�Z�����H�i�L���T���h�E�C�b�`���͈���сj�x�e�̌�A�����������Ԃ��|�������c�����Ă݂�̂���Ăł��낤�B�X�ɁA���₵�����l�́A���O��E�\MAIL���Ŏ�����o���Ă��炤�H�v�i��������\���O�ɖ���N�����Ă���l���������j���K�v�ł��낤�B�w���̎��ȏЉ��EXCEL�ŏ���������ăV�j�A�Ɠ��l�z�z����i��������b������ςł��邱�Ƃ͗����ł���j�b����o���₷���悤�Ɏv���B
���c�}���j
�P�D�O��搶�̓w�͂Ō��\�Ȑl���ɏW�܂��Ă���������͎��n�ł��B(ꎓ��L�O����̉e�̌�s�͂�����������m��܂����B�L��������܂���)
�Q�D���삳��̒��J�Ȑ������D�]�ł����B
�R�D �O��搶����w���Ղł̍Â��ł������ǂ����Ƃ�����Ă��L��A������������b�ł��B
�S�D�l���I�ɂ�1�`�[��6�l�Ŏ���������̂��炢�͗L��܂��B20�l�Q���Ƃ��������v����Z�ł����B
�T�D�l���������ƈ�l������̘b���@����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�w���̔��ȉ�ɂ������悤�ɂ�������1�`�[���̐l�������Ȃ����������ǂ������ł��ˁB�V�j�A�𑽂����Ă������@���ǂ���������܂���ˁB
�U�D �\���I�Șb��������l������A���J�ȉ�S���������Ǝv���܂��B
�V�D ���P�[�g���ʂɃo�C�A�X���������Ƃ��Ă��A�D�]���ɏI���܂����B�W�҂̋��͂𑽎ӂ��܂��B���V�j�A�̕��X�̗��������ӂ��܂��B
�Έ䐳��
��錧�͌����J���┭�d���̗��n���ł邱�Ƃ���A���q�͂ɑ���ӎ��͂��Ȃ荂���A�V�j�A�̔M�ӂ����肷��̂ł͂Ȃ����Ƃ̌��O������Ă������A�w���B�͋ɂ߂Ă��Ȃ��ł������B�ɂ�����ߏ�Ȕ����⏬�����Z�ɂ����鋳����Ȃǂ��܂߂ƁA�V�j�A�̔M�ӂɋ������Ă��炦���悤�Ɏv���B
�������Ȃ���A�Θb��ʂ��Ċw������̎���ɃV�j�A�̉Ƃ����p�^�[������E�����ꂸ�A������Ȃ����c�����B���Ԃ�����Ȃ��̂�����Ƃ͎v�����A���^��������E�����_��ʂ��ĉ���������ł��炤�Ƃ����i�K�ɐi�߂�K�v���������������B�Ȃɂ��̂ɂ������Ȃ��͋����A�S�苭�����A�����̌��q�͂�S����҂Ɋ��҂���������ł���B
�܂��A�w�����̎���ɂ��ׂĉ������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�w���̏[�������s�����Ă���Ƃ����ʂ����낤�B���ł��ׂĖ����Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���̂ŁA�N1��J�Âł���Α��Ƃ܂łɕ�����o�����邱�Ƃ��ł��A���̂悤�ȓ_�͏����͉�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
����A�����{���ɓ��闝�w���Ȃǂ̊w���Ȃǂ��Θb�̑ΏۂƂȂ肤�邱�Ƃ�A����w�̊w���Ղ̊��p�ȂǁA�V�j�A�̊����̕����L����\�������邱�������������Ƃ����n�ł���B
�Y�t�Q
�w��������A���P�[�g�W�v����
�����F26��
�i�P�j�u�w���ƃV�j�A�̑Θb�v�̕K�v���ɂ��Ăǂ̂悤�Ɋ����܂����H
�@�@�@���̗��R�́H
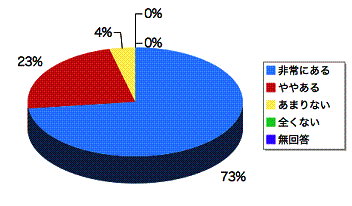 |
���ɂ���F19
��₠��@�F 6
���܂�Ȃ��F 1
�S���Ȃ��@�F 0
���@�@�F
0
���R
�����ɂ���
�E �����Ŋ��Ă����o������������M�d�Ȏ��Ԃ�����
�E �l�X�Ȓm�������������X�ƒ��ڂ��b�ł���͔̂��ɕ��ɂȂ�
�E �V�j�A�̕��X�̘b�����Ă��������ĕ�����Ȃ����Ƃ�������������
�E ���q�͂ɑ��闝����[�߂邽�߂ɏd�v�Ȗ���������
�E �o������@����܂�Ȃ�����
�E �u�`�Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�h������i���̐��j
�E �����Ԍ��q�͂̏����Ă���ꂽ���̈ӌ������Ƃ͏d�v������
�E ���q�͂ɂ��Ă悭�m�����ɗL�Ӌ`�Ȃ��̂ł��邩��
�E ���q�͕͂K�v�s���ȃG�l���M�[�ł���C��Ȃ͍̂����C�s���ւ̗����ł���
�E �o�����ꂽ������
�E �l�X�Ȏ��̌����܂߁D����̎��Ԃ�m���M�d�ȋ@�����
�E �M�d�Ȑ�y�̈ӌ��������ł��邩��
�E �V�j�A���畁�i�����Ȃ������w�Ԃ����@��ł���Ǝv��
�E �`�������v��������C�`�������Ȃ�����
�E ���{�C�����Đ��E�̒u����Ă���G�l���M�[����C���q�͊W�̔w�i���킩�����̂�
�E �����������f������̂ɕK�v�Ȏ����Ǝv����
�E ���q�͂Ɉꏏ����������l�̘b�����@��Ȃ�����
�E ����ɂ����l�̘b�����ŕ�����
�E �����J�̐���ɂȂ��M���ƐӔC������������
����₠��
�E ����ł͐���������ɂ����̂ŁC����͐���������ꂽ�Ǝv����
�E ���q�͂ɂ��Ēm���⌻���m�邱�Ƃ��ł��邩��
�E ���q�͂ɂ��Ă̐������m�����w�Ԃ��ߕK�v
�E �̂�m���Č�������Ă���l�̈ӌ��͑��
�i�Q�j�G�l���M�[��@�ɑ���F���ɕω��͂���܂������H���̗��R�́H
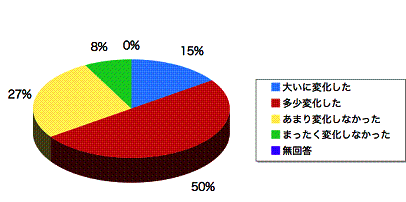 |
�傢�ɕω������@�@�@�@�F 4
�����ω������@�@�@�@�@�F13
���܂�ω����Ȃ������@�F 7
�܂������ω����Ȃ������F 2
���R
���傢�ɕω�����
�E ���߂āC���ꂩ��̃G�l���M�[�̕K�v����F����������
�E �n�����g���Ȃǂ𖢎����Ɋ����Ă�������
�@�������ω�����
�E ������x�����͂��Ă������C����������@�������ׂ����Ǝv����
�E �I�C���s�[�N�ȂǓ���m���������C����ɂ��ς����
�E �����̌��q�͎��Ƃ̊g���m����
�E ��������ڂ����m�邱�Ƃ��ł���
�E ��͂薢�����l����ƃA�u�Ȉ��Ǝv�����D�������������ł͂܂����Ǝv����
�E ���q�͂̕K�v�����ĔF������
�E �G�l���M�[�ɑ����@���͂��������C�����������ς����
�E �G�l���M�[�͊��̖��ɂ����āC�����������߂鎖�͑厖�ł���Ɗ�����
�E �ȑO���瑛����Ă�������
�E �l�X�Ȑl�̘b��������
�@�����܂�ω����Ȃ�����
�E ���̉�ɎQ������O�����@���������Ă�������
�E ���ΔR���̕s���Ȃǂ͉��x�����������Ƃ̂�����e������
�E �ȑO��莝���Ă���
�E ���x�������Ă��邩��
�E ���X�F������������
�E �l���Ă������Ɠ���������
�E ��@�ӎ����L�߂錈�ߎ肪�Ȃ�����
���܂������ω����Ȃ�����
�E ��炠����x�̔F�����������̂�
�i�R�j���q�͂ɑ���C���[�W�ɕω��͂���܂������H���̗��R�́H
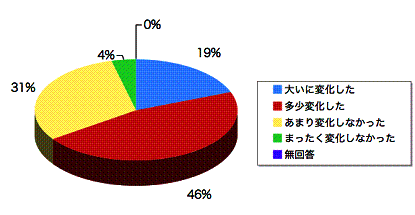 |
�傢�ɕω������@�@�@�@�F 5
�����ω������@�@�@�@�@�F12
���܂�ω����Ȃ������@�F 8
�܂������ω����Ȃ������F 1
���R
���傢�ɕω�����
�E ���S���̖ʂł̈ӎ����ȑO�����悭�Ȃ���
�E ���Ȃɑ��郁�[�J�[�̎��g�݂Ȃǂ��f����
�E ���q�͂̈��S���������ł���
�������ω��������܂�ω����Ȃ�����
�E �G�l���M�[�Ƃ��čl������Ɨǂ����C�܂��܂������̗��������肸������ł���Ɗ�����
�E ����̓��{�ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ���������
�E �����̘Q����Ȃ������łȂ��C�G�l���M�[���Y���������ɍ������Ƃ͒m��Ȃ�����
�E ���q�͊W�҂����ʂ��Ă��������オ�������ƕ�����
�E ���x�C�����������ێ����Ă����ɂ́C�K�v�s���Ȃ��̂��ƕ�������
�E ���q�͂ɑ��Ă�����x�̒m���������Ă������C���[�܂���
�E ��苻����������
�E �����ɂ����ẮC��_���Y�f�̔r�o�ʂ��Ⴂ�̂ł�����������Ȃ���
�E �������Ƃ����ʂł̓E�����̊m�ۂɓ����悤�Ɏv����
�E ���q�͂��d���Ƃ��Ă����l�X�́h���S�h�Ƃ������t�ɔ[�������̂�
�E �V�j�A�̕��X�̘b�������߁C���q�͂͂܂��܂��d�v�ł���Ɗ�����
�@�����܂�ω����Ȃ�����
�E �̂���m���Ă��邱�ƂȂ̂ŃC���[�W�ɕω��Ȃ�
�E ���q�͕͂K�v������ǂ�͂�D����̎Љ�ł͎�����Ȃ��Ƃ�����ۂ͕ς��Ȃ�����
�E ���X���ꂩ��K�v���ƕ����Ă�������
�E ���ɍu�`�ň�ʂ�͒m���Ă�������
�i�S�j���O�ɕ��������Ǝv���Ă������͕����܂������H
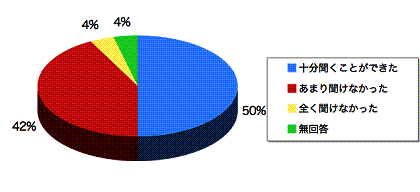 |
�\�����������ł����F13
���܂蕷���Ȃ������F11
�S�������Ȃ������@�F
1
���@�@�@�@�@�@�F
1
�i�T�j�Θb�̓��e�͖����̂������̂ł������H���̗��R�́H
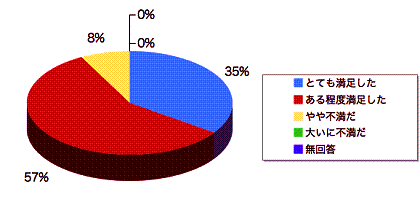 |
�ƂĂ����������@�F
9
������x���������F15
���s�����@�@�@�F 2
�傢�ɕs�����@�@�F 0
���@�@�@�@�@�F 0
���R
���ƂĂ���������
�E ���L���b�������đ�ς��߂ɂȂ���
�E ���낢��ȍl�������Ƃ��ł��ĂƂĂ������ł���
�E ���q�͂̍őO���Ŋ���Ă�����̐��̐����������̂�
�E �ƂĂ��킩��₷������
��������x��������
�E �Θb�̎��Ԃ��v���������Z�������C�F�����������Ƃ�������Ă��Ȃ�����������
�E ���낢��Ȃ��Ƃ�����������
�E �߂��ʒu�ŋc�_���ł�������
�E �Θb�Ƃ������u�`�ɂȂ��Ă��܂�������
�E �����̍l���ȊO�̂��Ƃ��ėǂ�����
�E �����Ȏ���m���Ă���̂ł������Ǝv��
�E �w������������x�������Ȃ��ƁC�Θb�ɂȂ炸�C�u�`�ɂȂ��Ă��܂�
�E �����������Ԃ������
�E ���ɎQ�l�ɂȂ�b�������C�f�B�x�[�g�ł���قǂ̒m���C�l�����w�����ɂȂ��c�O��
�E ����ɑ�������炦������
�����s����
�E �����������e�̘b��̂���O���[�v�ł͂Ȃ�����
�i�U�j���q�͂ɑ���S�̒Ⴂ�P�O��A�Q�O��̎�N�w�ɑ��錴�q�͍L��
�@�@�@�����͂ǂ�ȕ��@���ǂ��Ǝv���܂����H
�E �w�Z�ł̕ی�҂������Ă̋���
�E �w�Z�ł̋��炩��ς��Ă����ׂ����Ǝv��
�E �w�Z����̒��ŕς��Ă������Ƃ��d�v���Ǝv��
�E �w�Z���̖K������āC�A�N�e�B�u�ɍu�������Ă݂�
�E �v���[���e�[�V�����ɒ����l���N�p����
�E �e�ւ̏��`�B
�E ���w���̍�����̋���
�E TV�ŃG�l���M�[���ɂ��Đ��������M���Ă���
�E ���q�͂̋����i�߂�
�E CM
�E �{��C�}�X�R�~��p���čs�������ǂ�
�E ����D�n���Ɍ㉇��Ő������邵���Ȃ��D
�E ���ۂɂӂꂠ���Đ��̐���������Ԃ悢
�E ���f�B�A��ʂ��Ă̍L��
�E �Y�z�ƌ��q�F�̎��҂�������
�E �w�Z�̎��Ƃɑg�ݍ��ގ����K�v�ł���ƍl����
�E �����ւ̋���
�E ����w���v�j�ɓ����
�E �����A�j���[�V����(PR�p)��p����
�E ���S�Ȃ̂ŁC�����C���[�W�����o���Ȃ���Ή������Ȃ��Ă����v���Ǝv���܂�
�E ���C���w�Z�ŏo�O����
�E �Θb�Ɛ���
�E ���ۂɌ��w�ɂ����Ƃ悢�Ǝv���C���̕����b����苻��������
�i�V�j�{����ʂ��đS�̂̊��z�E�ӌ��Ȃǂ�����Ύ��R�ɏ����Ă��������B
�E �V�j�A�̕��X�̋M�d�Șb�������Ĕ��ɗǂ�����
�E �Θb�̎��Ԃ������Ɨ~��������
�E ���ɗL�Ӌ`�Ȃ��̂������̂ō���������������������Ǝv����
�E ���R�G�l���M�[�C���z�G�l���M�[�ȂǂɊւ���C�Ԉ�������������Ă���
�E ����ɃO���[�v��������̂͗ǂ��Ȃ�
�E ���ɎQ�l�ɂȂ邨�b���ėǂ�����
�E �Q�����Ă悩�����D���q�͂ɋ����͂��������C���ۂɎd���Ƃ��Ď������s���ۂ̃C���[�W�����߂�
�E �����̒��̈ӎ����傫���ς��C����Q���ł��{���ɂ悩�����ł�
�E �������̖ʂł́C���q�͂�蕗�͓��̕����������������ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv��
�E �����Ȏ��Ԃ��߂�����
�ȏ�