�Љ�E�������Ì��J�V���|�W�E��
���q�͂̃p�u���b�N�R�~���j�P�[�V�����ɂƂ��đ厖�Ȃ��Ƃ͉����H
�V���|�W�E���̎�|
�Љ�E������ł́A��т��Č��q�͂�����R�~���j�P�[�V�����̖������J���_�̑ΏۂƂ��Ď��グ�Ă��Ă���܂��B����́A���C���ɂ����ďZ���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̗֍��Ɏ��g�܂ꂽ�d�����̓y���q�q����A�q�ϓI�Ȏ��_�Ō��q�͂𑨂��Ȃ������Ƃ��č�N�̊w��܂�����ꂽ�����V���̓��ʊ��𐄐i���ꂽ�{�c�r�͂�������}�����A����ɃR�~���j�P�[�V�����̐��Ƃ̊w�K�@��w�c�������搶�̍u���ō\�����܂����B
���@���@����17�N11��22���i�j13:30�`16:30
��@��@������w�@���c��[�m�r���z�[��
�e�[�}�@���q�͂̃p�u���b�N�R�~���j�P�[�V�����ɂƂ��đ厖�Ȃ��Ƃ͉����H
�v���O����
�P�j�u���C���ɂ����郊�X�N�R�~���j�P�[�V�����̏Z���蒅�����v�@�y���q�q���i�d�����j
�Q�j�u�����V�����ʊ��-���q�͂�₤-��ނƔ����v�@�@�@�@�@�{�c�r�͎��i�����V���j
�S�j�u���q�̓p�u���b�N�E�R�~���j�P�[�V�����̗v���i���Ȃ߁j�v�@�c���������i�w�K�@��w���_�j�@�@
�T�j���^�y�ѓ��_
�����F�{��p�Y���i���{���q�͊w��E�����l���x���������j
 �����̉��̖͗l
�����̉��̖͗l
������̈��A
 �@��N�ƍ��N�A����߂Ă��铌��̉��ł��B�Љ������́A�Z�p�n�̌��q�͊w��ɂ����āA�l���n�������Ă�����Ƀ��j�[�N�ȕ���ł���܂��B�č����q�͊w��ɂ����̂悤�ȕ���͂���܂���B���N�V���|�W�E�����J�Â��邱�Ƃ���̖ڕW�Ƃ��č�N�������Ă���A��N�̂��㔻���̃V���|�W�E���ɑ����č��N���Q��ڂƂȂ�܂��B���Ɍg������W�҂̂��w�͂Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B
�@��N�ƍ��N�A����߂Ă��铌��̉��ł��B�Љ������́A�Z�p�n�̌��q�͊w��ɂ����āA�l���n�������Ă�����Ƀ��j�[�N�ȕ���ł���܂��B�č����q�͊w��ɂ����̂悤�ȕ���͂���܂���B���N�V���|�W�E�����J�Â��邱�Ƃ���̖ڕW�Ƃ��č�N�������Ă���A��N�̂��㔻���̃V���|�W�E���ɑ����č��N���Q��ڂƂȂ�܂��B���Ɍg������W�҂̂��w�͂Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B
�@������͔��ɍL�͂ȕ�����J�o�[���Ă���A���̒��ɍL�����܂܂�Ă��܂����A�o�g��̂ɂƂ���Ȃ����f�I�Ȋw��Ȃ�ł͂̊������ł���_����̓����ł���Ǝv���Ă���܂��B�\�Z�K�͂��������܂��\���Ȑw�e�Ƃ͌����܂��A�V�K������܂߂Ĉ����������x�������肽���A���肢�v���܂��B
����̊��������Љ�܂��ƁA�t�H�̔N��A���̂Ƃ��ɁA�N�ɂQ��̃`�F�C���f�B�X�J�b�V������ݗ���������J�Â��A���q�͂̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Љ���̖����c�_���Ă��Ă��܂��B���̑��ɍ����̂悤�ȃV���|�W�E���ƁA���ꂩ�獡�N����ϑ������A����͂i�m�d�r����̒��������ł����A������n�߂邱�ƂƂ��Ă���܂��B������́A�{�Ƃ͕ʂ����ǎЉ�I���̏d�v����F�����Ċ����������Ƃ����l�����ō\������Ă��܂������A�R�~���j�P�[�V������{�ƂƂ���悤�Ȑl�B�Ɋ����ɓ����Ē��������Ǝv���Ă���A���̂悤�Ȑl�B�ɂ���Ċ������s����悤�ɂ��Ă��������Ƃ��l���Ă���܂��B
�{���̃e�[�}�̃R�~���j�P�[�V�����́A�Z�p���ɂƂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�������ŁA�܂��͂��̍���𗝉����邱�Ƃ��K�v�ƍl���Ă���܂��B�Z�p���ɂƂ��ẮA���̂悤�ȃV���|�W�E����w��������̗����̂��߂ɗǂ��@��ł���Ǝv���Ă���܂��B
�R�~���j�P�[�V�����ɑ��銈���͐��E�I�ɗl�X�Ȍ`�ōs���Ă��܂����A���ł̌o�����W�߂ė������邱�Ƃ��d�v���Ǝv���Ă���܂��B�Ⴆ�A�����m�������W�܂��Č��q�͂̂��Ƃ��c�_���鍑�ۉ�c������܂����A�O��̉�c�ł́A�c�������搶�̃��[�_�[�V�b�v�ɂ��A�e���ł̃R�~���j�P�[�V�����������Љ�����Z�b�V�������݂����܂����B���̎��̔��\�̃p���[�|�C���g�͎Љ������̃z�[���y�[�W�Ɏ��߂Ă���܂����A��X�ƊW�̐[���č��ł́A�m�d�h�i���q�̓G�l���M�[����j�����S�ɂȂ��ċc��⍑���ɑ��ēW�J���Ă���L�����Љ��܂����B�i�L�����Ɗ����܂������A�Ⴆ�A���郁�b�Z�[�W��`����̂ɂǂ��������t��p����̂��K���Ƃ����������Ȃ���Ă��āA���q�͂� �gclean air benefit�h�Ƃ������b�Z�[�W��`����A���S�̃��b�Z�[�W�����̌��t�œ`������A�Ƃ������Ƃ������Ă���܂����B���ЁA�z�[���y�[�W�������ɂȂ��āA�e���łǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă��邩�A���Q�Ƃ��������B
���{�͕č��̂�����^��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�n���̏⒆�����{�Ƃ̊W�Ƃ����Ⴂ�܂��̂ŁA���{�̂����͉�X���g���l���Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B���������@��ɍ����̂��̃V���|�W�E���������ɗ��ĂA����Ƃ��Ă͑�ϗL�肪�����ƍl���Ă���܂��B
�@�Ō�ɍ����̍����̋{��p�Y������Љ���Ă��������܂��B�{�肳��́A�����d�͂Œ������q�͔��d���̌��݂�^�]�ɏ]������A���ގЌ�A���݃j���[�N���A�T�����C���L������Â��Ă����܂��B���q�͊w��̃t�F���[�ł������܂��B����ł͋{������A��낵�����肢�v���܂��B
�{�����
 �@���Љ�ɗa����܂����{��ł��B�{���͂R���̍u�t�̕������������Ă���܂��B��߂̍u�����I������Ƃ���ŁA�x�e�����A�Ō��30���قǎ��Ԃ�����āA���_���s�������Ǝv���܂��B
�@���Љ�ɗa����܂����{��ł��B�{���͂R���̍u�t�̕������������Ă���܂��B��߂̍u�����I������Ƃ���ŁA�x�e�����A�Ō��30���قǎ��Ԃ�����āA���_���s�������Ǝv���܂��B
�@�܂��A�{���̍u�t�̐搶�������Љ�v���܂��B�ŏ��̍u�t�́A�y���q�q�搶�ł��B�搶�͑�w�����ƌ�A�d�����ɂ�����ɂȂ�A���ݏ�Ȍ������ł�������Ⴂ�܂����A�ʎY�Ȏ����G�l���M�[���̌��q�͍L��]��������̈ψ����͂��߁A�������̈ψ���w�߂Ă�������Ⴂ�܂��B
�@���̍u�t�͒����V���̋{�c����ł��B�搶�́A�����V���ŗv�E���C���Ă����A���݂͕ҏW�ψ����̕ҏW�ψ������Ă����܂��B�����͂��̂��Z�������Ԃ��Ɋ����Ă��̍u����̂��߂ɗ��Ă��������܂����B������������������ł����A���̑��Ɍ��q�͂Ɋւ��鐢�E�̎�ނ�����A����𒆍��V�������30����ɓn���āA�u���q�͂�₤�v�Ƃ����V���[�Y�ŘA�ڂ���܂����B�����̂��b��������W�ꂽ���̂ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂��A�ڂ��܂Ƃ߂Ė{�ɂ������̂�800�~�ŁA��t�̂Ƃ���ł����߂���������悤�ɂ��Ă������܂��B
�@�Ō�̍u�t�͓c�������搶�ł��B�搶�́A�����w�K�@��w�@�w���ŋ��ڂ������ɂȂ��Ă����܂������A���݂͖��_�����ł����܂��B���{�L��w��̏�C���������Ƃ߂̑��A���{�I���w��̌��������Ƃ��A���{�����w��̌������Ƃ��A�d�E���C���Ă����Ă���܂��B
�@�{���͊e�搶������40���Â̂��u�����܂��B����ł́A�y���搶���炨�肢�v���܂��B
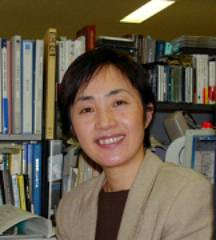 �u���P
�u���P
�P�A
�Ȋw�Z�p�̃��X�N�R�~���j�P�[�V�����̒蒅�Ɍ�����
���C��C3(�V�[�L���[�u)�v���W�F�N�g�̏Љ�
�@�@�@�u�t�F�@�d�͒����������@�@�y���q�q
�@
C3�v���W�F�N�g���{�̔w�i
�E JCO�ՊE���̔�����ɑ�(���C��)�̒����i�Z�������̎��̏����ǂ̒��x�����Ă������A�ǂ̂悤�ȕs��������Ă���̂��A�ǂ�ȉۑ������Ă���̂����ɂ��ėX���A���P�[�g�C�ʖK��C�O���[�v�C���^�r���[�Ȃ�4��ނ̒��������{�j�ɓd�͒��������������͂����̂��A���̊����̂��������ł���
�E 82���̌ʖK�⒲���ł́A���q�͂ɗ����̂���l�����q�͂̃��X�N�ɂ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ӎ��ɕω����Ă����B����C�����O���[�v�C���^�r���[�ł́C���X�N�ɂ��Ęb���Ȃ��A�b���ꂪ�Ȃ��Ƃ����Ƃ����l������
�E �����Ń��X�N�R�~���j�P�[�V�������{�̕K�v�������ʂƂ��đ��ɒ���
�E �����̎���@�ւƂ��Ă̌��q�͈��S�k��ݒu����A�܂������̋����v���ɂ��AJNC�Ƀ��X�N�R�~���j�P�[�V���������ǂ����������A�����ɂ�蓌�C���̒��Ƀ��X�N�R�~���j�P�[�V�����̌`���o����
�E �������Ȃ���A���X�N�ɂ��Ęb����͂Ȃ��Ȃ��o�����A���X�N�ɂ��Ęb����Ƃ������͋C���Ăы��܂��Ă����i�s���⌜�O������ƌ��q�͔��Δh�Ɍ�����Ƃ����ł������j
�E ���̂悤�ȏ̒��ŁA�d�͒����������͌��q�͈��S�ۈ��@�̌��匤���ɁA�Љ�iCommunity�j�Ƃ̑Θb(Communication)�Ƌ���(collaboration)�̂��߂̎Љ����(C3�v���W�F�N�g)�����債�̗p���ꂽ
�E 2002�N12���A���C����C�R�v���W�F�N�g���X�^�[�g����
�A
���X�N�R�~���j�P�[�V�����ɂ���
�E ���X�N�R�~���j�P�[�V�����Ƃ́C���Ƃ̒m����`���邱�ƁA���i���̍l��������Ă��炤���ƁC�����[�ւ�ڎw�������̂ł͂Ȃ�
�E �����Řb�����X�N�R�~���j�P�[�V������1989�N�ɃA�����J�Œ�߂�ꂽ��`����{�Ƃ��A���̂����̃v���Z�X��ʂ��ċ��ɍl���A���ɑ��������Ă������Ƃ�ړI�Ƃ���
�E ���X�N�R�~���j�P�[�V�����Ƃ́C�Θb�E���l�E������ʂ��āA�����I�ȐM���W�����邱�Ƃ��ƍl���Ă���
�B
C3�v���W�F�N�g�̓���
�E ���X�N�R�~���j�P�[�V�����̒����ł͂Ȃ��C���X�N�R�~���j�P�[�V�����̎Љ�I�Ȓ蒅��ڂ������H�I�Ȍ��������ł���
�C
���O�̈ӎ��������瓾��ꂽ�v��̉ۑ�
�E  ���O�̏Z���ӎ������ɂ��C���X�N�R�~���j�P�[�V�����̏��ݒ肵�Ă��A�Ȃ��Ȃ������ɘb���o���Ȃ��ł�����
���O�̏Z���ӎ������ɂ��C���X�N�R�~���j�P�[�V�����̏��ݒ肵�Ă��A�Ȃ��Ȃ������ɘb���o���Ȃ��ł�����
�E ���̗��R�Ƃ��āA��Ԗڂ́u�o���������Ƃ��Ȃ�����o���Ȃ��v�A��Ԗڂ́u���������Ă����傤���Ȃ��v�Ƃ������ߓI���̂ł�����
�E ���̂P/3�����q�͊W�҂Ƃ������Ƃ������Č��q�͂ɂ��Ęb���Ȃ��C�b�������Ȃ��Ƃ������͋C�ɖ߂������
�E ���̂��߁A�Θb���邱�Ƃ��牽�����ς�邱�Ƃ�������K�v��������
�E ������������邽�߂̃��X�N�R�~���j�P�[�V�����̏�Ƃ��āu���C���̊��ƌ��q�͈��S�ɂ��Ē����v��ݒu
�D
�u���C���̊��ƌ��q�͈��S�ɂ��Ē����v�̊���
�@�E�@�u�����v�͎Q���҂̃o�����X�ł͂Ȃ��A�Q���ӗ~���d������
�E �����I�Q���҂ɂ��p���I�ȋc�_�̏�ł���A���炪�������e�����ߍs�������Ƃ���
�E �Q���҂�6���Ŕ����A�ŏI�I��16�����Q�������i�j��14���A�����Q���A60�Έȏオ11���A�����W�̌��q�͈ȊO�̋Z�p�҂������j
�E �����̕p�x��21��̉�����{�����B�����A�Q���҂͑��Ɏ��@����\�͂������ė~�����ƍl�������A�҂��Ă��Ă������i�܂Ȃ��̂ŁA�������������王�@����v���O���������������̊����Ƃ��Đݒ肵��
�E
���@�v���O�����̓���
�@�E�@�v���O�����́A�����̌��w��ł͂Ȃ����̂ɂ��悤�Ƃ̈ӌ��̂��Ƃɍl����ꂽ
�E �u�����v�����o�[�����@�ꏊ����@�̌���ɍŏ�����ւ����(�j�R���T�C�N���@�\�A���{���d�E���C���d���E�p�~�[�u�A���{���d�E���C��d���A��錧�E���q�͑����h�ЌP��)
�E �������߂Đ��������̂ł͈ӌ����o�Ȃ��Ƃ̗��R����A���O�ɖ�2���Ԃ̐��������Ǝґ������
�E ���w���ɂ��������邪�A���w��Ɏ��Ǝ҂Ɩ�2���Ԃ̋c�_�̎��Ԃ�݂��c�_����
�E ���@�̊��z������|�[�g�ɂ܂Ƃߎ��Ǝ҂ɒ�o����
�E ���|�[�g��o��A���Ǝ҂ƍēx�c�_���鎞�Ԃ�������
�F
�Q���҂ւ̃A���P�[�g����
�E �����������\�z�����ȏ�Ɏ��Ǝ҂͑Ή����Ă��ꂽ�Ƃ̈ӌ�����������
�E �g�D�������Ɏ�Ԏ���ďZ���ӌ��ւ̃��X�|���X���x���ƁC���������̃R�~���j�P�[�V�����w�͂��]�����Ⴍ�Ȃ�
�E �Ή��҂����܂�M�S�ɐ�������ƁA�Q���҂̐������Ƃ����낻���ɂȂ�A�Q���҂͐����҂ɑ��A�p�[�g�i�[�V�b�v�Ɍ�����ƍl����
�G
�Ή��҂ւ̃A���P�[�g����
�@�E�@������ǂ������Ă��炦��
�E ���̊����͈�ʏZ���̍l���𗝉������ł��L��
�E �V�������_�ł̈ӌ������炦��
�H
�Z��(�Q����)�Ǝ��Ǝ�(�Ή���)�͂Ƃ̈��S�Ɋւ���l�����̑���
�E �{�݂͎g�p�ړI�ɉ��������S�Ǘ����Ȃ���Ă��邪�A���̘_���͎Q���҂ɗ�������ɂ����A�Q���҂͈�̑g�D�̒��ň��S�Ǘ��̊�����ꂳ��Ă��Ȃ��̂͂��������Ǝv�����B�����ē��ꂳ��Ȃ����R�ɂ͑g�D�̕ǂ�����ƍl����
�E �Ή��҂͈��S�m�ۂɓ�����A���ː����S���d�_�I�ɐ����������A�Q���҂͕��ː����S�����ł͂Ȃ��A�J���ЊQ���܂߂Ď��Ə��S�̂̈��S���S�z���A�E�������S�łȂ���ΏZ��������͂��͂Ȃ��ƍl����
�E �Ή��҂͐E�����\���ȌP�����Ă��邱�Ƃ�O��ɐ����������A�Q���҂͖�����̂��Ƃ�S�z���A�s����ȐE���ɂł����S�ɑ���o���邱�Ƃ����߂�
�E �Ή��҂͖@����K��������Ă��邱�Ƃ����S�̍����ɐ����������A�Q���҂̓��[�������Έ��S�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���������̈��S����邽�߂ɁA���炪�l�������ǂ������d�v�ƍl����
�E
�I
�Q���҂̊��z
�E �m����������
�E �Z���̊����Ɏ��M�����Ă�悤�ɂȂ���
�E ���q�͂ɊS�����Ă�悤�ɂȂ���
�J
�{�����ɎQ�����ĂȂ��Z���̈ӌ�
�E �{�����ɎQ�����ĂȂ����A���@�v���O������m���Ă���l�ɑ��Ĉӌ������Ƃ���A�m�����Ȃ��l�����@���Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ����ӌ��͏��Ȃ��i�R�p�[�Z���g�j���Ǝ҂ɏZ���̎��_���ӎ�������_�ŁA�Ӗ�������Ɠ������l�����������i��60�p�[�Z���g�j
�K
���Ǝ��Ə��Ƃ̊W�̍l�����̕ω�
�E 14�N�x�́A���Ǝ��Ə��̊W���ς���Ă����ׂ��Ƃ̈ӌ��͖�30�p�[�Z���g�ł���A���̂����u���ł��b��������W������ׂ��v�Ƃ̈ӌ��͉ߔ������Ă����A16�N�x�ɂȂ�ƁA�P�ɘb��������W�����ł͂Ȃ��A�����Ӗ��łْ̋��W�����ׂ��Ƃ̈ӌ��������Ă���
�L
���ꂩ��̓��C��
�E �قڑS���������̌p������]
�E �{�����͑��Ǝ��Ə��Ɠ��������������A�����ْ������������S���g�D��NPO�@�lHSE���X�N�E�V�[�L���[�u�̓��C���x���Ƃ��ĐV���ɏo������
�i9��29���ɓ��t�{���NPO�@�l�Ƃ��ĔF���ꂽ�B�j

�u���Q
�����V�����ʊ��|���q�͂�₤�|��ނƔ���
�@�@�@�u�t�F�@�����V���@�@�{�c�r��
�}�X�R�~�Ƃ������ꂩ��݂��R�~���j�P�[�V�����Ƃ������Ƃł��b������B�V���L�҂͂܂������C���^�[�v���^�[�̖����ʂ����Ă���B�����ׂ��炴�鑶�݂��Ǝv���Ă���B���̗��ꂩ�猩�����q�͂Ƃ͉����ɂ��Ęb�������B
�@�����V�����u���q�͂�₤�v�Ƃ����`�ʼnߋ��Q�N�ԁA���T�P�y�[�W�Â��E�A�A�����J�A���[���b�p�A�A�W�A�A�����ē��{�ɂ��ĘA�ڂ��Ă������A���̎�ނ̔w�i�A�ߒ��A�����ɂ��Ęb���A�܂��A�Ō�ɂ��̊���ʂ��A�V�����猩�����q�͂͂ǂ������邩���b�������B
�@
�@�܂��A��ނ̔w�i�Ƃ��Ē����V���̗���ɂ��Đ�������B�����V���͍L���̕��a�����̂��������ɂ���B��������͍��̎O�z�̂���ꏊ�ɂ���A��100�l���S���Ȃ�A�����̗B��̎ʐ^����ނ������j������B���̂悤�ȗ��ꂩ��A��������ƕ���Ő��E�̊j���̕����[�h���Ă��āA���{�V������܂ȂǑ�����܂��Ă���B���V���������Ƃ��̎�̊��܂��ł�������܂��Ă���B
�������A������ƌ����ĕK�������L�������q�͂ɔ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���a30�N�����a�����Ō��q�͂̔�����J����A���j�c�̂̐l�������������Č��q�͂͑f���炵���ƌ����āA������������ȂǁA�L�������q�͂̕��a���p�Ɋւ��ė��������������j������B�����V���Ƃ��Ă͌��q�͂̕��a���p�ɂ͒����̗�����Ƃ��Ă��Ă���B
���50�N�̐ߖڂƂ������ƂŌ��q�͖��ɎЂƂ��č���ǂ����g�ނ����l���Ă���2000�N���A�h�C�c�������p�~�����肵���j���[�X���傫����������A�t�B�������h��5���@��V�݂���Ƃ̕�����A���E�̌��q�͏�͈�̂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���A�Ƃ������ƂɂȂ�A����͍s���Č��邵���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ����B
����A�����ł͂���̃i�g���E���R��̖��A�����d�͏�ւ̗��n���Ŕ��E�^���̑Η�����s�����Ă���Ƃ������A�����ē���3���@�̗��n���Ƃ���3�̖�肪����A���ꂩ���ǂ��Ȃ邾�낤���A���E���猩�����{�͂ǂ������邾�낤���Ƃ������_���������B
���Ɏ�ނ̌o�܂ɂ��Ă��b������B���x�A�j���[���[�N�x�ǂ���������Ƃ������ĊC�O��ނ̌�������r�I����ł���A�����I�Ȗ��̓N���A���ꂽ�B�������A��J�����͎̂�ސ�ւ̎�Â邪�������Ƃł������B�����ŁA�����d�͂̋{�莁�A�����̓��ƌ��q�͈ψ����A�L���s�̕������s���A���Y�̑�Ԏ��Ȃǂɋ��n���̂����b�ɂȂ����B���Ɛ搶�͈ꎞ�A���ɂ���ꂽ�Ƃ������ƂŁA���q�͂̌��_�ł���A�L���E�����Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��������v����������Ă������Ƃ�����A�����o�b�N�A�b�v�����B���q�͂̎�ސ�ɂ͗l�X�Ȑ���������A��ʎ҂ɂƂ��Ď�ނ͌����ĊȒP�ł͂Ȃ������B�݉��͖݉��Ƃ������ƂŁA���̂悤�Ȑ��Ƃ̋��n���������A�Ŏ�ނ����������ꏊ�����������B����ł�����Ă��炦�Ȃ������ꏊ������B�X���[�}�C���A�C�����h�̓G�N�Z�����̃g�b�v�̎�ދ��Ă����̂Ɍ��n�ł͌x���S�������ɓ���Ă���Ȃ��������A�C�����̓E�B�[���̑�g�����d�b�ɂ��o�Ă���Ȃ������B�������A�v���9�����͎�ނł����B
������ނł��e����̂��߂̋K���Ȃǂɂ���ނ����炢�ʂ����������A���̊����z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��邽�߂��A�s����X�ŋL�������Ă����A�Ɛ����|���Ă��������A���͓I�ȑΉ��������A�ŏ����Ɏ�ނł����B���̏����ĉ��߂Ċ��Ӑ\���グ�����B����2�N�|����20���������Ă����B
���Ɏ�ނ̌��ʂɂ��Ă��b������B����̎�ނň�Ԍ��O���Ă����͍̂L���̔���҂̕��X�����̋L���ɂǂ���������邩�������B���q�͂��m�肷��A�ڂł͂Ȃ����A�Ɣᔻ�I���������������Ƃ��\�����Ă����B�������A���ʓI�ɂ͔ᔻ�̓d�b�Ⓤ����1�{�����������̂��ӊO�ł������B�����\���ے��I�ȗႪ�������B��ւ̔��Δh�̕�����A���ɏ���L�x�ɐ��荞��ł���L�v�������A���i���̕��ɂ�����ǂ�ŗ~�����Ƃ̃��[�������B��������ƃ}�X�R�~�͂ǂ��炩�̗���̈ӌ��������t����������Ȃ肪���Ȓ��ŁA���Δh�̕��ɒ����I�ŁA���Ƃ��ĉ��l������ƔF�߂�ꂽ���Ƃ͊����������B���q�͂̕��a���p�𐄐i����ꍇ�̉ۑ�A��߂�ꍇ�̉ۑ�𒆗��I�ɕ`�������Ƃ��]�����ꂽ�̂��Ǝv�����A���̂悤�ɒ����I�ȗ��ꂩ��̕����Ȃ��̂������Ȃ����Ǝv���B
 �t�ɍ��N�A���q�͊w��܂���܂������A���i���Ƃ��������q�͂Ɍg����Ă�����X������]�����Ă��炦�����Ƃ��L�������B�{���̍u����������_�@�Ƃ������̂��Ǝv��������̌��c���u���˗����铙�A�u���̋@������Ă���B���E�̌��q�͂��T�ς�����ʂ̐l�ł��ǂ߂�{�����ɏ��Ȃ��̂ŕ]�����ꂽ�̂��Ǝv���B��剻�����̖{��ʂ̍��ɂ��ď��������̂͑������A���E�̌��q�͂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ������Ƃɂ��Ĉ�ʎ҂��ǂ߂���̂͂قƂ�ǂȂ������A����������{�I�Ȃ��̂��ӊO�ɔ����Ă���Ƃ������Ƃ���Ƃ̊F����ɂ��l���Ē��������B
�t�ɍ��N�A���q�͊w��܂���܂������A���i���Ƃ��������q�͂Ɍg����Ă�����X������]�����Ă��炦�����Ƃ��L�������B�{���̍u����������_�@�Ƃ������̂��Ǝv��������̌��c���u���˗����铙�A�u���̋@������Ă���B���E�̌��q�͂��T�ς�����ʂ̐l�ł��ǂ߂�{�����ɏ��Ȃ��̂ŕ]�����ꂽ�̂��Ǝv���B��剻�����̖{��ʂ̍��ɂ��ď��������̂͑������A���E�̌��q�͂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ������Ƃɂ��Ĉ�ʎ҂��ǂ߂���̂͂قƂ�ǂȂ������A����������{�I�Ȃ��̂��ӊO�ɔ����Ă���Ƃ������Ƃ���Ƃ̊F����ɂ��l���Ē��������B
�I���ɑウ�u���������q�́A����nj��q�́v�ɂ��Ă��b�������B�ߋ��̌��q�͕͂ǂ��ł��������A�ɂ��Ă̎��̊��z�ł���B�������Y������w�E����Ă���Ƃ���A�ߋ��̌��q�͕����茩�ł���������ł���͎̂c�O�Ȃ��玖�����Ǝv���B
�L�҂�1�`2�N�̃y�[�X�ŕp�ɂɒS�����ς��̂Ō��q�͂ɂ��Ċm�ł���L���������̂���ϓ���Ƃ����̂����̗��R�ł���B���q�͖��Ƃ����̂͒n���肩�獑��܂ŁA���͖����`��₤�Ă���Ǝv���B�����܂ł̖���s��ł���̂ł���B���n���ɂ͎l�����I�̗��j������Ƃ������ƂŁA�c��������ςȍL���肪����B���̂悤�Ȗ��ɂ��Đ��Ƃ̊F���猩�Ċm�ł���L���������Ƃ����Ă�1�`2�N�̌o���̋L�҂ɂ͖����Ȃ̂ł���B����ł��e�ЁA���̏ꂻ�̏�ɉ����ėǂ������ėՂ�ł���B�����͋��ݎ���Ă��炢�����B���̂悤��3�N��������Εʂ����A�u�����͒m��Ȃ��v�Ƃ��u���q�͂ɂ��ė������Ȃ��v�Ƃ��悭�����邪�A����͓�����O�Ȃ̂ł���B10�N20�N����Ă�������Ƃ�������1�`2�N��������Ă��Ȃ��L�҂ɂ��������͍̂����Ǝv���B���̕ӂ�����Ă������������B
������A�ӊO�Ȃ��ƂɋL�҂ɂ͉�Ђ���ǂ�ȋL���������Ƃ��������͂Ȃ��B�L�҂��������L����P����Ƃ��A��߂�����Ƃ������Ƃ��L�蓾�Ȃ��B���������Ӗ��ł͋L�҂͂��Ȃ莩���̎��R�ӎu�ŋL����������B�X�^���X�����m�ȑ��̐V���ł��A�ォ�炱�������L���������A�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�X�̋L�҂������̎Ђ����炱���������ɏ����������ǂ��낤�ȂƂ����l�̎v�����݂ŏ����Ă���̂��Ǝv���B�ォ�狭������Ă���̂ł͂Ȃ��A�����܂Ŏ���I�Ȕ��f�A���r�ɂ���ċL���������悤�ɂł��ς�蓾��Ƃ����������߂ċ������Ă��������B
�ǂ��}�X�R�~�ɑ��āA���q�͔��d���̂�����Ƃ������̂ł��L���ɂȂ�A�ƌ����邱�Ƃ����邪�A�ǂ܂����̗���ł͂����v���邩���m��Ȃ����A�����ق��̗���ł́A�ǂ��ł��ǂ����Ƃ͌����ď����Ȃ��B������Ƃ������ƂɎv���Ă��A�厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv������L���ɂ��Ă���B�X�̋L���ɗ]��_�o���点���ɍl���ė~�����B�L�����ڂ�������q�͂ւ̘_�c���[�܂��ėǂ����Ƃ��Ǝv���B������Ȃ��Ȃ�������낵���A������Ă���ق������S���Ǝv���B
�Ō�ɐ��m�ȏ����܂��s�����Ă���Ƃ������Ƃ�\���グ�����B�X�C�X�����q�͔p�~���������[�Ŕی��������ƂȂǁA�������蕽�a���p�ւ̎�g�݂�����Ă���̂ɁA�t�̃C���[�W�������Ă���l�������Ǝv���B�܂��A�ςȕɂ͂��������A�Ƃ�����ƌ����ׂ��ł���B�����肾����d���Ȃ��A�ƕ��u���邱�Ƃ͊ԈႢ�ł���B���X�A�Ǝv�킸�ɌJ��Ԃ��w�E���ė~�����B
���m�ȏ��͌J��Ԃ��`���ė~�����B�\���ȏ�����ɐ��m�ɓ`����Ă���̂��A�r���^��ł���B����̓}�X�R�~�̕��s���Ȃ̂����m��Ȃ����A���Ƃ̊F����ɂ��l���Ē��������B���ꂩ��v�X�_�c��[�߂Ȃ�������Ȃ��̒��łǂꂾ�����m�ŏ\���ȏ�����ɓ`����Ă���̂������߂Č����Ē��������B
 �u���R
�u���R
���q�̓p�u���b�N�E�R�~���j�P�[�V�����̗v���i���Ȃ߁j
�@�@�@�u�t�F�w�K�@��w���_�����@�c������
�i�����z�z���ꂽ�������������������ł��܂��j
�ݓc���V�����u�g�C�������}���V�����v�Ƃ���������ӂ��n���Ĉȗ��A�����Ƌc�_��������������ɂ�������炸�A�܂������@����A�g�D���ł��Ă���A�葱�������܂��Ă���ɂ�������炸�A�ˑR�Ƃ�����s�����]��͂����肵�Ă��Ȃ����Ƃ��āA�u�����x�����ː��p���������v����肪����܂��B
����1976�N9���P���ɁA���q�͈ψ����́u�����x�����ː��p�����̒����Ǘ��V�X�e���v�Ɋւ���ψ���̈ψ��Ɏw������܂����B����͎������q�͊W�̐��{�ψ�����ψ��Ƃ��đI�C���ꂽ�ŏ��̈ψ���ł����B���̌�A����1985�N����2001�N�܂Ō��q�͈ψ���ƌ��q�͈��S����̐������߁A���̊ԂɂQ������q���u���v�v�̍���Ɋւ�܂����B�Ō�Ɏ��́A���q�͈ψ���u�o�b�N�G���h����啔��v�ψ��Ɓu�����x�����ː��p�����������k��v�ψ��߂܂����B
���͂����m�̂Ƃ���A�����w�ƃR�~���j�P�[�V��������Ƃ����Љ��Ȋw���ł��B�����w�ƃR�~���j�P�[�V�����̎��_����݂āA����Ɏl�����I�������āA���܂��ɂ��̐��ʂ��s�����ł���̂́A����̃v���Z�X���̂ɂȂɂ���肪���邩�A���邢�͐���̎�̎��̂ɂȂɂ���肪���邩�A�̂ǂ��炩�ɖ�肪�i����悤�Ɏv���܂��B�@�����ō����́A�ȉ��A�S�̖����N���Ă݂悤�Ǝv�������B
�悸��P�ɁA���ݓ��{�ł́u�����x�����ː��p����������v�I�肪���ȍ���ɒ��ʂ��Ă��܂��B���̌���������ƒ��߂Ă݂����Ǝv���܂��B��Q�ɁA�uNIMBY�v�nj�Q�Ƃ�����Љ�S���I�Ȍ��ۂ�����܂��B���́uNIMBY�v�nj�Q���u�����x�����ː��p����������v�I��ɂǂ�Ȍ��ʂ��y�ڂ����߂Ă݂܂��傤�B�uNIMBY�v�nj�Q�̕ǂ��Ȃ�Ƃ����ĉz���Ȃ��ƁA�u�����x�����ː��p����������v�I����������ɐi�܂Ȃ��̂ł��B��R�ɁA���Ăł́A�u�����x�����ː��p���������v�Ɋւ���ߋ��̐���̌���^�ʖڂɁA�܂����ʂ���~�߁A�ߋ��̎��s����w�сA�V���ȍs�����������グ��Ƃ��������������ɂȂ��Ă��܂��BIAEA���u�����x�����ː��p�����Ǘ��̎Љ�I���ʂɊւ���R���T���^���g��c�v�ł́A�ߋ��̎��s�̌o���Ɋ�Â��āA���܂��܂ȗ��Q�W�ҁi�X�e�[�N�z�[���_�[�Y�j��ɂ����u�����x�����ː��p����������v�̌��̕K�v�����Ƃ��ĂT�̌��������グ�A����N���s���Ă��܂��B���̋@��ɁA�����T�̌������Љ�����Ǝv���܂��B��S�ɁA�u���q�͍L��v�̖�肪����܂��B����܂ŁA���q�͂ɑ���u�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�邽�߂ɁA���{�ł́u�L���v��u���������v�������ɍs���Ă��܂����B�������A����ɂ��A���Ă̌��q�͍��̂قƂ�ǂɂ����āA�u�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�A�u�L��v�A�u�����v�ȂǂƂ������t���̂���������p��Ă��܂��āA�قƂ�ǎg���Ă��܂���B����ɂ́u����̗���v�Ɓu���l�ς̕ω��v���e�����Ă��܂��B�Â��T�O�ɂ��܂ł����t����Ă����玞��x��ɂȂ�܂��B����ł́A���ď����Łu�L��v��u�����v�ɑ����Ďg���Ă��錾�t�i�T�O�j�͂Ȃɂ��Ƃ����܂��ƁA�u�p�u���b�N�E�C���t�H�[���[�V�����v���邢�́u�p�u���b�N�E�A�E�g���[�`�v�ł��B�܂��A�u�p�u���b�N�E�R�~���j�P�[�V�����v���p�ɂɎg���܂��B����ł́A�u�L��v��u�����v�ƁA�����̐V�������t�̂ǂ������e�I�ɈႤ�̂ł��傤���B���������ŋ߂̓������ANRC (�A�����J���q�͋K���ψ���)�́u���b�J�}�E���e���v�v�悩�琶�܂ꂽ�u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����E�K�C�h���C���v����E���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�u�����x�����ː��p����������v�I��͉������Ȃ̂��H
�����́A�����x���p���������������ł͂Ȃ����A���邢�͂���܂ł��܂��������������S�̂Ȃ�������������������Ǝv���܂��̂ŁA��łȂɂ��̂����ɗ����Ǝv���āA����������������p�������Ă��������܂����B
�ŏ��ɁA�����x�����ː��p���������̌o�܂������ȒP�ɂȂ����Ă݂܂��傤�B������ѓ��R���ƒc�i�����j�́A�P�X�W�O�N��̖�����X�O�N��ɂ����āA�����x���p����������\�z���̈��S������ђn�w�����̈��S���𒆐S�Ɍ����J����i�߁A����ƕ��s���āu�o�b�N�G���h�v����̍�������݂Ă��܂����B���̌��ʁA2000�N�ɂ́A�@���i�u������ː��p�����̍ŏI�����Ɋւ���@���v�j�����肳��܂����B���̖@���ɂ���āA�u�����x�����ː��p���������v�̎�́A�����n�I��̎菇������A�����̕��@�A�����̍����Ȃ������x������܂����B���̖@����ς��Ȃ�����A��X�͂��͂��߂�ł��܂���B��ɐi�ނ����Ȃ���Ԃɂ���킯�ł��B
���̖@���̒��g���܂߂āA����̓��{���u�����x�����ː��p���������v�Ɋւ���l�����͔��ɖ���I�ł���ƁA�O�����獂���]�����Ă��܂��B���R���ƒc�i�����j�͊O���̐��Ƃ����Ɂu�s�A���r���[�v�i�����]���j���˗����A�����ł��̌��ʂ̕���J���܂����B���̕�ł́A�t�����X�A�A�����J�A�C�M���X�Ȃǂ̃��r���[���[����A�n���w��H�w�̑��ʂ���̃v���X�̕]���ɉ����āA���̖@���̒��g�ɏ����J��n�������̂̎̈ӌ��d���ׂ��Ƃ������Ƃ��������܂�Ă��邱�Ƃ���A���{�̖@������ѓ��{���{�̖����`�I�ȃX�^���X�ɑ��Ă��J�ߌ��t�Ղ��܂����B
�������Ȃ���A�����͂Ȃ��Ȃ�������肭�͂����Ă��Ȃ��̂�����ł��B�Ⴆ�A�u�����x�����ː��p���������n�v�̐��ݓI���ƍl�������n�������̂ł́A�u���ː������p�����������֎~�v�������ĂȂ���Ă��܂��B�u�������ݔ��v�ɂ͈ȉ��̂R�̈�����p�^�[��������܂��B��P�̃p�^�[���́u���ɂ�锽�v�ɂ����̂ŁA����ɓ��锽�͂P��10�s��������܂��B��2�̃p�^�[���́u�c��̔��Ό��c�v�ɂ����̂ŁA����ɓ��锽�͂V�s��������܂��B���ŋ߂ł́A��3�̃p�^�[���Ƃ��ă}�X�R�~�i���ɒn�����ɂ����j�����������ƂȂ��Č����f�O���鎩���̂������Ă���܂��B�����m�̂悤�Ɍ��q�͔��d�������@�\�i�����Č��@�\�j���u�����x�����ː��p����������v�̐��ݓI���n�̌����̂ɂȂ��Ă���܂��B����@�\��͌���̎�������������̂ɐ����̂��߂ɃX�^�b�t��h������ق��A�u�����x�����ː��p���������v�Ɋւ���p���t���b�g������Ď����̂Ȃǂɔz�z���Ă��܂��B�������A�����̂�����ɊS�������ƁA���̂��Ƃ�n����������B�n����������ƁA�n���̔_���A�����A�Z�������łȂ��A�אڎs�����̔_���A�����A�Z�����ꏏ�ɂȂ��Ĕ�������オ��B���������u���@�\�v�̐������Ă݂悤�Ƃ����Ƃ���܂ł����Ă��A�������O�ɔ�������オ���Ă��܂��A���ǁu�����P��v���������Ă��܂��Ƃ������Ⴊ�A����܂łɂS�Ⴀ��܂��B
���̒��q�ōs���܂��ƁA����ɉ����Ă�����n�������̂��łĂ��Ȃ��Ȃ鋰��������܂��B����n�����̐V���L�҂���ނɂ��ƂÂ��ď������L���̒��ŁA���̂������������P��Ƃ������Ƃ��N�����Ă��܂����̂��Ƃ��������ɐG��A����ɐϋɓI�Ȑ��i�h���S�������̂́u�����x�����ː��p�����v�́u�����v�ł͂Ȃ��A�u�����x�����ː��p�����v�����Ƃ��u�����i���ˁj�v�ł���Ɣ�������߂ĕ��͂��Ă��܂��B
�m���ɑ�ςȂ��������������킯�ł��B�����n���ɂȂ�Q���~�ȏ�́u������v�����܂����A����Ƀ{�[�����O�Ȃǂ̊T�v�������n�܂�ƂQ�O���~�����܂��B�������n���ɋُk�����𔗂��Ă��邽�߁A���݁A�ǂ��̒n�������̂ł������͑�ςɋꂵ���B������A���ȁu�j�̂��݁v�ł��u�����i���ˁj�v�ɂȂ���̂Ȃ�Ή��ł����������Ă��āA���Ȃ��Ă�2���A���܂�������20���������Ă���ƐԎ�����������B�����Ȃ�A��҂̗����ɂ����~�߂������邾�낤���A�V���b�^�[���~����ςȂ��̘V�܊X�ɂ������炩���C���߂��Ă���̂ł͂Ȃ����B����ɂ��A�ǂ��̒n�������̂�������̍����ɔߒɂȎv���ŗ����������Ă��܂��B���̈�Ƃ��āA�u�����x�����ː��p����������v���ݓI���n�Ƃ��Ď�������悤�Ƃ���̂ł����A���ꂪ���Ƃ��Ƃ��}�X�R�~�̕ŁA�����P���Ƃ����������Ă���킯�ł��B���ꂪ�ʏ�̃p�^�[���ɂȂ��Ă���ƁA�܂��܂��V���Ɏ���グ��n�������̂͏��Ȃ��Ȃ��Ă���B���̌��甲���o�����߂ɂ́A����̕��͂ƁA���̌��ʂɊ�Â��V�������@�_�̊J�����K�v�ƂȂ�܂��B
�킪���ɂ�����ߋ������q�͐���̃T�N�Z�X�X�g�[���[�����������݂܂��ƁA�u�����i���ˁj�v�������̒��S�I�U���ł��������Ƃ���j�I�����Ƃ��ĔF����������܂����B�u�d���O�@��t���v�A�u���ƌ��v�A�u�S�z���v�Ƃ��ēd�͉�Ђ������Ɏx�����Ă���u�n�拦�͋��v�Ȃǂ��A����܂ň���ł͌��q�͎{�ݎ�e�̋��͂ȗU���ƂȂ�A�����ł͒n�������̂ƒn��Z���������Ă����͎̂����ł��B�������q�͂ɂ��ĉ�����n��Љ�ɗ��ގ��ɂ́A���ꂪ�u�����i���ˁj�ɂȂ�b�v�Ƃ������Ƃ��蒅���Ă��܂��B�������A�ŋ߂̗�����Ă݂܂��ƁA�����i���ˁj������Ɩ��͂������Ă��Ă���悤�ȌX�����F�߂��܂��B����́u�����x�����ː��p����������v���ݓI���n�̗�ł�������悤�ɁA�����炭�͈��S�̒Njy�̂��߂ɁA���Y�����̂��n��Z�����A�܂��אڎ����̂��n��Z�����A�ڂ̑O�̂Q���~���S�O���邱�ƂȂ��R����Ă��܂����̂ł��B�����ł����́A�u�Љ�I���l�ς̑��ΓI�ω��v�Ƃ������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�܂���B�u�����i���ˁj�v���������Ƒ厖�Ȃ��̂��������Ƃ��A�l�тƂ͂��́u�����Ƒ厖�Ȃ��́v��I��ŁA�u�����i���ˁj�v��I�Ȃ��Ȃ�܂��B���Ă��܂��܂ȁu���Q�v�����ɂȂ����Ƃ��A�u�A���j�e�B�v�i�����̉��K���j�Ƃ������t���͂��܂����B���܂ł͂�葽���̐l�тƂ��u�A���j�e�B�v�\�\����̓I�ɂ����u���S�v�ŁA�u���N�v�ŁA�u���S�ł���v�悤�ȁu���K�v�Ȑ����\�\�����߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�u�����i���ˁj�v��荂�����l�̂�����̂�����A�l�тƂ�������̂ق���I������Ƃ������Ƃ͏������s�v�c�ł͂���܂���B���{���܂��n�������́u�����i���ˁj�v�����\�ł����B�͂����āA���܂ł������ł��傤���B�̂���g���Ă��������������܂ł��g�������Ă��邱�Ƃ����s�łȂ����Ƃ��A����ꎩ�g�����ȕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
 �Ȃ��uNIMBY�v�nj�Q���N����̂��H
�Ȃ��uNIMBY�v�nj�Q���N����̂��H
�uNIMBY�v�iNot In My Back Yard�j�nj�Q�͎Љ�S���I�Ȍ��ۂŁA�ꌾ�ł����Ȃ�u�s���ȓy�n�J�����s�Ȃ��邱�Ƃɑ��Ĕ�����l�тƁv���Ӗ����܂��B���������ڂ�����`����ƁA�u�Y�����A���ݏ�����A���Ŋ��ҍX���{�݂Ƃ����悤�ȁA�n��Љ�S�̂ł͕K�v�����A�i�Ϗ�悭�Ȃ��A�댯�A���邢�͎����̎����Ă���s���Y�̎��Y���l��������悤�Ȃ�����̂�������{�݂������̉Ƃ̗���A���邢�͎����̒��ɂ��邱�Ƃɔ�����l�тƁA���邢�́A�����邱�Ɓv�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��Ɂu�����x�����ː��p����������v�͂����������̂̂ЂƂł���A���̂悤�ɍl�����Ă��d�����Ȃ��ł��ˁB�Ȃ��Ȃ�A�������������N�Ƃ����Ă�����ː��p������n���ɖ��߂Ă����Ĉ��S�Ȃ̂��ǂ������A�����I�A���o�I�ɔ��f����\�͂��A�����͎����Ă��Ȃ�����ł��B�ł�����A�t�@�E�X�g���m�̌��t�����A�u�����ƈ��������ɁA�����ɍ���v���Ƃ��S���I�ɒ�R����l�тƂ��������Ă��s�v�c�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B
�uNIMBY�v�nj�Q�͌��q�͊֘A�{�݂ɑ��������N����킯�ł͂���܂���B�u���͔��d�v�́u�\�t�g�E�G�l���M�[�v�̎�͂Ƃ��č����]������Ă��܂����A�u���͔��d�v�ɑ��Ă��uNIMBY�v�nj�Q�͋N���Ă��܂��B�f���}�[�N�̎Љ�w�҂��u���͔��d�v�ɑ���uNIMBY�v�nj�Q�͂��āA��P�ɑ����A��Q�Ɍi�ςւ̃_���[�W�A��R�ɐݒu��(�n�������̂ƋƎ�)�ƒn��Z���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̌��@���琶����s����{����uNIMBY�v�nj�Q�����̕K�v�����Ƃ��ċ����Ă��܂��B�����f���}�[�N�ŁA���͔��d�̃t�@�[���ł͉��\������͔��d�@�̃|�[���������A�C��������ɂԂ����Đؒf����A���̎��[���C�m�����ɂȂ���Ƃ����ᔻ���o�Ă��Ă���Ƃ������Ƃ����n�̐l���畷�������Ƃ�����܂��B�u�\�t�g�E�G�l���M�[�v�̎�͂Ƃ��ĕ]���̂悢�u���͔��d�v�ł���uNIMBY�v�nj�Q���N�����̂ł�����A�����ł��������҂́u�����x�����ː��p����������v�ɑ��āA��苭���uNIMBY�v�nj�Q�̔����������Ă��s�v�c�ł͂���܂���B
�ߋ��̋��P����w��IAEA�\�\����5�̌���
���[���b�p�����q�����́A����܂Łu�����x�����ː��p����������v����낤�Ƃ��Ď��s���J��Ԃ������܂��B�m���Ƀt�B�������h�͐�����̂ЂƂƂ��Č����Ă��܂�����ǂ��A�ق��̍��ł͌����Ȑ�����͂���܂���B�X�E�F�[�f���ł��v�������͒����ɐi��ł͂��邯��ǂ��A������Ƃ����邩�ǂ����̓N�G�b�V�����E�}�[�N�ł���܂��B
�ŋ�(2002�N5��)�E�B�[���ŊJ���ꂽIAEA�́u�����x�����ː��p�����Ǘ��̎Љ�I���ʂɊւ���R���T���^���g��c�v�ł́A�ߋ��̎��s�̌o���Ɋ�Â��āA���܂��܂ȗ��Q�W�҂�ɂ����u�����x�����ː��p����������v�̌��Ɋ֘A���āA���̂悤�ɂT�̌��������グ�A����N���s���Ă��܂��B
�i1�j�u�J�����v�iOpennes�j
IAEA �́u�����x�����ː��p����������v��ݒu����Ƃ����悤�ȐV������Ă������Ȃ��ۂɂ́A���́u�J�����v�����ɑ厖���Ƃ��Ă��܂��B�u�J�����v�͓��{�ł́u���J���v�Ƃ��u�����J�v�ɂقړ������Ӗ��������t�i�T�O�j�ł����A���m�ɂ����Ƃ��Ȃ�ܒ~���Ⴂ�܂��B�u�J�����v�ɂ́A�R�~���j�P�[�V�����̑���肩�痘�Q�W�ҁi�X�e�[�N�z���_�[�Y�j�ɑ��ĐϋɓI�Ƀ��b�Z�[�W�M����Ƃ������ƂƁA���Q�W�҂̌��������悭�����Ƃ����A�o�����I�R�~���j�P�[�V�����i���Ȃ킿�A�Θb�j�̈Ӗ����܂܂�Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���{��́u���J���v��u�����J�v�ɂ́A�u�������ꂽ�Ƃ��ɐ����҂ɑ��ď������Ƃ����A���ɓI����1�����I�ȃR�~���j�P�[�V�����v�̈Ӗ���������܂���B�u�J�����v�̖��̂��Ƃ�IAEA���ϋɓI�ȑo�����I�ȃR�~���j�P�[�V�����i�Θb�j��]�܂����ƍl���A�܂��܂��͂����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A���{�ɂƂ��Ă��d�v�ȃR�~���j�P�[�V�����헪�̓]���̕K�v���������܂��B
(2�j�������iTransparency�j
���{�ł����́u�������v�Ƃ������Ƃ��]���܂����A���{��ł����u�������v�Ɖ��Ăł����utransparency�v�ł͈Ӗ������Ȃ�Ⴂ�܂��B�A�����J�ł����[���b�p�ł�IAEA�ł��A�u�������v�Ƃ͂����u�������蒮�����肷�邱�Ƃ��ł��邱�Ɓv�ł͂Ȃ��A�u���Q�W�҂����������̌��O����ǂ̂悤�ɐ���҂⎖�Ǝ҂ɂ���Ĉ����Ă��邩������m��\�́v�ƒ�`����Ă��܂��B�܂�A�u�������v�́u�m�錠���v�ƂƂ��ɗ��Q�W�ґ��̔\�͂̈ꕔ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ƃ͂����Ă��A���������\�͂��t���ɔ����ł��邩�ǂ����́A����҂⎖�Ǝ҂��͂ސ������ɍ��E����邱�ƂɂȂ�܂��B���̊Ԃ������a�̂�����̂���A�����J�Y�����̗A���ĊJ�̌��ɂ��āA�����J���Ȃ̃X�|�[�N�X�}�����e���r�E�C���^�[�r���[�ŋL�҂̎���ɓ����āu�F��ȐR�c��̍��ӂ��K�v�ł���A����ɂǂ������邩�͖����Ƃ��Ă͌y���Ɍ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɠ����Ă��܂����B�u�����v�����u������v�����u�������v��50�p�[�Z���g�ȉ��ł��ˁBIAEA�́u���������������̌��@�����s�̌��v�Ƃ����Ă���킯�ł��B
�i3�j�u�����Ή��\�́v�iResponsiveness�j
�������y���搶������ꂽ���Ƃł����A�ً}���̍����ɂ�������炸�A�Ή��Ɉ�N�����������Ă��܂��̂ł́A���Ȃ��̂Ɠ����ł���܂��B�u���̂ł�������o���邾��������������v�Ƃ����̂��A�����ł����u�����Ή��\�́v�ł��B���Q�W�҂̌��O�A�s���A�^�f�ɑ��Ē��ق𑱂��邱�Ƃ́A�Ȃɂ��B���ꂽ���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����A�V���Ȍ��O�A�s���A�^�f�̌����𗘊Q�W�҂̒��ɑn��o���܂��B���ɑΉ��̓��e���u�����x�����ː��p���������v���̐l�����̈ӂɓK�����̂łȂ��Ƃ��A�f���������͏��Ȃ��Ƃ��ނ�̔�����^���Ɏ~�߁A�v���ȍs���������ĉ������Ƃ����u���Ӂv��ނ�ɓ`���邱�Ƃ��ł��܂��B
�i4�j�u�_��v�iFlexibility�j
IAEA�́u�_��v���u���Q�W�҂̕K�v�ɍ��킹�ď������鎩�����A�Ȃ�тɒ������I�v��Ɋւ���ߋ��̌����K�v�ɉ����ĕύX����\�́v�ƒ�`���Ă��܂��B����҂⎖�Ǝ҂͂Ƃ�������`�Ɋׂ�킯�ł����A����ł͑ʖڂƂ������Ƃł��B�ނ��덑���◘�Q�W�҂̗v���ƕK�v�ɉ����āA�������������I�ł���A��������Nj����邤���Ń}�C�i�X�łȂ�������S�O�Ȃ�����ς��Ă����Ƃ����p����Y��Ă͑ʖڂł��邱�ƁA�ߋ��̐������X�ɉĂ��������������Ȃ��Ɓu�����x�����ː��p����������v�̂悤�ȐV�������̂������͂ނ����������Ƃ��A����IAEA�̌����͎����Ă��܂��B
�i5�j�u�葱���̌������v�iProcedural Fairness�j
���̌��t�͂��܂���{��I�ł͂���܂��A�ꌾ�Ō����Ă��܂��A�u�����⎖�Ǝ҂͌������傩���ӂ������čs������v�A�u������Ȃǂ͈���Ȃ��v�A�u����������U��Ȃ��v�Ƃ����悤�ȈӖ��������܂��t�ł��B�ŏ����甽�Ύ҂�b����������r������Ƃ������Ƃ��A�u�葱���̌������v�ɔ����邱�ƂƂȂ�܂��B���ɂ����̓_�Ɋւ��āA�����₩�Ȍl�I�o��������܂��B�א���t�̉��ō]�c�܌�����i�Ж��A�j���Ȋw�Z�p�������Ō��q�͈ψ��������˂Ă�������A���܂����͌��q�͈ψ���Łu�����v���啔��v�̈ψ��߂Ă��܂����B���̎����߂č]�c���q�͈ψ����̃C�j�V�A�e�B�u�Ō��q�͈ψ���Ɂu�ӌ����揀���ψ���v���݂����A�����ψ��̈�l�ɑI��܂����B����5�N12���̂��Ƃł����B���̋L���ł́A���̈ψ����12��28���܂łقƂ�ǁu���Ӂv�W�܂��āu�i�����́j���ӌ�����v�̍\�z�����܂����B�������قƂ�ǖ���o�Ȃ��āA�����̋c�_�Ɏ����X���Ă���܂����B���̎����߂Č��q�͈ψ����Ấu���ӌ�����v�Ɍ��q�͂ɔᔻ�I�Ȑl�������A�ӌ����A�������ׂ����̂�����Ύ�����邱�Ƃ����܂�܂����B���̌�A�u�~���c�v�A�u�V���|�W���[���v�A�u������v���X�A���̂͂��낢��ς��܂������A�u���q�͔��̐l�тƂ������Ĉӌ����v�Ƃ������͍����Ȃ��r�₦�Ă��܂���B�]�c���q�͈ψ����̉p�f�ł������Ƃ����ׂ��ł��傤�B�������Ƃ��ẮA�����o�ɂ�čŏ��̐V�N���������A�u���ӌ����v���Ƃ��̂��̂��`�[�����Ă��Ă��邱�Ƃ�������ƐS�z�ɂȂ�܂��B
�ߋ��̎��s����w��NRC�\�\�u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����̃K�C�h���C���v
���̂�����ŁA�u���Ȃ��w���q�͌����x��w���q�͍L��x�łȂ��A�w�p�u���b�N�E�R�~���j�P�[�V�����x�Ȃ̂��v�Ƃ������Ƃɘb���ւ������Ǝv���܂��B
�u���q�͌����v�Ƃ����̂́A�������t�ł��B���X�́u�p�u���b�N�E�q�A�����O�v�Ƃ����p����u�����v�Ɩ��̂ł��傤�B�u�����v��u������v�Ƃ������t�͗��j���Â��A�ꊴ���Â������čd���B�������łȂ��A�܂��Ɂu�����v�̓������v���v�����錾�t�ł��B���ĎЖ��A�̍]�c�܌������q�͈ψ����߂��Ă�������A�]�c�ψ����̃C�j�V�A�e�B�u�Ō��q�͈ψ����Ấu�i�����́j���ӌ�����v�������܂����B�����u�����v�ł��A�u�����v�Ɓu���ӌ����v�ł͈�ۂ��S���Ⴂ�܂��B�u���v�����炱���A�u�i�����́j���ӌ����v�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
��������A�A�����J�ł������悤�ȕ����������ƂȂ�܂����B����܂ł̂������d����Ŕj���邽�߂ɁA�u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ������n����A�����iNRC�\�\���q�͋K���ψ���j�ƍ����Ƃ̑Θb��i�߂悤�Ƃ������݂�NRC�̓��������Ă���܂����B����ɂ��ANRC�ł́u�p�u���b�N�E�����[�V�����Y�v�i�L��j�Ƃ������t���g���Ă��܂���B���̑���Ɂu�p�u���b�N�E�C���t�H�[���[�V�����v��u�p�u���b�N�E�R�~���j�P�[�V�����v���g���n�߂܂����B���{�ł́uPA�v�Ƃ����Ă���u�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�Ƃ������t���A���܂̓A�����J�ł����[���b�p�ł��قƂ�ǎg���Ȃ��Ȃ�܂����B�uTo enhance public acceptance�v�̂悤�ɕ��͂̂Ȃ��ł͎g���܂����A�����ڕW�Ƃ��Ắu�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�͂��͂�g���Ȃ��Ȃ����̂ł��B���̂��ƌ����܂��ƁA�u�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�ɂ́A�u���O����e���邱�Ƃ�O��ɂ�������I�ȉ����t���v�̌ꊴ�������A���{�@�ւ⌴�q�͎Y�ƊE�����̂悤�Ȍ��t���g�����Ƃ͕s�ސT�ŕs�K�Ƃ����F�����A�悸�����̑�����A�����Ă����������t�����܂�[���l���Ȃ��Ŏg���Ă������{�@�ւ⌴�q�͎Y�ƊE�ɂ��Z�����Ă���������ł��B�ł�����A��قlj��搶���G���ꂽ�u�����m���q�͉�c�v�iPBNC�j�ł́A����Ɂu�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�Ƃ������t���g�����Ƃ�10�N�ȏ���O�ɂ�߁A���̑���Ɂu�p�u���b�N�E�C���t�H���[�V�����E�A���h�E�A�E�g���[�`�v�i���O�Ɍ��������я��j���g�����ƂɌ��߂܂����B���{�ł͑��ς�炸�u�p�u���b�N�E�A�N�Z�v�^���X�v�Ƃ������t���g���Ă��܂����A����͒P�Ɍ��t�̖��ł͂Ȃ��āA���t�̔w��ɂ���u���{����ь��q�͎Y�ƊE�ɂ�錴�q�͂̈���I�ȉ����t���͕s�K�v�Ƃ��鋭�����̗��ꂪ���邱�Ƃ𗝉����Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ȃ��ƁA���ꂩ��͑�O�̍s���┽����ǂ݈Ⴆ��Ƃ����ԈႢ��Ƃ��₷���Ȃ�܂��B����͍���A���ɐ��{�@�ւ⌴�q�͎Y�ƊE�ɂƂ��Ē��ӂ��ׂ����Ƃ̈�ɂȂ邾�낤�Ǝv���܂��B
�u���q�̓R�~���j�P�[�V�����v�́u�Θb�v�Ƃقړ��`��ƍl���Ă�낵���Ǝv���܂��B����ɂ́u��b�v���܂܂�܂��ˁB�悭�R�~���j�P�[�V�����̐��Ƃ����͌����܂����A�ł��L���ȃR�~���j�P�[�V�����́u�Θb�v�Ȃ�ł��B�u��Έ�̉�b�v�A���邢�́u�~���c�̂悤�ȏ��O���[�v�ł̑Θb�v�̂悤�ɁA�N�����N�ɑ��Ă����₪�ł��A�������Ԃ��Ă���悤�ȏ����グ�邱�Ƃ��A���ꂩ��̃R�~���j�P�[�V�����̏��ݒ肷�邤���Ŕ��ɏd�v�ł���܂��B����̕ω����u�Θb�d���̕������������Ă���v���Ƃ��������F������K�v������ł��傤�B�u�C���^�[�l�b�g�v�̂悤�ȐV�����֗��ȃR�~���j�P�[�V������i�����B�������قǁA�l�ƌl�̐S�����Ԑ̂̃R�~���j�P�[�V������i�i�Ⴆ�A�菑���̎莆��ʂƌ���������b��Θb�j�̕⊮�I�d�v���������̂ł��B���̂悤�Ȃ킯�ŁA�����́u�p�u���b�N�E�R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ����e�[�}�́A�܂��Ƃ����X�����̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B
�����ɁA�u���b�J�}�E���e���E�v���W�F�N�g�v�ɑ���NRC�̔��Ȃ�Ԃ����������܂܂�Ă��܂��B�u�����x�����ː��p����������v�̑I��Ɋւ��āANRC�͐����I���s���J��Ԃ��Ă��Ă��܂����ANRC�̈̂��Ƃ���͂����������s�̌������Ƃ��Ƃ�܂ŕ��͂��Ă��邱�Ƃł��B���ʁA���͂Ƃ����ƁA�������������̂����O�҂����͂���킯�ŁA���͂R�O�N�ȏ�A���܂��܂Ȑ��{�֘A�̈ψ���ɌW����Ă��܂������A���̊ԁA���������������̂���Ă������Ƃ����ȕ]�����āA���������������͂����Ƃ����o���͂قƂ�ǂ���܂���B������NRC�͂܂��ɂ��������Ă̂����킯�ł��B�������A���͂������ʂɊ�Â��āA���s�̌����𖾂炩�ɂ��A�������̕��@������̎�ō��肵�ĐV�������@�_��ł��o���܂����B���̕��@�_�̈��NRC�̑g�D�Ɋւ�����̂ŁANRC�ɂ���܂ő��݂��Ȃ������u�R�~���j�P�[�V�����ǁv��V�݂��A�s���ƃR�~���j�P�[�V�����̑o���̌o�����L�x�Ȑl�����u�R�~���j�P�[�V�����ǒ��v�ɔ��F�A�V�C���܂����B����ɂ͓�����NRC�̈ψ�������z�����Ȋw�҂ł�����A�o���̖L�x�ȍs�����ł����������Ƃ��K�������Ǝv���܂��B�ނ͎����̌o������R�~���j�P�[�V�����̏d�v���𐳂����F�����ANRC�Ɂu�R�~���j�P�[�V�����ǁv��V�݂��邱�Ƃ𑼂̌��q�͋K���ψ������Ɏ���A���ɖ����v�̎^���邱�Ƃɐ��������̂ł��B
���̌��ʏo�Ă����A�E�g�v�b�g�������܂��B�ЂƂ́A�Q�O�O�S�N1���ɏo���ꂽ���̂ł����A�u�O�����X�N�E�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ���K�C�h���C���v�Ƒ肷��NRC�̃X�^�b�t�p�ɏ����ꂽ�u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v�̎�����ł��B���̎�����́u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v�̎�ł���O���́u�X�e�[�N�z���_�[�v�i���Q�W�ҁj�����ɑ��āANRC�̃X�^�b�t�͂ǂ̂悤�Ƀ��X�N�ɂ��ăR�~���j�P�[�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�܂��A���������R�~���j�P�[�V�����s���ɂ͂ǂ̂悤�ȎЉ�I�A�S���I��肪�t�����Ă��邩��₷������������̂ł��B
���́u�K�C�h���C���v�̃e�L�X�g��WORLD WIDE WEB (www) ����ȒP�Ƀ_�E���ł��܂��B�܂�WEB�́uNRC�v(U.S. Nuclear Regulatory Commission) �ɓ����Ă��������āA�uReading Room�v���N���b�N����ƁANRC�̏o�ŕ�����ޕʂɏo�Ă��܂��B�����ŁA���́u�K�C�h���C���v�̔ԍ� (NUREG/BR-0308) ��T���ăN���b�N���Ă��������B�e�L�X�g�Ɛ}�\�͂��Ȃ�啔�̂��̂��A���A�S�̂Ƃ��č������̂���J���[����́u�K�C�h���C���v�ł��B���́u�K�C�h���C���v�ɂ́u�ǎ҂ɓǂ�ł��炤���߂ɂ́A�o�ŕ��ɂ͑����ȍ�����������������悤�Ȃ��̂����邱�Ƃ��]�܂����v�Ƃ�����|�̎w�E������܂��B�܂��ɂ��̎w�E�ʂ�ɐ��삳�ꂽ�u�K�C�h���C���v�ł��B�u�K�C�h���C���v�̓��e�͔��ɖȖ��Ŗ��x�̔Z�����̂ł��B����(8�y�[�W)�����Ă��������܂��ƁA�u�O�����X�N�E�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ���K�C�h���C���v�̖ڎ�������܂����A����͂����E�X�Ƃ��������d��������܂���B�S���w�҂����Ă��A�Љ�w�҂����Ă��A���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����̐��Ƃ����Ă��A���ꂾ���ԗ��I�Ȃ��̂��A�悭���܂�NRC�Ƃ����A�R�~���j�P�[�V������X�N���͂�X�N�Ǘ��ɒ��ڊW�̂Ȃ����{�@�ւ���肠�������̂��Ƃ������ƂɊ������܂��B�V�݂��ꂽ�u�R�~���j�P�[�V�����ǁv����ѐV�C�́u�R�~���j�P�[�V�����ǒ��v�̍ŏ��̎d���̐����ɁA�h�ӂ�\���鎟��ł��B
�����ЂƂ̃A�E�g�v�b�g�́A�Q�O�O�S�N�P�Q���Ɋ��s���ꂽNRC�̃X�^�b�t�Ɉ��Ă�ꂽ�u�������X�N�E�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ���K�C�h���C���v(NUREG/BR-0318)�ł��B���{�ł��A�܂��ǂ��̍��ł������ł����A�ł����G�Ȑl�Ԍ��ۂł���u�R�~���j�P�[�V�����v�ƍH�w�I���i�ƌ��ۂ̏W�ςł���u���q�́v�Ƃ́A����Ȃɑ������ǂ��킯�ł͂Ȃ��̂ł��BNRC�́A���Ƃ��ƌ��q�͋Z�p�ҏW�c�ł��B����NRC�������̂悭�Ȃ��u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v����v�ȕ��@�_�Ƃ��đ��푽�l�ȁu�X�e�[�N�z���_�[�v�i���Q�W�ҁj�����ɐڂ��Ă�������A���q�͋Z�p�ҏW�c�̍\�����̃����^���ȉ������璅�肵�A���X�Ɂu���X�N�E�R�~���j�P�[�^�[�v�Ƃ��Ă̎��H�I�\�͂�g�ɂ��Ăق����Ƃ����l������A�u�������X�N�E�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ���K�C�h���C���v�����삳�ꂽ�킯�ł��B
�u�O�����X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v�Ɓu�������X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v�Ɋւ���Q��ނ́u�K�C�h���C���v�����삳���O�ɁA���ۂɂ͑傪����ȁu��b�����v�����{����Ă��܂��B�ڍׂɂ͗�������܂��A�����������������������炱���A�Q��ނ́u�K�C�h���C���v�̃V�i���I���������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�����̌��ʂ́u�O�����X�N�E�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ���NRC�K�C�h���C���̋Z�p��̊�v(NUREG/CR-6840)�Ƒ肷����ɓZ�߂��Ă��܂��B���̕����O�q�̂Q�́u�K�C�h���C���v�Ɠ��l�AWEB����_�E�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�Ō�Ɉꌾ�\���グ�����̂ł����A�u�����x�����ː��p����������v�J�݂Ɋւ��āA���{�A�d�͎��ƎҁA���q�͎Y�ƊE�����ꂩ��g���u�����i���ˁj�v�͔���Ȋz�ɂȂ�܂��傤�B���ꂩ��n���Ƃ̌��ɗv���鎞�ԁA��p�A�J�����u�����i���ˁj�v�Ɋ��Z����Δ���Ȃ��̂ɂȂ�Ǝv���܂��B����炪���ׂč����̕��S�̏�ɐ��藧���Ă��邱�Ƃ�Y���ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤�B����ɁA���܂ł́u��������������Ή��Ƃ��Ȃ�v���オ�����Ă��܂������A�ŏ��ɐ\���܂����悤�Ɏ�������l�ς��ς���Ă��Ă��܂��B�ǂ������͕ʂɂ��āA�u���̂̂�����́v(����)����u���̂̂Ȃ����́v(���)�։��l�̏d�S���ڂ����悤�Ɏv���܂��B���̈Ӗ���2005�N�ɓ��{�ŋN�������o�����\�\�Ⴆ�A�^�j��ȏO�@���I����O�㖢���̃e���r�ǔ������\�\�͏ے��I�ł��B�u�����i���ˁj�v�������̐S�������̂ł͂Ȃ��A�u���v�������̐S��h���Ԃ����̂ł��BIAEA��NRC���ߋ��̌�肩��̔��ȂƂ��āu����(����)�v��������̓I�ȁu�����v��u���X�N�E�R�~���j�P�[�V�����v���u�����x�����ː��p����������v���̉����̕K�v�����Ƃ��Ď�����Ă��܂��B���{�ł͐V�����@�����ł��Ă��A�n�悮��݂́u�����x�����ː��p����������v���Ή^�����ˑR�Ƃ��đ����Ă��܂��B�u���q�̓R�~���j�P�[�V�����v���uNIMBY�v�nj�Q�Ɍ����ǖ�ɂȂ邩�ǂ������A����̌��ƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���^����
�{�����
�\�肵��3�̍u�����I���܂����B��30�����Ԃ�����܂��̂ŁA���ꂩ�玿�^�̎��ԂɈڂ肽���Ǝv���܂��B����₲�ӌ��̂�����́A����̏�A�����Ƃ����O�����Ă��b���������B
�i�����A�j�n���ɂ�����̂����A�����x���̖����܂߂ė��n���ɌW��邱�Ƃ������B���n�̐^�������ɂ���ƁA�����e�͗����A�˕ʖK��͂����A�ŁA���q�͂Ɋւ�����ʂɗ^������B���������ɂȂ�ƁA���炩�ɒ������n���̕�����x���������ɂȂ�B�Ƃ��낪�A�ő�̗��v����҂͒����ɂ��āA�����ł̃R�~���j�P�[�V�������i��ł��邩�ƌ����ƑS���i��ł��Ȃ��B���������n���ƒ����̃R�~���j�P�[�V�����M���b�v������ǂ̂悤�ɉ������Ă����̂��A�c���搶�ɂ������������B
�i�c���j��Ƃ��肩�Ǝv���BNRC�̃��b�J�}�E���e�B���ɐ��s�̏����̎��s�Ⴊ�Q�l�ɂȂ�Ǝv���B�ŏ��ނ炪�n���ɑ��Đ�������J�������ɂ�NRC�͉�����肽���̂��A�Ƃ���NRC���̈���I�Ȑ��������ŁA����邠�Ȃ������͂ǂ������Ă����?�Ƃ�������͈��NRC����o�Ȃ������B����ŁA�����Ă�����͂��炯������Č����Ɏ��s����킯�����ANRC���������ɕ��͂��āA��̑Ή����܂Ƃ߂��B��́A�����ɍs���Ƃ���ɂ��Ď��O�ɂ悭���ׁA�c��������ŏo������B�����Ă����l�������Ă�����_�͉��Ȃ̂����悭�m������ŏo������A�Ƃ������ƁB�}�X�R�~�ɂ��Ă������邱�Ƃ����A���i���邢�͓ǂ�ł����j���肪�ǂ�Ȑl���S�R�m��Ȃ��Ō�낤�i�������j�Ƃ���̂́A�R�~���j�P�[�V�����̖@���ɍ����Ă��Ȃ��B��߂́A�n�w�����Ƃ����ɂ߂ĉȊw�I�Ȃ��Ƃ������ɑf�l�ɕ�����悤�ɐ������邩�A���̐����̎d���ł���B�ʼn��̂��̂��̂̈��S���ɂ��Ă��A���N�ɑ���e���]���ɂ��Ă��A�n�w�̈��萫�ɂ��Ă��A�Ȋw�҂̌��t�Œ�������A�n�����́A�킴�ƕ�����Ȃ����t�Œ����ĉ��Ɋ����C���ƁA�{���Ă��܂��B�����ŁA�R�~���j�P�[�V�������Ƃ������̂�����Ăǂ���������������Ε������Ă��炦�邩�������������B���{�ł����l�̂��Ƃ�����B�u�Ђ��v�Ƃ������t�Ɂu�픚�v�Ɓu����v�̓�ʂ�̈Ӗ������邪�A�����Ă������ł͂ǂ������Ӗ�����̂�������Ȃ��B���ː�������́u����v�́A���Ƃ��Ɖp��́uexposure�v�����Ȃ̂ŁA���炳���Ƃ����\���ɕς��Ă������Ǝv���̂����A�O���`�̓��{�ł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ�Ȃ��B
�ȏ�̂��Ƃ�NRC�̃K�C�h���C���ɔ��f����Ă��邪�A����ɂ��̒��ŎQ�l�ɂȂ�̂́ANRC�Ƃ͉��̂��߂ɂ���̂��A�����NRC�̐E���̈ӎ��ɓO�ꂳ�������ƁB���q�̗͂l�X�Ȍ��ۂ��獑���̈��S����邽�߂�NRC�͂���̂��A�Ƃ������Ƃ��ĔF�������āA����������ƐڐG����ۂ̊�{�ɐ�����悤�ɂ��������ƁB������ANRC�����̃A���P�[�g�����̌��ʁA�����ʂłɂ���Ƃ����Ȃ��Ō��e�̖_�ǂ݂�����悤�Șb���肪�����Ƃ̎w�E���o�Ă��āA�b��������Ƃ��͑���̖ڂ����Ď����̌��t�Řb��������Ƃ����悤�Ȋ�{�I�Ȃ��Ƃ��K�C�h���C���ɂ͏����Ă���B
NRC�����O���̖@���ɂ����邱�Ƃ�����̂ŁA�����ɂ��̗����@���̍l������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������B�������������ɂ̓K�C�h���C�������炵�č��ؒ��J�ɐ�������BNRC�́A�����ł͂Ȃ��āA�����Ƃ���ɂ��[�����R�~���j�P�[�V�����̊�{�ł���Ƃ̔F���̏�ɃR�~���j�P�[�V����������W�J���Ă���B
�i�����B�j�y���搶�̂��b�̒��ŁA���C���̊��ƌ��q�͈��S�ɂ��Ē����̏Љ�������B���̉�̃����o�[�\���ɂ��āA�S����16�������A�j����14���A������2���ƏЉ�ꂽ�B�j���������悢�Ǝv���̂����A����������ɂ��������������̂��A�ǂ�����Ώ����𑝂₷���Ƃ��ł��邩�A���ӌ����f�������B
�i�y���j�j���̔䗦�͋C�ɂȂ邱�Ƃ̈���Ǝv���B���̉������x�������āA�����o�[�ɒj���̃o�����X�����Ă����������Ă݂��B����Ƃ݂ȁA���Ă���Ƃ͎v��Ȃ��A�Ƃ����Ԏ��ł������B�܂�A�Q�������l����l��l�����̈ӌ����q�ׂ��ł��邱�Ƃ��厖�ŁA�j���̔䗦�͂���Ȃɑ厖�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������B
 �@���q�͂͊�{�I�ɋZ�p�I�Ȃ��Ƃ������̂ŁA�����͎Q�����ɂ����B�������g�A���Z�܂ŗ��n�ɂ������A���n�̏����͑a�܂����̒��ň�B���ꂪ���{�̎��ԁB���C���ł����q�͂ɑ��ĕs�����q�ׂ�̂͏����̕��������B�����ĕs�������Ɣ��Δh���ƌ�����B������܂��܂������͐g�������Ă��܂��B�j���̕������������Ƃ������Ƃ͓����ł͂��邪�A�ǂ��̗��n�n��ł����ʂ��Ă���B���������𑝂₵�����Ƃ͎v���Ă��邪�A�K���������ꂪ���ł͂Ȃ��A�ƍ���̌o���Ŋm�M�����B
�@���q�͂͊�{�I�ɋZ�p�I�Ȃ��Ƃ������̂ŁA�����͎Q�����ɂ����B�������g�A���Z�܂ŗ��n�ɂ������A���n�̏����͑a�܂����̒��ň�B���ꂪ���{�̎��ԁB���C���ł����q�͂ɑ��ĕs�����q�ׂ�̂͏����̕��������B�����ĕs�������Ɣ��Δh���ƌ�����B������܂��܂������͐g�������Ă��܂��B�j���̕������������Ƃ������Ƃ͓����ł͂��邪�A�ǂ��̗��n�n��ł����ʂ��Ă���B���������𑝂₵�����Ƃ͎v���Ă��邪�A�K���������ꂪ���ł͂Ȃ��A�ƍ���̌o���Ŋm�M�����B
�@�v���W�F�N�g���I�����NPO�ɂȂ������ANPO�ɂȂ��Ď����I�Ȋ��������߂��Ă���ƁA�����̕��������ȃA�C�f�B�A���o���Ƃ����������o�ė��Ă���B���ł͒j���̊F����A�撣���Ă��������A�Ƃ����ɂȂ��Ă���B
�i�����C�j���R�Ƃ�������ŋ��k�����A�c���搶�Ɏf�������B���{�ł́A���S�Ƃ����S�Ƃ������āA���S�ƐM���Ƃ͌���Ȃ��BNRC�̕����͐M������{�ɂȂ��Ă���ƔF�������B���̕����̒��ň��S�Ƃ����L�[���[�h�͂ǂ̂悤�Ɉ����Ă���̂��H
�i�c���j���S�Ƃ����̂́A���{��Ɠ��̂��邢�͓��{�l�Ɠ��̐S���I��\�����t�̂悤���B���S���p��A�t�����X��A�h�C�c��̎����ň����Ă݂Ă��҂����Ƃ������t���Ȃ��B�ufeeling a peace�|���낢�����������v�����S�ɋ߂��p�ꂩ������Ȃ����A���{��̈��S�ɑΉ�����P��͑��̍��ɂ��Ȃ��̂�������Ȃ��B�������A���{��̈��S�ɑΉ������S����\�����錾�����͂���̂ŁA���́A���鎖�ۂ����̐S����Ԃ�ۏ���̂��ǂ����A�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���q�͂ŋN���鎖�̂͐l�דI�Ȃ��̂ŁA�s�R�͂ɂ�鎖�̂Ƃ������̂͂قƂ�ǂȂ��B�����A���͌l�̖��Ɛ��x�I�Ȗ��ɂ���ƌ��邱�Ƃ��ł���B�����Ď��s�͂��Ď��s����w�Ԃ��Ƃm�ɂ���BNRC���R�~���j�P�[�V�����Ɋ֘A���Ă��Ȃ����ƌ����Ă邱�Ƃɂ́A�ǂ������A�N�V��������������Ƃ������Ƃ��������邢�̓X�e�[�N�z�[�����|�ɒm�点�Ȃ����A�Ƃ������Ƃ�����B���s�̕��͓͂��{�ł���邪�A���X�ɂ��Ă����ςȂ��A�Ƃ������Ƃ������B����ɂ́A��l��2�N���炢�őւ��Ƃ������Ƃ��W���Ă���B�����t�H�[���[�A�b�v���Ȃ����A�S�z���Ă���l�����Ɉ��S���Ă��炤���Ƃ��ł��Ȃ��B�����������Ƃ��������Ƃ��邽�߂ɂ́A�R�~���j�P�[�V�����̐��x��v���Ȃ������A����ɕK�v�Ȑl�ނ�{�����邱�Ƃ��K�v�B
NRC�̃R�~���j�P�[�V�������ł́A���̃��[�_�[�ɂ̓W���[�i���X�g�̌o��������A��@�c���̉������e�����������Ƃ�����R�~���j�P�[�^�[�s�����ĂĂ���B���̕����̐l�I���������{�ɂ͂Ȃ��B�A�����J�����łȂ��A�t�����X��t�B�������h�ł��R�~���j�P�[�V�����̃f�B���N�^�[�̓W���[�i���Y����Љ�Ȋw�̔��m����C�m�����������l�ŏ����������B������ւ�̂Ƃ���͓��{�Ƃ��Ăǂ������Ή������邩�A�܂�A���q�͂̒����炻�������l�������邩�A�O������������Ă��邩�A�������荘�𐘂��čl����K�v�̂���ۑ�ł���B
�i�����D�j�p�u���b�N�R�~���j�P�[�V�������厖���Ƃ������ƂŁA�s�\����������Ȃ����A���Ǝ҂����̕����ɐi��ł���Ǝv���B�Ⴆ�Η��n�ł́A������x�Z���S�̐l�����������Ƃ����ɂȂ�Ȃ��Ɛi�܂Ȃ��킯�����A���̂��߂ɂ́A�����f������@���H�v����K�v������̂��B�Ⴆ�A��c�����J�ɂ���Ƃ��A�J��Ԃ��I�Ȏ�@���g���Ƃ��A�������������Ƃ�����A�S�̂Ƃ��Ă̗����Ɍ��т��Ă����̂��B
�i�y���j�����ɍL���͈͂ɒm�炵�߂�Ƃ������Ƃ͂��Ȃ����������B����ꂽ�l�̊Ԃŗ����̓����Ȃ����̂��͈͂��L���Ă�������������킯���Ȃ��B����ꂽ�l�ɂ܂����������Ē����āA���C���̏ꍇ�ŐS���������Ƃ́A�Z������Z���ւƂ����`���Ă��炤�Ƃ������ƁB����2�N�����ɖ�肪�N���鐢�̒��Ȃ̂Ŏ��Ǝ҂⍑�ɑ���Z���̐M���͉s�\�ȏɂȂ��Ă���B���Ǝ҂�������撣���Ă�������A���Ԃ̏Z�����m�œ`����Ƃ������Ƃ͊C�O�ł͍s���Ă���B���R�~�ɂ����ʂ̕����p���t���b�g���X�I�ɔz������ʓI�B�p���t���b�g�͔z��Ό��Ă����Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�S�̂���l�������Ă���Ȃ����A�����Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�Ƃ����킯�ł��Ȃ��B���C���̌o���ł́A�n���ɂ�邱�Ƃ��厖���Ǝv���Ă���B
�i�c���j�y���搶�̋�Ƃ��肾���A�ꌾ�t�����������B���{�̃R�~���j�P�[�V�����́A���b�Z�[�W�𑗂鑤�����O�̊�̂Ȃ����̂Ƃ����O��̏�Ō�肩���Ă���B���ϒl�I�ȓ��{�l�Ƃ������A�����������̂�����Ă���B����͐�ɂ܂����b�ŁA����̊S�������Ȃ��B���̐l�����Ɏ����̎v�����Ă��炤�̂��A�Ƃ������Ƃ����肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B������Љ�w�ł́u�Z�O�����e�[�V�����v�ƌ����Ă���B�܂�A�ǂ��������������l�X���Ƃ������ނ�����B�j�������A�s��̐l���_���̐l���A�^���̐l�����̐l���A���������l�����̃O���[�v�ɘb��������A�܂胁�b�Z�[�W�����Ƃ����Ƃ������Ƃ����߂č�Ƃ����Ȃ�������Ȃ��B���܂ł͖����ɂ��Ă����Ǝ҂ɂ��Ă������������z���Ȃ������v���B�����������Ƃ̓R�~���j�P�[�V�����̃C���n�ŁA�L���ƊE�ȂǂɊw�Ȃ�������Ȃ��B�Ⴆ�A�����Ԃ�A�p�����Y�Ƃ́A�Ⴂ�l�̐F�̍D�݂͂ǂ����Ƃ��`�̍D�݂͂ǂ����A�Ƃ����s�꒲����O��I�ɂ��B����Ɋr�ׂ�Ɠ��������g���Ă����ݐH���Ɏg���Ċ̐S�v�̂Ƃ���Ɏg���ĂȂ��̂����q�͂��Ǝv���B
���ꂩ��A���f�B�A�̗��p�ɂ��Ă������ƍH�v�������������B���܂�C���^�[�l�b�g�ŏ������݂̂ł���u���O����R����A�����������̂ɏ������݂����Ă���ƁA�Z�O�����e�[�V�������ł��Ă���B�܂�A�Ⴂ�l�����̍l�����Ƃ��A�������Z���V�e�B�u�Ɋ����邱�ƂƂ��A���������������Ă��邵�A����ɑ���Ή��̎d�����������Ă���B�Ώۂƃ��f�B�A�ɂ��Ă���������ƍl���邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂��A���z�ł���B
�{�����
���Ԃ������̂ŁA���̕ӂō����̓��_����I��ɂ��܂��B�Ō�ɂ��u������������3�l�̍u�t�̕��X�ɔ���ł�����������Ǝv���܂��B�i����j�Љ�E������ł́A���̂悤�ȓ��_����t�H�̑��ɂ�����Ă���̂ŁA����Ƃ����Q�����������B
�i���j